|
十八の綱吉がいるべき世界に戻ってすぐ、綱吉は全力で戦うはめになった。戦いながらリボーンからとぎれとぎれに事情を聞いて、綱吉は驚いた。
二十七歳の綱吉が回避した襲撃の変わりに、今現在戦うことになっている現状がよく理解できなかった。もしかしたら、未来の綱吉が辿った道と違う道を今の綱吉が辿りつつあるのか――などという考えが過ぎったが、すぐに目の前の戦闘へ引き戻され、それどころではなくなってしまった。
朝日が昇る前までにどうにか綱吉、了平、リボーンの三名で襲撃犯達を撃破した。
日本国内に拠点を設けているボンゴレの日本支部へリボーンが連絡をいれた。破壊された学校を術師の幻覚によって補うことと、倒した襲撃犯達の身柄の管理をリボーンは日本支部へ依頼した。リボーンは日本支部の人間が来るまではその場に残ると言い、了平のバイクでとりあえずシャマルのマンションへ向かうように綱吉に指示をした。
未来で極度の緊張状態が続き、現代へ戻ったと思えばすぐに戦闘だ。普段の綱吉であれば、リボーンと共にその場に残ると言うに決まっていたが、すでにいまの綱吉にそれほどの気力はなかった。
綱吉は素直にリボーンの言葉に「うん」と頷きを返した。少しおぼつかない足取りの綱吉を心配してか、了平の力強い腕が綱吉の肩をがっしりと支えてくれた。彼は綱吉と目が合うと、初夏の太陽のように明るく爽やかに笑顔を浮かべた。了平の笑顔を見ていると綱吉はそれだけで安心することが出来た。この人が側にいる間は安心していてもいいんだ、悪いことなんて起きはしないんだ――そんな思いを起こさせることに関しては、笹川了平をおいて他にいない。
了平が運転するバイクの後部座席に乗って、綱吉はシャマルのマンションへ向かった。立て襟の外套を身にまとっていたせいか、バイクの速度によってうまれる強い向かい風に当たっても寒くはなかった。
了平の無駄な肉のない引き締まった腰に腕を回してしっかりと掴まって、綱吉は目を閉じていた。
未来では様々なことがあった。骸は果たして無事だったのだろうか。雲雀は綱吉が骸が生きていると言うのなら生きていると言っていた。ならばきっと骸は生きてるのだろう。綱吉が信じることで彼の生存が確定するのならばどんな馬鹿なことでも信じたかった。
いろいろな人間が綱吉のために動いてくれていた。彼や彼女達の思いに答えられるようなことを綱吉は未来に残してはこれなかった。やはり、力不足なのだろう。十年の歳月の重みと深さが綱吉の心にのしかかる。これからの十年で、自分はどれだけ成長し、そして綱吉の周囲で生きてくれている多くの人達からもらった様々なものを、どれだけ返していけるだろうか。いまの綱吉には未知数すぎて分からなかった。とまどいや恐ろしさを感じてないと言ったら、嘘になる。
それでも、綱吉はドン・ボンゴレとして、未来で立ったあの場所へ立ちたいと思っていた。確かに最初は九代目によってお膳立てされ、リボーンによって導かれた場所だ。様々な人間の思惑によって用意された王座が、綱吉の前にあった。
だがしかし、数年の間で、綱吉は用意された椅子に己の意志で座りたいと思うようになった。浅はかだとは思いつつも、高校生活を送るようになってから、綱吉は己に出来ることが思いの外たくさんあることを自覚しつつあった。他の誰かがボンゴレを継いだとしたら、きっと出来ないようなことでも、綱吉がドン・ボンゴレとしてボンゴレを継いだのならば出来るかもしれないということがたくさんあった。ボンゴレは巨大な組織だ。巨大な組織には巨大な権力がある。組織のトップに立つことができれば、権力の矛先を出来るだけ正しい方向へ向けることができるだろう。
偽善的だと言われようとも、それが沢田綱吉のやり方で、生き方なのだ。
未来で見た、未来の綱吉はいきいきとしていた。映像で見た『彼』は人生を謳歌していた。仲間達と笑い合い、暗い顔なんてせずに、精一杯に生きている。きっと今以上に嫌なことや悲しいことがたくさんあるに違いないけれど、『彼』は明るい顔をしていた。内包された強さと信念が『彼』にはあった。
了平の背中にぴったりと頬を寄せ、綱吉は心底思った。
『彼』のようになりたいと。
『彼』の生きる世界が綱吉が生きる世界と繋がっているのかもしれない。
逆に、繋がっていないのかもしれない。
でももうそんなことは、綱吉には関係がないのかもしれなかった。
これから綱吉が歩く道が、『彼』に繋がっているかどうかは――、
その道を行く綱吉にしか分からないことだ。
目指すべきものがはっきりとした今、綱吉のなかに迷いはもうなかった。
了平にマンションの前まで送ってもらうと、マンション前に獄寺と山本、そしてシャマルが待っていた。
バイクから降りた綱吉に獄寺がすぐに駆け寄ってきた。あとから近づいてきた山本が、感極まって立ちつくしていた獄寺ごと、綱吉のことを両腕に抱きしめた。「おかえり」という山本の声を聞いたら、もう駄目だった。綱吉は安堵感からか、獄寺と山本の腕を掴んで泣いてしまった。
綱吉の溢れてきた涙が止まるころには、了平もシャマルもいなくなっていた。山本が言うには、了平はシャマルと何かを会話してから、バイクに乗って来た道を戻っていったらしい。シャマルも手を振り、車で出ていったようだった。
鼻をすすりながら、綱吉は獄寺が導くままに、シャマルのマンションの部屋へ向かった。とてもではないが、中学校の保険医が借りられるようなマンションの設備ではない。思っていたとおり、案内された部屋はだだっ広く、置かれている調度品もどこかのブランド製なのか高級そうだった。シャマルの部屋の雰囲気が、未来のボンゴレ邸の部屋の雰囲気に少し似ていて、綱吉はリビングルームの入り口で立ちつくしてしまった。
「ツナ?」
山本が背中を丸めて、綱吉の顔を伺うように見た。綱吉は首を振って、獄寺が導くままに、リビングルームの奥に用意されているソファに近寄っていった。獄寺が片手で示すソファへ綱吉は座った。
やわらかいソファに身体を沈める。背中でソファにもたれて目を閉じると、眠ってしまいそうなほどに心地が良かった。綱吉の隣に山本が自然な動作で座る。綱吉と目を合わせた山本は、小さく「あ」と声をあげて近くに立っていた獄寺へ顔を向けた。
「なぁ。獄寺、お湯でぬれタオルつくってきてくれよ。ツナ、鼻血のあと顔に残っちまってる」
「あぁ! 気が付きませんで、申し訳ありません! 十代目! すぐにご用意してきます!!」
綱吉が何かを言う前に、獄寺がどこかへ行ってしまう。とっさに持ち上げた手を下ろして、綱吉は隣に座っている山本を見上げた。彼は首を傾げ、双眸を細めて笑った。
「どーかしたか?」
「ううん。帰ってきたなあって、そう思って」
「あっちでは、大変だったみてぇだな。……痛いんじゃね?」
山本が己自身の顔を指さして、心配そうに眉を寄せる。確かに殴られた場所に痛みはあるが、心はもうすでに落ち着いている。山本がいて、獄寺がいる。二人が側にいるという安堵感のほうが強くて、痛みなどほとんど二の次だった。
「そんなに痛くないから平気だよ。湿布でも貼っておけば、腫れはすぐにひくだろうし」
「あーぁあ。せっかくのツナの可愛い顔がもったいねーな」
「こら。さらっと、可愛いって言わないでよ。オレはね、男なんだからさ。男の傷は勲章じゃん」
「……ふ、ははは。そうだな。男の傷は、勲章だ」
「あ。……なんか、ちょっと馬鹿にしてない? 山本」
「だって、なー。ツナの口から『男』とか言われてもなー、迫力ないもん」
「やーまーもーとー」
口元を引きつらせながら綱吉が片手を震わせながら持ち上げようとしていたところへ、獄寺が駆け戻ってくる。手には白い柔らかそうなタオルが握られている。すこし湯気がたっているタオルを獄寺は両手で綱吉へ差し出す。
「十代目。どうぞ」
「ありがとう。獄寺くん」
温かいタオルを手にとって、綱吉は顔を拭った。思っていたよりも血が出ていたのか、白いタオルは赤黒く染まっていく。乾いた血で鼻が詰まっているような気がしたが、無理矢理に鼻をかんだりすれば、また出血するかもしれない。シャマルに診てもらってからのほうがいいだろうと考え、綱吉はタオルで顔と首筋を拭うだけにした。すべて拭い終わって、汚れたタオルを目にした瞬間、家主であるシャマルに何の許可もなくタオルを血で汚してしまったことに気がついて、綱吉は慌てた。
「あ、あのこれ、シャマルんとこのタオルだよね?」
「ええ、そうです。あいつん家のですけど、平気ですよ。あいつ、金は有り余るほど持ってんで平気ですから。――それ、もうよろしいですか?」
「あ。うん。ありがとう」
血で汚れたタオルを受け取った獄寺は、綱吉の顔を眺めて満足そうに頷いた。
「綺麗になりました。――これ、処理してきますね」
綱吉よりもよっぽど綺麗な顔に微笑を浮かべ、獄寺はリビングルームから姿を消した。彼はすぐに戻ってきて、綱吉の側に立った。座らないのか?と聞いても、獄寺は微笑んでいるだけだった。獄寺はいつもそうだった。綱吉が座っていれば、そのすぐ隣に立っていた。いつからか、綱吉の隣の席に座ることはなくなっていた。彼の態度が次第に主従という型にはまっていくことを、どうあがいても止められないのだと綱吉は覚悟していた。獄寺が己の立ち位置を決めてしまった以上、綱吉がいくら近づこうとしても、彼は後退してしまう。距離は縮まらない。じわりと寂しさと悲しみが綱吉の心の隙間を伝い落ちる。友達で親友。ドンと右腕。どんな関係性であろうと、綱吉にとって獄寺が大切な人間であることに替わりはない。
「十代目?」
無意識に獄寺のことを見つめてしまっていたのか、ハッとした綱吉は反射的に笑顔を浮かべて、姿勢を正した。
「えっと……。ほんと、みんなにはいろいろ迷惑をかけちゃって……。ごめんなさい」
「いいんですいいんです、十代目がご無事だったんなら! もう俺はそれだけで嬉しいです……、十代目ェ……」
いきなり膝からくずれおち、絨毯のうえに膝をついた獄寺が、綱吉の座っているソファの肘掛けに両手をおいて、顔を伏せてしまう。ぎょっとした綱吉は両手を持ち上げて、獄寺の肩においた。
「え、ちょ……ッ、獄寺くん、泣かないでよ」
「そうだぞ。獄寺。ツナが困ってるだろー?」
「うるせえなっ。これはなっ、涙なんかじゃねぇ!」
がばっと顔をあげて山本を怒鳴りつけた獄寺は、眉をつり上げていた顔を瞬時に切なげな表情へ変え、若干潤みつつある目で綱吉を上目遣いに見た。
「十代目が無事に戻っていらっしゃって、本当に俺は嬉しいです。……未来の十代目も、そりゃあ格好良くて渋くてたまんなかったっすけど、俺はあなたにお会いしたくてたまらない気持ちにもなりました……。俺にとっての十代目は、やっぱり、あなたしかいないと、そう……」
言葉を切って、獄寺が頷く。
綱吉はそんな獄寺の頭を片手で撫でて、彼と同じように頷いた。
「うん。ありがとう。獄寺くん。――あのね。獄寺くんに頼みたいことがあるんだ。オレ」
「はい! この獄寺に出来ることならば、なんなりと!!」
「イタリアへ渡ったあと、オレのいたらないところとか指摘して欲しいんだ。獄寺くんのほうがマフィアの社会のこと知ってるだろうから。いろんなことをオレに積極的に教えて欲しいんだ。オレ、頑張るから。みんなのこと守れるように、十代目として、ちゃんとするから」
綱吉の言葉がじっくりと染みていくのを感じるように、獄寺は綱吉のことを瞬きを忘れたような瞳でジィッと見つめていた。獄寺は綺麗な顔をしているので、真っ直ぐに見つめられると綱吉は落ち着かない気分になる。苦笑を浮かべて首をかしげて、彼の視線に照れている自分を誤魔化した。
「……十代目……」
吐息のような声でつぶやいて、獄寺は顔を伏せてしまった。
何か悪いことでも言ってしまっただろうかと綱吉が不安に思って口を開く前に、山本が「うーん」と気の抜けたような声を出した。隣に座っている山本を見ると、彼はまじまじと綱吉のことをみて、あけすけな笑顔を浮かべた。
「ツナ。なんか変わったのな」
「うん?」
「実は俺、卒業式のあたりのころ、ツナが悩んでんのかなぁとか思ってたんだ」
どきりとして、綱吉は思わず表情をこわばらせてしまった。
山本は「やっぱりなー」と小さく呟いて、片目を細める。
「……山本はよく見てるよなあ」
山本は微笑むだけで何も言わなかった。
短いため息と共に迷いを吐き出し、綱吉は素直に話を始めた。
「……悩んでたっていうか……、やっぱり、知らない土地で知らない人達と会って、そこから新しい絆を築いていくのって、ものすごいエネルギーが必要じゃない? だからたぶん、緊張のしすぎで気が張ってたのかも。――でももう、大丈夫」
「ほんとですか?」
顔を伏せていた獄寺が顔をあげ、絨毯のうえに両膝をついたまま、真剣な眼差しで綱吉を見上げてくる。彼のまっすぐな視線から逃れようとせず、綱吉は答える。
「うん。――オレが見た未来には、みんながいたんだ。だったらオレは、すべてを信じて、真っ直ぐに道を進めばいいんだって思えたから。もう大丈夫。それにさ、獄寺くんも山本も、一緒に来てくれるんだもの。親友ふたりが側にいてくれるなら味方が少ないイタリアの土地でも心強いよ」
「そうだぞ。ツナ。俺達がついてるし、雲雀や了平さんもいるし、それにあれだ、小僧も一緒だろ? みんなで力をあわせりゃ、無敵だっての」
「うん。……うん、そうだよね、無敵だよね」
綱吉は頷きながら、笑顔を浮かべる。
すぐ近くで、ぐすりと鼻をすする音が聞こえてくる。綱吉は片腕で目線を覆っている獄寺の背中に手を伸ばして、何度かさすった。
「なんだよ。泣いてんのかー? 獄寺」
「うっせぇ!」
獄寺が叫んだと同時に、玄関側の廊下とリビングルームとを遮っていたドアが開いた。入ってきたのは、スーツ姿のシャマルとリボーンだった。了平の姿はない。
ソファセットにいる綱吉達を眺めたシャマルは、戸口辺りに立ったままで獄寺を半眼で見つめ、唇をへの字に歪めて息を吐く。
「一番うるせぇのはおまえだろ、隼人。――そんだけ元気なら、おまえらもう帰れよ。おっさん、疲れてへろへろなんだからさー」
「十代目はお疲れなんだ! もうすこし、この部屋でお休みになってからご帰宅されたほうがいいに決まってんだろ!」
「はいはい。そうですか。ご勝手にィ――。でもここ、俺の部屋、なんですけどねえー」
リボーンは部屋を横切って綱吉のもとへ真っ直ぐに歩いてくる。
綱吉がよく知っている、五歳のリボーンだ。
ローテーブルを挟んだ綱吉の向かい側のソファに座り、リボーンは小柄ながらもしなやかな仕草で足を組んだ。小さな足にひっかかっているスリッパの先が揺れた。
「具合はいいのか?」
リボーンの問いかけに綱吉は正直に答えた。
「痛いけど、耐えられないほどじゃないよ」
「随分とヒデェ有様なんじゃないの、ボンゴレ坊主」
戸口に立っていたシャマルがソファーセットの方へ近づきながら言う。
「頭痛はしたりしねぇか? 身体のどこかに違和感があるとか?」
「とくにないよ。……殴られたとこが痛いだけ」
リボーンが座っているソファの後ろの立ったシャマルがジィッと医者の目をして綱吉のことを熱心に観察する。そうしているシャマルのほうが、普段のシャマルよりもよほど男前なのではないか――と綱吉は思ったが、口にすると彼が調子にのるのでやめておいた。
「殴られたのは素手でか?」
「素手と、……あと拳銃のグリップのとこで殴られたのと、顔を蹴られた、かなあ?」
「十代目にひでぇことしやがって!!」
急な大声に驚いて、綱吉はとっさに隣に座っている山本の服の袖を掴んでしまった。獄寺は立ち上がり、握り込んだ拳をぶるぶると震わせながら、宙を睨み付けている。
「俺がぶち倒してやりますよ!! どこのどいつです!?」
短く息を吐いて、綱吉は山本の袖を掴んでいた手を放し、かわりに獄寺の服の裾を掴んで引いた。
「どうどう、獄寺くん落ち着いて。未来の人だから、どうにもならないよ」
――それに、デッセロは死んでしまった。
ディンツオに殺されてしまった。
銃弾によって割れた頭蓋骨から流れ出る血を思いだして、綱吉は思わず苦いつばを飲み込んだ。鼻先に香った血の香り、酸っぱい臭いがよみがえってきて、気分が悪くなってくる。
「ツナ」
いつの間にか伏せてしまっていた顔をあげる――、その先にリボーンがいた。綱吉の名を呼んだ彼の、ふわりとしたまつげに彩られた黒い大きな瞳が静かに綱吉のことを見つめている。
綱吉は帰ってきた。
ここにはもう死体はない。
小さく口を開いて息を吐き出して、綱吉は口元に笑みを浮かべる。リボーンの眉間にわずかなしわが刻まれる。彼は背後にいるシャマルを肩越しに振り仰ぎ見た。シャマルはリボーンの視線を受けてから、綱吉へ視線を向けた。
「念のため、脳の検査してみたほうがいいんじゃねぇかな? ボンゴレ坊主」
「万全を期しておいたほうがいいだろ。こいつに何かあったら、すべてが終わりだ」
「一休みしてから、ボンゴレ坊主は俺とデートだな」
「――検査するの? おおげさじゃない?」
「しておけ。ついでに、健康診断もしてもらってこい」
言葉は静かだったが、リボーンの視線にははっきりとした強要が含まれている。綱吉は特に反抗する要素もなかったので、素直に頷いておいた。
「……うん。分かった。お願いします、ドクター・シャマル」
「オッケーオッケー。任しときな」
かるいノリで片目をとじたシャマルを見て、獄寺が苛立たしげに鼻から息をつく。そんな彼の様子を横目で見て、山本がおかしさをこらえるように口元をゆがめる。綱吉は山本と視線を合わせ、小さく笑った。
「――あ! そういえば、そっちはどうだった? あいつら、ちゃんとボンゴレに引き渡しできた?」
「ああ。あとは、あっちが片づけてくれるだろうよ。なにしろ、未来のボンゴレ十代目の暗殺にボンゴレ内部の人間が関わっている可能性が出てきたんだからな」
「は?」
「え」
「うん?」
綱吉、獄寺、山本が同時に呻くのを見て、リボーンは面白がるように双眸を細めながら続けた。
「ボンゴレの人間じゃねぇが、同盟ファミリィの中の連中が徒党を組んで襲ってきたらしいな。ジャッポネーゼの十代目はいけ好かねぇとでも思ったのか……、短慮な野郎どもだぜ。同盟ファミリィの人間がドン・ボンゴレ十代目候補を暗殺しようとしただなんてな、ボンゴレ内部でも問題になるだろうしな。こりゃあ、幸先いいぞ」
「なんでですか!? 幸先なんて最悪じゃあないですか! リボーンさん」
「考えても見ろ。ツナは誰も彼もから祝福されてボスになる訳じゃねぇんだ。数ある候補者から選ばれた生え抜きとはいえ、異国の土地からくる若いドン・ボンゴレを嫌ったり憎んだりしてる奴らはくだらねぇほどいる。初めっから、周りが敵ばっかりだと思ってたほうが油断しねぇでいいだろ?」
「敵ばっかり、って……」
「だいたい、おまえは呑気だからな。気ィ抜いて暗殺なんてされてみろ。オレがもう一回殺してやるからな?」
「もう一回殺すって、どうやって?」
「地獄まで追いかけてって、頭蓋骨を打ち抜いてやるさ」
右手で作った指遊びの銃の――、人差し指を綱吉の眉間へ向け、リボーンが片目を細める。言葉を失っている綱吉を見た彼は、クスクスと一人で笑って、小さな肩を震わせている。
何がおかしいのかさっぱり分からない綱吉が困り果てていると、シャマルが何かを思いだしたように声を上げ、スーツの内ポケットから一枚の封筒を取り出した。どこにでもあるような白い封筒だ。彼は片手をソファについて、綱吉に向かって封筒を差し出した。
「これ、おまえに」
「なに?」
「ご確認をよろしく」
ソファから腰を浮かせて、綱吉はにやにやと笑うシャマルの手から封筒を受け取った。のり付けもされていない封筒をあけ、綱吉は中に入っていた折り畳まれた紙を取り出した。紙を広げてみるとなにやら細かい文字と数字が並んでいる。くせのあるシャマルの細い文字を読んでいくうちに、綱吉はそれが診察にともなった請求書だということが分かった。
「うん?」
だが、腑に落ちなかった。
綱吉はまだ、シャマルの手で診察や治療を受けた覚えはない。
だというのに、請求書とはどういうことはおかしいはずだ。
不可解なままに、シャマルを見つめ、綱吉は首を傾げた。
シャマルはにやついたまま、悪戯をしかける少年のような顔でさらりと言った。
「あん? 請求書に決まってんだろ」
「これ、治療の請求書でしょ? オレ、まだ何にも治療とか受けてないけど?」
「ばーか。おまえのじゃねぇよ。もう一人のおまえの分」
「え。あのっ、え?」
「未来のおまえが、おまえに払ってもらって言ってたんだ。払ってくれるよな?」
綱吉ははじかれるように、請求書の一番右下の合計という漢字の横に書かれている数字の羅列を見た。いち、じゅう、ひゃく、せん、まん、じゅうまん……、ぞわっとした悪寒に背中を震わせ、綱吉は目を見開いてシャマルを見た。
「うそぉ! オレ、こんな金額払えないよ!」
「そうだな。おまえの貯金なんかじゃ、とうてい補えきれないわな」
おかしそうに笑いをこらえながら、リボーンが言う。
リボーンは子供の成りをしていても、超一流の殺し屋だ。きっと綱吉よりも貯金はあるに違いないはずだ――などという思惑が一瞬で綱吉のなかに湧きあがる。
「り、リボーン」
「貸さねーぞ」
リボーンに笑顔のままで希望を断たれてしまう。顔を伏せて、思案してみても、現在の綱吉に支払えるだけの資金はない。むろん、母親である奈々には頼りたくはない。今回のことで心配をかけたうえ、多額の治療費まで奈々に負担をかけるわけにはいかない。
綱吉はおそるおそる顔をあげて、請求書を片手にシャマルを伺うように上目遣いで見る。
「シャマル、……出世払いじゃ、駄目?」
「世知辛い世の中、そんなにうまい話はねえよな?」
「えぇー。ちょっとー、どうしろっていうんだよ……」
「ボンゴレの小僧が身体で払ってくれるなら考えるけどなー」
意地悪く笑って、シャマルがふざけたように言う。金が払えないのならば、シャマルの言うとおり、彼の仕事を手伝ったほうがいいのかもしれない――と考えていた刹那、獄寺がびくりと身体を震わせたので、綱吉もつられてびくっと身を揺らしてしまった。
「ばっかやろう!! クソ医者! 十代目になんて破廉恥なことを!!!」
「へ?」
綱吉が間の抜けた声をあげた次の間、山本がこらえきれなくなった笑気を吐き出すように笑い出した。真っ赤な顔をしている獄寺を見て、シャマルが呆れたように首を振り、片手を身体の前で左右に振った。
「おいおい、ピンク色にすんのはおまえの頭のなかだけにしとけ。あのな、隼人。オレは、ボンゴレ小僧に助手として仕事を手伝ってもらおって思ってただけだぜ?」
「ああ?! なんだそりゃあ!」
「ナチュラルにいかがわしいのなー、獄寺は」
「いかが、わっ、しい……だとっ!?」
声を震わせた赤い顔の獄寺と綱吉の視線がからむ。彼は低い声で「うぐう」と呻いて、下を向いてしまった。綱吉は獄寺の腕を軽く叩いてなだめた。彼は半分困ったような、あと半分は照れたような顔で、わずかに頭を下げた。
綱吉はソファに背でもたれ、隣に座る山本、近くに立っている獄寺、正面に座っているリボーン、そしてリボーンの背後に立っているシャマルを見た。
「ああ……、なんか、帰って来たなあーって感じがするなあ」
「この騒がしさが、懐かしいってことかい?」
「うん。そう。……オレいますごく、幸せかもしれない」
「よかったな」
リボーンがそう言って、口角の片側を持ち上げる。
ふと、未来のリボーンがそうやって笑っていたことを綱吉は思いだした。瞬間、何故かどきりとした。目の前にいる五歳のリボーンが成長すると『ああなる』のだと今の綱吉にははっきりと分かる。顔立ちも表情も声も仕草も、まだ綱吉のすべての五感に残っている。
『ツナ』
今よりも少し低くなった彼の声が聞こえたような気がして、綱吉はぞくぞくとした悪寒とは違う、妙な気持ちに落ち着かなくなって、誰にも気が疲れないようにそうっと息を吐いた。
「ボンゴレ坊主が無事に帰ってきたってことは、イタリアへ渡る時期は予定通りなのか?」
リボーンの座っているソファの背もたれに両手をつくようにして身をかがめ、シャマルがリボーンに問いかける。彼はソファに座り、綱吉達の方を眺めたまま口を開く。
「ああ。少しごたついたが、無事にこいつが帰ってきたから、予定に変更はねぇよ。多少、イレギュラーな襲撃があったりしたが――その件は九代目が引き受けてくれた」
「あっちに行ったら、まっさきに今回の件のお礼を言わなくちゃね」
「おまえの無事な顔さえ見れば、九代目の苦労は報われるし、心労も軽くなるだろうよ」
「そうかな? そうならば、いいんだけどな……」
「あのう。十代目」
獄寺が綱吉のことを見つめながらあごをひいた。言葉の先を促すように綱吉がジッと獄寺の言葉を待つと、彼は遠慮がちな様子で、だがしかし、まっすぐに綱吉のことを見つめて言った。
「未来は、どうでしたか? 俺はあなたの右腕として、あなたのお側にいましたか?」
「まったくもう……、心配症だなあ、獄寺くんは。……獄寺くんはさ、オレと一緒にイタリアに渡ってくれるんでしょう?」
「そりゃあ、もちろんです!」
「なら、獄寺くんはオレの側にいると思うけど?」
綱吉の言葉に頷きながら、獄寺は小さな声で「はい」と言って、それ以上は何も言わなかった。泣きそうな彼の様子をリボーンがつつきたそうにしているのを綱吉は視線で制止しつつ、期待に満ちた山本の視線に答えるために彼の方へ顔を向けた。
「な、な! ツナァ、俺は? 俺はいた?」
「それがさ、山本とは会えなかったんだよ」
「あー、そっかー。そりゃあ、残念だったなあ。未来の俺ってどういう感じなのか、すっごい興味あったんだけどなー」
「オレも会ってみたかったなあ。未来の山本。きっと格好良くなってるだろうなあ」
「へへへ。ツナにそんなこと言われっと、照れるのなー」
はにかんだ山本に誘われるように綱吉もはにかんでいると、ふいに横顔に突き刺さるような視線を感じた。綱吉の正面に座っているのはリボーンだ。彼は足を組んだうえ、華奢な両腕を胸の前で組み、幼い顔立ちには不似合いであるのに、美しいがゆえに魅力が溢れる、艶笑をうかべている。
「オレはどうだったんだ?」
「え?」
嫌な予感がする。
超直感が綱吉の脳裏をかすめる。
「なにが?」
リボーンの黒い瞳が真っ直ぐに綱吉を見ている。
綱吉は視線を外すことが出来ない。
綺麗な、きれいな顔をした五歳の子供から、視線がはずせない。
「未来に、オレもいたんだろ?」
「あ、あー…………」
「なんだ、その反応は?」
「いた、いたよ。……いましたけど」
返事に窮する綱吉のことを不思議そうに山本と獄寺が見ているのが分かったが、綱吉にはどうすることもできなかった。
未来のリボーンとのキス、
『愛してるんだ』
デッセロが言っていた未来の綱吉とリボーンの関係。
『あなたが血迷って、あんなガキを愛人にしたことは、もはや裏社会でも有名なことじゃあありませんか!』
未来の綱吉と未来のリボーンの関係は、現在の綱吉と現在のリボーンには無関係だ。今までも、そういった『関係』を意識したことはない。綱吉はリボーンのことを家庭教師だと思っていたし、リボーンのほうも綱吉のことを生徒だと思っていた、はずだ。
だがしかし、綱吉は忘れられなかった。十四歳のリボーンの顔が、声が、触れてきた手が――記憶に残っている。目の前にいる五歳のリボーンには、十四歳のリボーンの面影がある。当たり前だ。本人なのだから。
綱吉とリボーンの視線がからむ。胸の奥がつーんと痛んで、綱吉は短く息を吐いて強ばりかけた身体から力を抜く。
『愛してるんだ』
もうすこしで変声を迎えそうな、きれいなアルトで紡がれる声がよみがえる。背中から首裏にかけて、妙な熱がかけのぼってくるような気がして、綱吉は片手で顔を覆った。やるせないような、情けないような感情に負け、綱吉は深く息を吐き出した。
「……何、赤くなってんの、ボンゴレ坊主。気持ち悪ィ」
「赤くなって、なんかないっ」
と、言ってみたものの、綱吉は熱をもった己の顔が赤くなっていると自覚していた。リボーンはずっと愉快そうに綱吉を見ている。その目が、綱吉の考えていることなど何もかも知っているのだというような光を宿しているような気がして、綱吉は逃げ出したいような気持ちになった。
「そうか。思いだして赤くなるほど、オレは男前だったか」
「ばかやろ! 心読むなッ」
「誰も心なんぞ読んじゃいねーぞ。おまえ、ちゃんと今は閉じてるからな。うかつに本音を口にするなよ。ドン・ボンゴレ」
「……え、なに? どうしたんだ? ツナも小僧も急に雰囲気変わったんじゃね?」
とぼけたような山本の声が綱吉の理性の限界を押し流した。
「オレは知らないッ。――か、帰る!」
衝動的にソファから立ち上がって、綱吉はリビングルームを横切って玄関への扉を目指す。
「え!? 十代目! お宅までお送りします!」
「あ。じゃあ、俺もつきあうわー」
獄寺と山本が綱吉の近くへすぐに駆け寄って来る。二人に顔を見られたくなくて、綱吉はうつむいたまま玄関へ続く廊下への扉を開けて、廊下へ出る。
「いったい、なんだっていうわけ? おまえ、何かしたのか?」
「さあな? オレには理由は分からねぇぞ」
シャマルの呆れた声に笑い混じりにリボーンが答える。
「まったく……、呆れた奴だな。あんなに考えてることが顔に出ちまうんなら、心を閉じてても意味ないだろ。バカツナめ」
リボーンが笑いながら何かを言っているのが聞こえたが、綱吉はすべてを振り切るように早足で玄関へ向かった。
|
|
××××× |
|
シャマルのマンションを飛び出したものの、徒歩で帰宅する訳にもいかず、綱吉達三名はタクシーで沢田家まで戻った。もちろん、タクシー代は奈々が支払ってくれた。
綱吉が自宅の玄関に立ったことを確認したことで満足したのか、獄寺と山本はそれぞれの自宅へ戻っていった。二人とも、何かあったらすぐに連絡をするようにと綱吉に念を押してから帰っていった。
帰宅した綱吉の顔を見た奈々は何にも言わずに、両腕で綱吉のことを抱きしめてくれた。何も聞かず、何も問わず、ただ温かく柔らかい腕で抱いてくれた。綱吉は奈々の身体に両腕を回して「ただいま」と言った。奈々は「おかえりなさい」と言って、潤んだ目で笑った。
抱擁をといた奈々は、まず綱吉の殴られた顔を見て心配そうにしていたが、次に綱吉が着ていたスーツや外套がとても上等なことに驚いて感心していた。自宅で洗えないと判断した奈々は、外套とスーツをクリーニング店に頼むことに決めた。綱吉は自室で普段着に着替えたあと、外套とスーツを抱えて一階のリビングルームに降りていった。
時刻はもうすぐ十一時になろうとしていた。子供達はまだみんな学校に行っている時間で、ビアンキは不在だった。奈々が丁寧にスーツをおりたたんでいるのをソファに座って眺めていた綱吉は、インターホンが鳴ったので玄関へ出ていった。
玄関のドアを開けると、シャマルが立っていた。思わずリボーンの姿を彼の背後に探したが、リボーンはいなかった。
シャマルは車を運転して、脳の検査と身体検査のために綱吉を自宅へ迎えに来たのだった。中学校の校医としての仕事はどうしたのかと聞けば、「俺ぁ、いま、風邪ひいてんだ」といってにやにやと笑う。今さらシャマルの所行を咎める気にもなれず、綱吉は大きなため息をひとつついて、彼への小言を諦めた。
奈々にシャマルと病院へ行くことを告げてから、綱吉はいったん自室へ戻って簡単な身支度をし、財布や携帯電話などをショルダーバックに入れて肩にかけた。
自宅を出てシャマルの車に乗って、彼の知り合いがいるという病院へ向かった。個人病院かと思っていた綱吉だったが、到着してみれば驚くことに大学の付属病院で、シャマルの知り合いだという医者は、シャマルよりも年が上で病院内でも役職があるような風体の壮年の男だった。医者の彼はシャマルに好きなように機械を使うように言って、自分は仕事があるからと言って出ていってしまった。綱吉がどんな関係なのか?と問うても、シャマルは微笑むばかりで答えてはくれなかった。
ときおり通りすがる女の看護士を見てはでれでれしつつ、シャマルは綱吉の怪我の手当をし、身体の検査をした。昼前から始まった治療と検査は夕方近くなってようやく終わった。綱吉が空腹を訴えると、シャマルは病院の近くにあったレストランへ綱吉のことを連れて行ってくれた。もちろん、彼が食事代もおごってくれた。感謝の気持ちをこめて礼を言う前に「イタリアで可愛い子みつけたら、俺に紹介しろよ」などとシャマルが言ったので、綱吉は最初の気持ちの半分くらいの気持ちで、お礼を言っておいた。
食事を終え、シャマルの送迎で綱吉が沢田家に帰ってきたのは夜の七時過ぎだった。すでに帰ってきていた子供達は、綱吉のことを発見すると、歓声を上げて飛びついてきた。その様子を見て、ビアンキと奈々が微笑ましげに視線を交わす。リボーンはダイニングテーブルの椅子に座り、少しだけ表情をゆるめて、新聞を読んでいた。
沢田家の夕食が終わり、風呂に入るまで、ランボもフゥ太もイーピンも綱吉から一度たりとも離れなかった。かけられる言葉のすべて、触れてくる彼らの手から、彼らが心から綱吉のことを慕ってくれていることが、綱吉にもありありと感じられた。綱吉が成長する間、沢田家には子供達の声が絶えなかった。一人っ子だった綱吉に突然出来た、兄妹のような彼らのことが、綱吉は大好きだった。
夜も更け、子供達と奈々が風呂に入り、ビアンキが入浴し、リボーンが入浴したあとで、綱吉は最後に風呂に入った。
子供のころから見慣れた脱衣所で服を脱ぎ、何度も何度も入浴した風呂場の戸を引いて中へ入る。湯気でけぶる湯船のなかへ、身体を沈めると、自然と間の抜けた声がもれた。
湯船のへりに後頭部をのせた綱吉は目を閉じて、
「……帰ってきたんだなあ……」
|
|
××××× |
|
濡れた髪をかわかしてから、リボーンはスーツのポケットへ入れて置いたステンレスケースを取り出して、綱吉の机に向かった。奈々から借りた工具が机のうえに乗っている。まずはマイナスドライバーをケースの隙間に差し込んで動かしてみるも、銃弾で歪んでしまっているせいか、あまり効果がない。ペンチで引き剥がそうとしても、なかなかうまくいかなかった。そもそも、工具が大人用のものなので、五歳のリボーンの手には大きすぎた。途中、苛立った気持ちに任せて意味もなく拳銃を撃ちたいような衝動にかられたが、深呼吸をして気分を落ち着かせた。
再度、気を取り直して、マイナスドライバーを隙間に差し込み、すこしだけドライバーの後ろを金槌で叩いた。少しの手応えがあり、ドライバーが隙間に入り込む。少しずつ身長にドライバーの先を隙間に差し入れ、だいぶ先が進入してから、リボーンはドライバーを握りしめ、てこの原理を利用して、ドライバーを動かした。初めは動きのなかったケースだったが、ほんの少しずつ、ドライバーが動くようになってくる。
「――なにしてるの?」
驚いて、リボーンは思わずドライバーを差し入れたケースを落としそうになってしまった。ケースを開けるのに必死になっていたせいで、綱吉が風呂から出て、部屋へ帰ってきたことにさえ気がつけなかった。集中するがあまり、周囲への警戒を怠ってしまっていた俺自身に呆れつつ、リボーンは作業を再開する。
「なにそれ? ケース? 壊れてんの?」
濡れ髪にタオルをのっけたまま、綱吉が椅子に座って机に向かっているリボーンの脇に立つ。ボディシャンプーの良い香りが綱吉の身体から香ってくる。
「銃弾が当たったせいで、歪んじまって開かねぇんだ」
「銃弾って! え、それ誰の――」
がちり、という音をたてて、ケースが開いた。
黒いベルベットにうずもれるように、二つの指輪が並んでいる。どちらも弾丸が当たり欠けているようなこともなく、無傷のままだ。
「指輪? おー、格好いいデザインじゃん」
綱吉が手を伸ばし、指輪の片方をはめ込みから取り外す。彼は親指と人差し指で指輪を持って眺め、指輪を顔に近づけた。
「あ。これ、内側に文字が掘ってある。しかも、日本語で。えーと、『永遠に影を愛する』? なんだこれ、そっちは――?」
言われて、リボーンは、ケースに残されていたもう一方の指輪を取り外し、銀色の指輪の内側を見た。文字は日本語でかかれている。しかし、指輪自体はイタリアの高級ブランド店のものだ。相当に良い顧客でなければ、わざわざ外国語、しかも日本語で文字を掘るような真似はしないだろう。だが考えても見れば、確かに、日本語ならば、不用意にイタリアで誰かに指輪の文字を見られたとしても、何と書いてあるか分からないはずだ。それほどに綱吉が工夫し、手の込んだプレゼントを用意する相手を、リボーンは思いつかなかった。それほどまでに綱吉に愛されている人間がいるということに、リボーンは静かに苛立っている自分を感じて、ひどく驚いた。卑屈に歪みかけていた唇を引き結び、リボーンはしっかりと指輪の内側の文字を視界にとらえ、声に出して読んだ。
「『生涯を大空に捧ぐ』」
「生涯を大空に捧ぐ? なにそれ、仰々しいなあ」
綱吉が笑いながら言うのを遠くからの声のように聞きながら、リボーンは指輪の文字を食い入るように見つめた。
永遠に、『影』を、愛する?
生涯を、『大空』に、捧ぐ?
リボーンの脳裏に、過去へ飛ばされてきた綱吉が言った言葉が思い出される。彼は、周囲の人間が、未来のリボーンのことを『影』や『烏』と呼んでいるのだと言っていた。
影イコールリボーンだとして、
『永遠に影を愛する』は
『永遠にリボーンを愛する』となるだろう。
そして、大空。
ボンゴレ関係で、
大空といえば、沢田綱吉のこと以外にない。
大空イコール綱吉だとしたら、
『生涯を大空に捧ぐ』は
『生涯を綱吉に捧ぐ』ということになる。
「『おまえが欲しいって言うなら、あげるよ』」
そう言って、微笑んだ二十七歳の綱吉の表情と声がリボーンの脳裏を過ぎていく。
『彼』と出会ってから、彼がときおり見せる表情や、リボーンに必死に隠そうとしていた思惑や事柄についての疑問点が、次々に解明されていく。
たったひとつの事柄で、『彼』の言動や行動の意味がとてもよく理解できた。
たったひとつの事柄。
未来の『彼』と、おそらくは未来のリボーンは、恋愛関係にあるということ。
気がついても、リボーンはおぞましいとも思わなかったし、特に嫌悪もしなかった。ただ単に、「ああ、そうか。そうならば納得できる」と思っただけだ。
指輪入りのケースを欲しいと言ったリボーンに、綱吉は言った。
おまえが欲しいって言うのなら、あげるよ。
彼の言葉には、きっとこう続いたはずだ。
(だって、それは、おまえにあげるために用意したものだったんだから)
「――くはっ、ははははははっ」
吸い込んだ息をそのまま吐き出すように笑って、リボーンは指輪を握りしめて額に寄せて笑気をこらえきれずに背中を震わせる。
「なに? どうしたの、突然」
「自信家すぎるだろう、ばか」
綱吉はリボーンに悪態をつかれても、綱吉はきょとんとした顔のまま、笑い続けているリボーンを眺めている。急に笑い出したリボーンのことが不思議でたまらないのだろう。
「なんでもねぇぞ。……く、あはは」
笑い続けるリボーンを怪訝そうに見つめた綱吉は、机のへりに腰を預けて、椅子に座っているリボーンの顔をのぞき込むように身を屈めた。
「なんだよ? なにがそんなにおかしい訳?」
「いや。……うん、もっと、未来のおまえと話がしたかったなと思ってな」
「ふぅん? 何を話したかった訳?」
「指輪をオレに渡さずに持ち帰ったとしたら『相手』にちゃんと渡したかどうか、とかな」
「渡さずに? ってことは、それ、未来のオレが持ってたやつってこと? へえ、ペアリングかぁー。いったい、誰にあげるつもりだったんだろ……。――ん? ……あれ?」
ふいに言葉を途切れさせた綱吉が、何かを思案するようにうっすらと唇をひらいたまま、視線を天井へ向ける。しばらく沈黙していた綱吉は、ハッとしたように息を吸い込んだかと思うと、リボーンの事を見た。そして短く呻くように声をもらしたきり、彼は片手で口元をおおい、うつむいてしまった。「まさかなあ、でもなあ」などというつぶやきを小さな声で言う綱吉の横顔の、頬から首筋にかけて、じょじょに赤みが増していくように見えた。
「なんだ、どうかしたか?」
「あっ、いやぁー……。なんでもない」
思い切り、誤魔化すために笑顔を浮かべ、綱吉は首を振った。本当はねっちょりと追求するつもりだったリボーンだったが、手の中にある指輪のことのほうがよほど興味があった。親指と人差し指で指輪をはさむように持ち、内側の文字を読む。
生涯を大空に捧ぐ。
いいだろう。捧げてやろうじゃあねぇか。
売られた喧嘩を買うような気持ちで文字を眺め、リボーンはほくそ笑む。
ふと、綱吉も自分が持っている指輪の文字をもう一度眺め直したのだろう。小さく「あっ」と声をあげ、またリボーンを見た。その顔が見る見るうちに照れたように赤くなっていくのをみて、綱吉が未来で何を見てきたのか、リボーンには分かってしまった。
綱吉は知ってしまったのだ。
未来の『彼』と『彼』の関係を。
だから、未来のリボーンのことを問われては答えに窮し、そしていま、指輪の文面の意味に思い当たり、顔を紅潮させて言葉を失っているのだろう。
綱吉の赤く上気した横顔を眺めつつ、リボーンは愉快さを隠しきれず、表情にのせながら口を開く。
「指輪は二つあるんだ。そっちはおまえがすればいい。オレはこっちをもらっておく」
「え? おまえの指じゃあ、サイズあわないだろ?」
ほんのりと赤い顔のまま、綱吉がぶっきらぼうに言う。照れ隠しにしか見えなかった。
「たぶん、そのうち合うようになるさ」
「うーん。……そりゃあ、成長すりゃあ、合うようにはなるんじゃないの?」
「それ、かしてみろ。はめてやる」
「は? いいよ。自分でやる」
「いいから、かしてみろ」
有無を言わせない響きを言葉に含ませると、綱吉は嘆息をひとつついて、片手で握り込んだ指輪を、渋々、仕方なさそうにリボーンの方へよこした。
「なんなんだよ、もう……」
綱吉のてのひらから指輪をつまんで受け取り、リボーンは綱吉の左手を手に取った。
「あ、おまえまさか――!」
彼が抵抗する間を与えず、リボーンは綱吉の左の薬指に指輪をはめた。「やっぱり、やりやがったな……」と恨めしそうに言って、綱吉が半眼でリボーンを睨んでくる。外そうとする綱吉の手に触れようとすると、彼は両手を身体の前へ引き寄せ、呆れたように息を吐いた。
薬指から指輪を抜くのを諦めたのか、綱吉は左手をつきだして、指にはめられた指輪を眺めた。
「ん。ちょっとゆるいなあ……。まあ、いいか。恰好良いし」
綱吉の薬指にはめられた指輪に刻まれた文字。
『永遠に影を愛する』
永遠など、リボーンは信じていない。
万物のすべては変わりゆくものだ。
だが、綱吉は信じているのだろう。
永遠なんてものを信じているのだ。
マフィアとして十年近く生きても、なお、彼は永遠を信じている。
リボーンがジィッと綱吉のことを眺めていることを気がついたのか、彼が指輪から視線を動かして、リボーンを見た。
「なんだよ……?」
永遠は信じられなくても、
綱吉のことを信じる価値はあるだろう。
リボーンが不敵に笑うと、綱吉は少しだけ戸惑ったようにわずかに目を細めた。
「だから、なに?」
「劇的な変化だなと思ってな」
「変化?」
「今日一日で、プロポーズして、指輪の交換までしたろ? オレ達、夫婦みてぇだな」
はじけるように動いてリボーンから距離をとり、綱吉は赤い顔で口を閉じたり開いたししていたが――、引きつったように笑ったかと思うと叩き付けるように叫んだ。
「ばっ、ばかなこと言うなよ! 気色悪い!」
「別に、オレは旦那でも妻でもいいぞ?」
「あほー! 誰もそんな細かい設定につっこみいれてないだろうが!」
「まあまぁ、仲良くしようじゃねぇか、ダーリン」
椅子から降りたリボーンは、部屋の壁際の本棚のほうへ後ずさっていく綱吉へ近づいていく。手にしていた指輪はすでに机のうえに置いてきた。リボーンの両手はいま、何も持ってはいない。
背中が本棚にぶつかった綱吉は驚いたように身体を跳ねさせる。逃げ道のないことを知った彼は両手をつきだしてリボーンの進行を止めようとしたようだったが、リボーンは彼の手へ両手を伸ばし、指を組み合わせるようにして拘束した。親指のはらで綱吉の親指の付け根を撫でると、彼の腕が動揺したように震えた。
「や、めっ、ろ! いったい、何の遊びだよ!? 人をからかうのもいい加減にしろよ!」
五歳のリボーンがいくら背伸びをしても綱吉の顔には届かない。少々の残念さを感じながら、リボーンは彼の身体にぴったりと密着するように身体をくっつけた。
「ひぃっ」
綱吉の腹部のあたりに顔をよせると、胸に顔をよせるまでもなく、彼の心臓がどきどきしているのが分かった。綱吉の身体に頬を寄せたまま、リボーンは笑った。年齢を重ねてもいっこうに変わることのない顔立ちが可愛らしいなどと思ったのは今が初めてだった。顔を真っ赤にして震えている綱吉の愛らしい態度が、リボーンの心をくすぐってやまない。
「ツナ」
「なんだよっ、手ェ離せよっ」
「仲良くしような、これから」
「はっ!? はあ……!?」
綱吉はあえぐように唇を震わせたかと思うと、膝から力が抜けたかすとんと座り込んでしまった。リボーンに掴まれている両手を持ち上げたまま、綱吉は顔を伏せている。ふわりとした柔らかそうな髪が揺れる。
リボーンのすぐ側にある綱吉の頭に唇を寄せる。綱吉のこめかみに頬をすり寄せると、わずかに彼の頬の熱が伝わってくるようだった。
「指輪に誓ってやる。オレは、ずっと、おまえの側にいてやる」
「なっ、なんだよ、誓うとかって」
「嬉しいだろ?」
綱吉が肩を揺らし、顔をあげた。思いのほか、リボーンの顔が近かったことに驚いたように綱吉は目を見開き、息を呑んだ。
「――ばっ……」
「嬉しいだろ?」
「――っ……、そんなの、わかんないっ」
「これからが楽しみだな」
「あーぁああぁー……、もう……」
綱吉はわめくことにも抵抗する事にも疲れたのか、盛大に息を吐き出して頭をもたげた。うろんそうな目でリボーンを見上げた彼は、唇をゆがめて疑わしそうな顔をした。
「いったい、何を楽しみにするつもりだ。せくらは教師め」
喉のあたりで笑い、リボーンは綱吉の左手を口元へ引き寄せ、薬指にはまっている指輪に唇を寄せた。
「愛してるぜ、ボス。適度に甘やかして、激烈にしごいてやるからな」
「なんじゃ、そりゃ」
「飴と鞭。好きだろ?」
リボーンが綱吉の頬へ唇で触れようとすると、彼は触れあっていた手を揺すって外し、リボーンの顔を手のひらで遮った。音をたてて手のひらにキスを落とせば、ますます呆れた顔をして、綱吉は吐息に疲れを混じらせて肩を落とす。
「やめてくれよ……。オレ、こういう遊び、嫌い」
「遊びじゃねーぞ?」
「顔が、遊んでます、って顔だ」
「へぇ? よく、オレのことが分かってるみてぇだな」
「おまえのそういう顔、オレ、すっごくよく知ってるもの。……あーあ、……もう、おまえってやつはほんとにさ……」
床のうえにぺたりと座り込んで、綱吉は立っているリボーンを見上げる。左手はまだ繋いだままだ。綱吉はリボーンの顔と、繋がれたままの左手、そして左手の薬指に光る指輪を眺め――、わずかに声をたてて笑った。それは自嘲ともとれたし、諦観した笑いのようにも見えた。
「……そうだよな、おまえって、そういう奴だもんな。分かってたけどさ、人間って、そうそう、変わるもんじゃないんだよな。『どっちもおまえ』なんだから、こうなるかもとは思ってたけど、でも、オレはオレだし、おまえはおまえだし……、だってさ……、未来は未来で、オレ達はオレ達なんだから……、まったく同じって、ことはないんじゃないのかなあ……」
「なに、一人でぶつぶつ言ってやがる」
「あ、え? んー、……なんでもない」
クスっと悪戯ぽく笑って、綱吉は手をのばしてリボーンの前髪をくしゃりと撫でた。大きな手のひらは髪を撫でたあと、たどるようにリボーンの頬に触れた。どきりと心臓が脈打つ。綱吉が触れている箇所が熱い。それは普段、リボーンが綱吉に迫るときに感じる高揚とは違う、もっと本能的な熱だった。
「オレだって、おまえのこと、好きだなって思うくらいは愛してるんだよ? リボーン」
はにかんだように笑って、綱吉は片腕でリボーンの身体を抱きしめてきた。先ほどまでリボーンが優勢だったはずの心理戦だが、いまやリボーンのほうが劣勢の状態だった。自分の心臓の音とは思えないほどに鼓動が体内で大きく響き出す。相手はあの沢田綱吉だと自覚しているというのに心音が高鳴りは強まるばかりだった。綱吉の髪からシャンプーのやわらかい匂いが香ってくる。眩暈のようなものを感じて、リボーンはそうっと息を吐き出しながら目を閉じた。
「ねぇ、リボーン」
リボーンの肩のあたりにあごを置いて、綱吉は囁くように言った。
「未来がどうなるかは分からないけど、オレ達はオレ達のやり方で生きていこうよ。これからはお互いになんでも話すようにしよう? オレ、おまえと腹のさぐり合いをしたりして、猜疑心にかられるのは嫌だよ。何も言わないで一人で抱えられたりしたら、オレ、本当に辛いからさ。いつだって全力でぶつかり合ってれば、すれ違うことだってないだろ? オレはもう、おまえだけを傷だらけにして生きていたくないんだ。オレはね、一緒に傷ついたり、泣いたり、怒ったりして、また――おまえと笑いたいんだよ。……リボーン、分かってくれる? オレの言いたいこと、伝わるかな……?」
ぽん、ぽん、と綱吉の手のひらが、あやすようにリボーンの背中を叩く。
傷だらけにして生きていたくない。
おそらく、綱吉が未来で見てきたリボーンは、大怪我といってもいいくらいの負傷をしたのだろう。その光景を目の当たりにしたことを綱吉は鮮やかな記憶として覚えているのだ。彼が未来で見てきたものがどんなものか、リボーンは分からない。きっと彼から聞いたとしても、リボーンが本当の意味で綱吉が経験したことを理解することは出来ない。
腕をゆるめた綱吉が抱擁をとき、リボーンの顔を間近に見つめてくる。ふざけた雰囲気も照れた様子もない、優しい微笑をうかべ、綱吉はリボーンの瞳をのぞきこんでくる。
綱吉はは未来で本来、経験しないはずの事柄を経験してきた。そのせいで、綱吉の内面が劇的に変化した。綱吉の瞳を見つめた瞬間、彼の変化がはっきりとリボーンに伝わってきた。
卒業式の日、彼が少しのためらいを抱えていることをリボーンは綱吉の表情から読みとって知っていた。しかし、いまリボーンと視線を交わらせている綱吉の瞳のなかには微塵の迷いもない。どんなに無様にあがこうとも、泥の中をはいずりまわってでも進んでいくしかないという、強い意志が綱吉の瞳の奥に宿っていた。
「オレの、言いたいこと、伝わった?」
「――ああ」
「ありがとう、リボーン」
リボーンが頷くと、彼は嬉しそうに双眸を細めて笑った。
「これからも、ずっと、よろしくね?」
胸が締め付けられるような思いにかられ、リボーンは腕を伸ばして綱吉の頭を片腕で抱きしめて、彼の頭に頭を寄せた。
「……リボーン?」
確かな熱が腕のなかで呼吸をしているのを感じながら、リボーンは抱え寄せた彼の髪に気がつかれないように静かにキスを落とした。
|
|
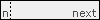 |