|
沢田家の玄関の前に立った綱吉は家屋を見上げていた。建物の中からは、テレビの音声と子供達のはしゃぎまわる声が聞こえてくる。リボーンは立ちつくしている綱吉の背中を少し離れた場所から見ていた。彼の態度は久しぶりに己の生家を見たかのように見えた。忙しい身の上なのかもしれない。当たり前だ。何千、何万という人間の上に立ち、その命を守るために日々を生きているのだ。組織のトップとして君臨し続けるためには己個人の感情など抑圧して生きていくしかない。
過ぎ去った過去を目の当たりにした綱吉の心には波紋が出来ているはずだ。しかし、リボーンには彼の心の波紋を感じる事は出来ない。ぴったりと閉じてしまった綱吉の心を読むことは、いくら読心術に長けているリボーンでも無理だった。
公園から出て、ケーキ屋に立ち寄って土産のケーキを買った。その箱はいま綱吉が片手にぶらさげている。商店街から沢田家へ辿り着くまで、二人が手を繋ぐことはなかった。他愛のない会話をして笑い合いながらリボーンと綱吉は肩を並べて歩いて帰路についた。
リボーンは公園を出て時からずっと緊張していた。緊張を悟られぬように幾重も幾重も頑丈な殻をかぶせ、リボーンは『いつも通り』を完璧に装い続けた。リボーンが作り上げた虚像に綱吉が気がついているかどうかは分からなかったが、彼はリボーンの態度については何も言わなかった。
数分間、黙り込んで家を見上げていた綱吉が、斜め後ろに立っていたリボーンを肩越しに振り返る。ふわりと長めの髪が動いて、すぐに彼の頬へ毛先がこぼれおちる。
「……入ろっか」
「オレの許可なんて必要ねーだろ。ここはおまえの家なんだから」
「うん。そだね」
そう言って笑い、綱吉は前を向いた。
肩を上下させるような深呼吸をしてから、彼は玄関へ向かっていった。リボーンも数歩遅れて歩き出し、玄関のドアを開けた彼の後に続いた。
ドアを開けた途端、夕食の良い香りが漂ってくる。奈々が何か言う声がしたかと思うと、ばたばたと元気な子犬のように子供達が三人、もつれるような勢いで玄関に走り寄ってきた。
「沢田さん。お帰りなさい!」
「ツナッ!」
「ツナ兄!」
三人の子供達が玄関で靴を脱いでいる綱吉の前に勢揃いして、にこにこと笑っている。フゥ太はどこかの上品な坊ちゃんのように、淡いピンク色のシャツに棒タイをして黒いスラックスをはいていた。フゥ太の左隣のランボがだぼっとしたフード付きのトレーナーとジーパン姿でいるので、余計にフゥ太の装いは彼を落ち着いた少年のように見せていた。ランボとはフゥ太をはさんだ反対側に立っているイーピンは、中華アレンジが施されたシャツに膝上丈のミニスカートを履いている。スカートの裾から健康的に伸びた素足がスリッパをつっかけていた。
綱吉は、沢田家の子供達と次々に視線をあわせると、にっこりと笑った。
「ただいま! いいにおいだね、今日の夕食はなに?」
「ママンがツナの好きなものたっくさん作って待ってたんだぞ!」
ランボが得意げに言うのを聞いて、イーピンがおかしそうに声をたてて笑い、首をかしげるようにして片目をつむる。ふたつのおさげの先が彼女の動きにあわせて揺れた。
「そうですよ。奈々さんのお手伝いをみんなでしてたんです」
「ビアンキさんは手伝ってないから、ポイズンクッキングにはなってないから安心してね」
「こら。フゥ太。聞こえてるわよ」
姿が見えずとも、奥のダイニングキッチンからビアンキの鋭い指摘の声が玄関にまで届く。フゥ太は顔をしかめて「聞こえちゃった」と言って苦笑いを浮かべて、短く舌を出した。
「楽しみだなあ」と言いながら、綱吉は用意されていた客用のスリッパに足を入れた。リボーンは自分用のスリッパをスリッパ立てから取り出してつま先を滑り込ませる。
玄関から廊下へ上がった綱吉の左腕にランボが甘えるように両手をからめる。リボーンの中で苛立ちがぶわりと浮上する。そのことに気がつきもしないで、ランボは綱吉の腕に寄り添ったまま喜色をうかべた顔で彼を見上げた。
「ツナァ」
「ん? なあに、ランボ」
「それ、なんだ?」
右手に並盛パティスリーのケーキが入っている手提げ箱を見てランボがにやにやと笑う。綱吉は腕にぶらさがっているようなランボのことを見下ろして優しく双眸を細めた。
「まったく。ランボはめざといなあ。――はい。イーピン。お土産だよ。選んだのはオレだけど、スポンサーはリボーンだよ」
イーピンに綱吉は箱を差し出した。彼女は両手で手提げの箱を受け取った。箱の横には店のロゴが印刷されている。イーピンの手元をのぞき込んだフゥ太も表情をゆるませてイーピンの頭を片手で撫でた。
「わああ! 沢田さん。これって!」
「並盛パティスリーのケーキだ! イーピンが大好きなのだね!」
「ありがとうございます、沢田さん! リボーンさん!」
イーピンが明るい笑顔を浮かべて綱吉とリボーンを交互に見た。
「夕飯が終わったあとで、みんなで食べような」
まるで十八歳の綱吉が言うように、優しい調子で『綱吉』が言うのをリボーンは聞いていた。
「はい」
「たのしみです!」
「やったあ!」
フゥ太、イーピン、ランボが口々に声をあげてキッチンへと駆け戻っていく。先を行った彼等が、台所に立っているであろう奈々に向かってケーキのことを話している会話が廊下にも漏れ聞こえてくる。
「子煩悩なパパだな」
歩き出そうとした綱吉の背中に向かって言うと、彼はわざとらしくもずっこけるような仕草をして、リボーンのほうへ振り返った。
「うっ。そうだよな、オレの年だと、ランボ達くらいの子供がいたっておかしくないっちゃーないか……、こども、子供ねえ……」
「おまえ、結婚はしてないのか?」
「……………………」
困っているような、それとも『おまえがそれを言うのか?』とでも言いたげな、微妙な顔をして綱吉は唇の片側を持ち上げる。彼が浮かべた表情の意味が分からなかった。
未来の綱吉の恋愛事情などリボーンにとっては知るよしもないことだ。
十八歳の綱吉は、笹川了平の妹である京子へ思いを馳せているようではあるが、彼は告白さえしないだろう。京子も少なからず、綱吉のことを好いていることはリボーンにも分かる。もしも、京子が告白をしてきても綱吉は断るのではないか――という考えがリボーンにはあった。
京子は四年制の大学へ進学することになっている。彼女には彼女の未来と夢があり、綱吉と共にイタリアへ来るということは、京子は文字通りすべて諦めて、あるいは捨ててこなくてはならない。彼女はそれを了承するかもしれない。だが、了承した彼女が得るものは綱吉の愛情だけではない。命を狙われる危機といつも同居し、己の周囲で数え切れないほどの人間が傷つき死んでいく――。一般的な家庭で教育された京子が耐えられるかどうかは分からない。
綱吉は京子を愛している。
だからこそ、京子とは仲の良い友達のままでいたいのだろう。
ドン・ボンゴレになる沢田綱吉の愛を受け取るには、彼女は脆く儚く優しすぎる。
ほんの数秒間、リボーンも綱吉も黙り込んだ。
綱吉は相変わらず、眉を寄せて、笑っているような困っているような顔をしている。その子供っぽい表情のせいか、リボーンは次第に己の中で彼に対する緊張感が和らいでくるような感覚がした。
「なんだ、その沈黙は? 結婚はしてねーのか? つきあってる愛人のひとりやふたりくらいいるんだろ? え? ドン・ボンゴレ?」
「いますよ。ひとりだけ」
「一人か。はあん。おまえ、日本人らしく恋人一筋ってやつなんだな」
「まあ、そうですけど」
子供のころ彼がよく見せた卑屈な感じで顔をしかめつつ、綱吉が唇をわずかに突き出す。思わずリボーンは吹き出してしまった。
「なに変な顔してんだ?」
「恋人一筋じゃあ、悪いのかよ」
「ああ、わりぃーと思うぞ。ドンともあろう男が、たった一人の女しか愛せねーようじゃあ、ふところが知れてるなってこった」
「あそう! じゃあリボーンなら同じ時期にどれだけ愛せるわけ?」
「両手の指だけじゃあ足りねーな」
「あー、そうですか。へぇえ、ふぅーん」
綱吉の頬がぴくりとひきつったように動いた。
リボーンは何故か「しまった」と思った。いったい何を失敗したのかは分からない。リボーンに愛人がいることはすでに周知の事実であったし、今でも十数人の魅力ある女性達とおつきあいをしている。どの女性とも関係は良好だ。
一度、床のあたりと見た綱吉の視線が、じろりと粘着質があるようにリボーンを見た。
「なんだよ、その目――」
「いいぇえ。なんでもありませんよー」
「なに、ガキくせー言い方してんだ。――で、子供はいんのか?」
面食らったように目を瞬かせた綱吉は、苦い顔をして肩をすくめた。
「あの、オレ、結婚してるなんて言ってないよな? なんで子供の有無なんて聞くの?」
「結婚してなくても子供はいるかもしれねーだろ? ――なんだ、おまえまだチェリーなのか?」
「ばっ、馬鹿っじゃないの!」
どもった彼は頬を朱に染めて引きつった声をあげる。
「いきなり何言うんだよっ」
「おまえもうすぐ三十路だってのに、なんなんだ、その青臭いガキみたいな反応は。気持ち悪ぃな」
「うるさいな! 残念ですけどチェリーじゃありませんから! っていうか、おまえにそんなこと言われると心外なんですけど! だいたいおまえがオレの――!」
ばちん!と音をたてるくらい勢いよく、綱吉は片手で自分の口を覆った。ぎゅっと両目をつむった彼は、一度だけ地団駄を踏むようにして片足をばたつかせたあと、口元を覆っていた手を外して、狼狽したようにリボーンを見た。明らかに激しく動揺している綱吉の様子が手に取るようにリボーンに伝わってくる。
「うぐぅ……、なんでもない! わっ、忘れて! 記憶から抹消して! 五分くらい前からの会話、全部消去! オールクリアして! オールクリア! デリートデリート!」
「は? なんで駄目ツナのチェリーにオレが関わってくるんだ?」
「ツナー、さくらんぼがどうかしたのか?」
リボーンの呟きと、リビングからひょっこりと顔を出したランボの声音が重なる。
「なんでもない、なんでもないから――」
玄関側とリビング側に右手と左手を付きだして、綱吉は赤い顔に引きつった笑顔を浮かべて言葉を繰り返した。
「ツナ、夕飯の用意出来たぞ!」
「うん、わかった。行くよ」
にっこり笑ったランボがリビングのなかへ顔をひっこめる。
重たく息をついた綱吉の側へリボーンは近づいていった。
彼は、近寄ってきたリボーンに気が付いて、おおげさなくらいに驚いて身体を揺らす。歩き出そうとする綱吉の右手をすくい上げるようにして掴む。急に思い立って、リボーンは綱吉の手の甲に触れた親指で、ゆっくりと、思わせぶりに彼の手の甲を撫でた。見る間に綱吉の大きな琥珀色の目が見開かれ、唇が何かを言おうとして震える。彼の狼狽が面白くて、リボーンはすくい上げた彼の手の甲に唇をおとす。「ひぃっ」と綱吉が短く息を呑んでびくりと手を震わせる。リボーンは愉快さに任せて声をたてて笑いながら、綱吉のことを上目遣いに見上げた。リボーンと目が合うと、綱吉はまるで羞恥心にまみれた少女ように今にも泣き出してしまいそうな顔で唇を引き結んでいた。
「夜の作法についても教育してやろうか。ドン・ボンゴレ」
綱吉は「うぐぅ」とも「くそぅ」とも取れるような低いうめき声を上げたかと思うと、リボーンの手から勢いよく片手を引き抜いて、びしりとリボーンの眼前へ人差し指を突きつけて言い放った。
「余計なお世話だ、このやろうっ。いかがわしいんだよっ、こんの五歳児!」
鼻息もあらく歩き出した彼は駆け込むようにリビングに消えていった。
廊下にひとり残されたリボーンは、ひとしきりくるくる変わっていった綱吉の表情のひとつひとつを思いだす。いくらとり澄ましていようとも綱吉は綱吉なのだ。彼がリボーンの顔の作りに惹かれていることをリボーンは知っている。リボーンは決してナルシストではないが、綱吉は綺麗な顔立ちの人間が好きだ――だから必然的にリボーンの顔も好みの部類にはいるだろう。というか、人間は誰しも、綺麗だったり可愛い顔立ちには無条件に惹かれるものだ。
リボーンは己の顔に手で触れる。
利用価値はいくらでもあると思っていたが、これほどに綱吉に有効的なものだとは思っていなかった。
大人の綱吉であれだけ狼狽するのだから。
十八の綱吉など、もっと簡単にねじ伏せることができるだろう。
今までは暴力で教育をしてきたが、これからはリボーンの顔と言葉だけで彼を調教することが出来そうだった。そろそろ殴るのも蹴るのも面倒になってきていたし、甘言と微笑で相手の感情を捕まえて良いようにあしらうことはリボーンにとっては拳銃の引き金を引くよりも簡単なことだった。
「……帰ってきたら、覚悟してろよ。ダメツナ」
ここにはいない『綱吉』にむかって呟いて忍び笑いをもらしたリボーンは、綱吉の手の甲へ触れた唇を舌で舐め上げながら、騒がしいリビングへと向かった。
|
|
××××× |
|
綱吉とリボーンがリビングへ行くと、沢田家の晩餐が始まった。テーブルのうえには窮屈なくらいに料理ののった皿が並べられ、椅子に座った面々は終始笑顔で料理を味わいながら会話をした。
子供達はことあるごとに綱吉が生きていた未来のことを聞いてきたが、そこは長年対人用に鍛えてきた話術を駆使して、子供達の注意を他へ他へとそらしていた。そもそも、子供達は自分たちのことを話したいものだ。綱吉の誘導どおり、子供達は自分たちが通う日本の学校についていろいろと話をしてくれた。
子供達は夕飯の片づけが終わり、場所をダイニングテーブルからリビングのソファセットに移っても綱吉から離れようとしなかった。テレビを見よう。ゲームをしよう。と、あれやこれやと綱吉の手をひいて遊びに誘う。子供達の相手をしながら、綱吉はふと、己が子供らしい子供達と触れあう機会などなかったのだなあと思いだした。
年齢が十代半ばの元・アルコバレーノ達は、見た目が子供であろうとも中身は綱吉よりも年齢が上かもしれない連中ばかりで子供らしい所など外見だけだ。無邪気に笑ったり、すねたりする沢田家の子供達のことを眺めていると、綱吉はあらためて、リボーン達は『子供』ではないのだろうな、と思った。
せっかくの機会だと考えて、綱吉は出来るだけ子供達の期待に応えて遊びに興じた。
綱吉の視力はある程度回復してきていて、普段通りに見えるようになってきていた。シャマルの説明どおり、衝撃による負傷というよりは、精神的な失明だったのかもしれない。
実は、シャマルのマンションを出るときも目は見えていた。だけどわざと見えにくいふりをして、リボーンがどうするかを試してみた。彼はおぼつかない綱吉の様子をみかねて手を貸してくれた。口や態度が荒いのは彼なりの装飾で、彼はほんとうは優しい。リボーンの小さな手を握りながら綱吉の内側は必死に泣くのを堪えていた。
子供達と遊びながらも、綱吉はずっと頭のすみで未来のことを考えていた。
逢いたいな。
逢いたいな。
――逢えるだろうか。
不安は音もなく雪のように降り積もる。
それでも綱吉の表層はずっと笑っていた。誰にも降り積もる不安を感じさせることなく、時間だけが流れていく。もちろん、五歳のリボーンにも気取られてはいないはずだ。うまく相手を騙す術は家庭教師からしっかりと教え込まれ、不本意ながらも環境が環境だったせいか、欺く術は上達するばかりだった。
子供達とゲーム興じて数時間後、奈々が「そろそろお風呂に入っておやすみしなきゃいけないわよ」と苦笑まじりに注意するまで、綱吉自身も夢中でゲームに興じていた。
まず、イーピンと奈々が入浴して、次にビアンキ、フゥ太、リボーンの順番で入浴した。ランボは最初から綱吉と入るのだといって駄々をこねていたので、最後に二人で入浴をした。
すでに夜の十一時を過ぎているというのに、ランボは眠そうな素振りすら見せずに、綱吉にべったりとくっついていた。
そのせいなのか、リボーンは綱吉から離れたソファに座って膝の上に雑誌を広げて静かにしていた。ビアンキが側に座ってやりとりをする場面もあったが、ほとんど彼は雑誌に視線を落としていた。彼が不機嫌になっているのかと様子をうかがってみても、そんな態度のかけらも見せない。――だが、きっと不機嫌なのだろうなと綱吉は察知していた。
リボーンとランボは何もかもが対局の位置にある、だけど本質はとても似ている。だからお互いが何をしていようとも気に入らないし、ちょっかいを出したがるのだ。これが長年、二人の関係性について綱吉が考え続けて出した答えだ。
子供のランボは五歳のころよりも甘え上手だ。自分の容姿が人よりも優れている自覚もあらわれているのか、上目遣いに見上げて甘えてくる。どうにも昔から綺麗だったり可愛い顔に弱い綱吉としては困った事態だった。
風呂場ではしゃぐランボをかるく叱りつつ、綱吉は入浴した。とはいえ、湯船に浸かることはできないので、熱いお湯でぬらしたタオルで全身を拭っただけだった。トランクスとパジャマの上着をはおった状態で、綱吉は風呂場のすみにあったプラスティック製の椅子に腰掛け、ランボの話し相手をした。
ランボに肩までお湯に浸かるように言い、一緒に百まで数を数えながら、綱吉は脳裏で「オレはいったい、いつから子持ちになったんだろうか」とぼんやりと考えていた。ふと、連鎖するように、玄関先でリボーンと綱吉との間で行われたやりとりを思いだし、綱吉の心臓はどきりとした。
たった五歳とは思えぬ色香と美しい顔立ち、情愛を思わせるような湿った仕草。
あれは反則だ。
内心でうめくように思ったが表情には出さなかった。
綱吉はランボと一緒に数を数えている。だがしかし、綱吉の一部はリボーンのことを考えていた。
ただでさえ、今の綱吉はリボーンに触れたくて触れたくて触れたくてたまらないのを我慢している状態だというのに、彼のほうから仕掛けてくるとは思っていなかった。だから心底驚いて、感情を誤魔化すことすら出来なかった。
赤面してあれだけ狼狽すれば、彼は何かに気が付いてしまうかもしれないことくらい、綱吉には分かっていたのに、おさえきれなかった。
夕飯のあとから今までで、綱吉はいつリボーンから「――おまえはオレのことが好きなのか?」などと問いかけられるのかと冷や冷やしていた。彼の読心術のことを考えて、綱吉はきっちりと己の心を密閉している。どこにも隙間など作っていないつもりだったが、夕刻の玄関でのやりとりは失敗すぎていて、隠していた全てが引きずり出される可能性があってもおかしくはなかった。
だが結局は、子供達に終始まとわりつかれていたおかげで、綱吉とリボーンは夕食中以外は会話していない。
まだ、していないだけだ。
これから綱吉は己の部屋に戻らなくてはならない。部屋にはリボーンがいるはずだった。
綱吉が高校に入学する辺りから、リボーンはハンモックで眠るのをやめた。身体の成長のこともあったし、ハンモックで眠るのにも限界があったためだ。彼は問答無用で綱吉のベッドを明け渡すように言ってきた。綱吉に拒否権はなかった。なので、綱吉の部屋にもとからあったベッドにはリボーンが寝るようになり、綱吉自身は絨毯のうえに布団をしいて眠るようになった。最初は違和感ばかりで眠れなかったが、結局は床で眠ることに順応してしまった。
風呂から出たランボがきちんとパジャマを着るのを待ってから、綱吉達はリビングに向かった。リビングにはフゥ太がテレビを見ながらソファに座っていた。彼にランボを預けて、綱吉は二人に「おやすみ」の挨拶をして二階にあがった。
ドアの前でかるく深呼吸をしてから、綱吉は己の部屋のドアを開けた。
紺色に白地の縁どりのあるパジャマに袖を通したリボーンは、ベッドの縁に腰掛けていた。小柄な彼の体躯では、ベッドの端に座ると足先が浮いてしまう。綱吉の手のひらに収まってしまいそうな小さな素足だ。
「よう。ご苦労さん。新米パパさん」
「パパじゃない……」
呻きながら綱吉はドアを閉める。
ベッドの近くの床には、奈々がしいてくれたのか――または低い確率でリボーンがしいたいのかもしれなかったが――、すでに綱吉用の敷き布団が敷かれていた。絨毯のうえに敷かれた布団のうえにあぐらをかいて座った。
「ランボって、あんなに落ち着きなかったっけ?」
「あいつはいつもうぜーぞ?」
「オレのなかでは、もう二十歳ちかい感じだからなあ。ギャップがものすごくって、不思議な感じが」
ばたばたという騒がしい足音がして扉がノックもなくばたんと開いた。リボーンは顔をしかめている間に、ランボは枕を抱えたまま綱吉の側まで近寄ってきてにっこりと笑った。
「ツナッ、一緒に寝よう!」
「……ランボ……」
「うぜーぞ。阿呆牛。てめーはフゥ太と一緒に寝ろ」
「やだっ、ランボさん、ツナと一緒がいい!」
「聞き分けねーと痛い目みるぞ」
「どうどう。二人とも落ち着いて」
綱吉が両手を持ち上げて上下させる。
開きっぱなしだったドアからうす水色のパジャマのフゥ太が顔を出した。綱吉の膝にもたれかかるようにしているランボを見たフゥ太は苦笑いをして、片手で額をおさえて片眉をはねさせた。
「こーら、ランボ! ツナ兄だっておまえにずっとくっつかれてたら疲れちゃうだろう? ほら、僕と一緒に寝よう?」
「えーぇ、ランボさん、ツナと――」
「明日、一緒に遊んでやるから。今日はフゥ太と一緒に寝なよ、ランボ」
綱吉はランボのやわからい髪を優しく撫でながら言った。彼は下唇を噛んでしばらく黙っていたが、フゥ太が手招いているのを見て、
「わかった」
と、小さな声で言った。
あぐらをかいて座っている綱吉の側に立ち、ランボは何気ない仕草で綱吉の頬へキスをした。十八歳のころの綱吉にとっては、頬へのキスなど子供相手でもどきどきとしていたものだったが、二十七歳の綱吉にとっては呼吸するのと同じだ。
「おやすみ。ツナ」
「おやすみ。ランボ」
自然な仕草でランボの頬へキスをおとす。ランボは砂糖菓子のように甘く微笑むと、ドア口にいたフゥ太に近づいていって身体をぶつけるようにした。フゥ太はランボの背中に手を回しながら「ツナ兄、おやすみ」と笑ってドアをしめた。二人分の足音はすぐに遠ざかって聞こえなくなった。
「ほんと。あいつはうぜぇな」
あまりにも低い声でリボーンが言うので、綱吉は反対に笑ってしまった。
「そんなにうざいかな? 可愛いじゃん。ランボ」
「おまえの目はおかしい」
リボーンは信じられないとでも言うように、片目を細める。
綱吉はおかしさをこらえきれずに笑って肩を揺らす。
「そうかもね。おまえも可愛いって思うしね。オレの目、おかしいのかもね。――もう寝ようよ。湯冷めしちゃう」
「そうだな」
素足を布団のなかへ入れて、布団の中にもぐりこみながら綱吉が言うと、リボーンもベッドの布団をめくりあげて、もぞりもぞりと布団にくるまった。
「おやすみ。リボーン」
枕に頭を乗せた綱吉は、ベッドの高さのせいで見えなくなったリボーンへ向かって声をかける。「おやすみ」という声が小さく聞こえたかと思うと、部屋の照明がふっと消える。おそらく、リボーンがベッドのうえにおいてあった照明のリモコンを操作したのだろう。
薄暗い闇の中で綱吉は目を閉じた。
眠りに落ちることなど出来ないことを知りながら――、目を閉じた。
|
|
××××× |
|
リボーンは音もなく暗闇の中で目を開いた。視界の先には見慣れた綱吉の私室が広がっている。薄暗い室内では時計の秒針の音だけがやけに大きく響くばかりだ。視線だけを動かしてリボーンはベッドの上から布団のふくらみを見た。ふくらみは規則正しく上下している。
気配をすべて消して、リボーンはベッドで身体を起こした。音を立てずに気配を消したまま動くことが出来なくては殺し屋などという稼業につくことはできない。ベッドから足を下ろして立ち上がり、布団で寝ている綱吉の傍らに立つ。彼は身動きひとつせずに寝息を立てている。
色素の薄いやわらかそうな髪の毛先が白い枕のうえに流れている。リボーンは綱吉の枕元に膝をついて座り込んだ。そしてゆっくりと息を吸い込んで、
「ツナ」
と、ほんの小さな声音で囁いた。寝ている人間が起きるには小さすぎる声だというのに、綱吉の肩がわずかに震えるように動いたのを、リボーンは見逃さなかった。
「……おまえ、まさか、ずっと眠ってないんじゃあないだろうな」
普通の声音で言いながら、リボーンは綱吉の肩を掴んだ。綱吉は細長く息を吐いて寝返りを打ち、戸惑ったままの瞳でリボーンのことを見上げた。
「リボーン」
枕のうえに頭をのせている綱吉のことをリボーンは無表情で見下ろす。眠たげな様子など微塵もない彼の瞳を見てリボーンは確信した。彼は寝ていない。おそらく、こちらへ来てから一度たりとも眠っていないのかもしれない。
綱吉は曖昧に笑って布団を腕ではらいながら起きあがった。何もかもを遮断するように微笑んで綱吉はリボーンを眺めている。微笑の裏に隠されている綱吉の本当の顔を探るようにリボーンはまっすぐに彼の瞳を射抜くように見た。
「こっちに来てから、おまえが寝ているところをオレは見ていないぞ」
「寝てるよ」
「嘘だな」
綱吉はぐるりと視線を回転させ、鼻から息をついて肩をすくめる。
「心でも読んだ?」
「オレがおまえのことで分からないことがあるとでも思うのか?」
「おまえがオレのことで分からないことは、あると思うけれど?」
真っ向から綱吉はリボーンの視線を受け止める。
どんなにリボーンが睨んでも物怖じすることなく、琥珀色の瞳は澄んだ色をたたえている。十八歳の綱吉ならば浮かべることなどできないような、そんな瞳だ。ふわりと十八歳の綱吉の姿が、目の前にいる綱吉に重なってすぐに消える。
「未来に、帰りたいか?」
「え」
急な問いかけに綱吉は面食らったように目を見開いた。
リボーンは無意識のままに片手で口元を覆って舌打ちをした。
未来に帰りたいか?
質問の裏を返せば、早く十八歳の綱吉に会いたいと言っているようなものだ。
眉間に深いシワを刻んで綱吉を見る。
彼は驚きを引きずった顔つきのまま、首を傾げるようにした。
「……わりぃな。いまの、忘れてくれ」
リボーンが片手を振ると、綱吉は短く呼吸してから頷いた。
「『ここ』は泣きたいくらい懐かしい場所だけど、オレの居場所じゃないからね。帰りたいよ、未来に」
「……そうか」
「リボーンは?」
「オレが、なんだ?」
「十八歳のオレに、帰ってきて欲しい?」
「こんな不自然な状態でいることは異常だ」
すでに予測済みだった綱吉の質問へ、リボーンは考えていたとおりの答えを返した。綱吉は片目を細めて、リボーンのことを睨み付けるようにしたが、すぐに破願してあごをひいた。
「ちえ。素直じゃないよな。まったくさ……」
小さな声でぶつぶつ言いながら、綱吉は肩を揺らして笑う。笑い声だけを聞いていれば、十八の綱吉と変わりはない。リボーンは惹かれるままに綱吉の髪に手を伸ばした。驚いたように身をすくませた綱吉の表情が、奇妙なこわばりを見せる。綱吉の前髪をくしゃりとかきあげると、彼は猫のように大人しくしていた。伏し目がちのせいか、頬に睫毛の影が落ちている。
リボーンは綱吉の髪から指先を離す。綱吉は瞬きが多く、緊張しているような空気がわずかに伝わってくる。一度伏せられた綱吉の目がリボーンを見た。
日本人らしからぬ琥珀色の瞳、年齢のわりに幼いままの顔立ち――、そこに浮かぶ微笑。
瞬間、リボーンのなかでピシリとなにかが砕けたような音がした。
砕けたものが何なのか。
リボーンは目を背けた。
見てはいけない。
知ってはだめだ。
心のあちこちから幾人もの自分自身が叫んでいる。
そんななかで、いちばん弱く、いちばん脆いリボーンが、『それ』に触れようと手を伸ばしている。
「リボーン?」
どきりと心音が肌をうち破って外側に漏れたような気がして、片手で胸元をおさえる。不思議そうな綱吉の視線ですぐに理性を取り戻したリボーンは、突然に思いついたことをあまり考えもせずに実行した。布団に両足をもぐりこませたままの綱吉の側に身体を寄せると、ぎょっとして彼は身を強ばらせた。
「え、なに?」
「ちょっと、おまえ端によれ」
「は?」
「一緒に寝てやる」
「は、はぁ!?」
大きく目を見開いた綱吉はのけぞるようにして息を呑んだ。その様子があまりにも滑稽だったので、リボーンは思わず笑ってしまった。
「なに、焦ってんだ?」
「ちょ、なにしてんのっ」
「添い寝してやろうかと思ってな。前も、おまえ、して欲しいって言ったじゃねーか」
「あれはっ、おまえが――」
「うるせーぞ。そっち、端によれ」
リボーンはやると言ったらやる。そのことをよく知っている綱吉は、リボーンが引き下がらないことを理解して、渋面を作って首を振ったあと、深い溜息をついて肩を落とした。
綱吉は左端へ寄り、できた右側のスペースへリボーンは身体を滑り込ませた。綱吉の体温のおかげで布団は温かい。だがしかし、そもそもシングルの布団なので少しでも寝返りをうてば布団がめくれてしまいそうな感じだった。
「枕よこせ」
「あー、はいはい」
リボーンに枕を差し出して、綱吉は折り曲げた己の腕に頭をのせた。手のひら一つ分ほどの距離に綱吉の顔がある。リボーンは綱吉からうばった枕を頭の下へいれて寝やすいように整えた。
綱吉はバツが悪いのか、どうしてなのか分からないが、必死に困った顔をして落ち着きなく視線を彷徨わせていた。リボーンは見た目は五歳の子供であったが、中身はそうではない。そういったことで困っているというよりは、もっと何か違ったことで戸惑っているようにも見えた。
ふと、彼がリボーンの顔立ちに魅力を感じていることを思い出す。晩餐前の彼の狼狽ぶりは実に愉快だった。思い出し笑いをして唇を歪めたリボーンを見て、綱吉はますます顔をしかめて朱に染まりつつある顔でわざとらしく息を吐いた。
「こんなんじゃ、寝れないんですけど?」
「子守歌でも歌ってやろーか?」
「寝るまで監視するつもりなわけ?」
「お望みとあらばな」
子供のように舌を出して鼻筋にしわを寄せた綱吉は、口のなかでぶつぶつと何かをつぶやく。
「……もう、人の気も知らないでさあ……」
「なんだ? 言いたいことがあるなら言っていいんだぞ?」
下唇を突き出すようにしていた綱吉はリボーンのことをしばらく睨み付けていたが、根負けしたように息を吐き出した。
「おやすみッ」
ぶっきらぼうに言い放ち、綱吉は目を閉じた。唇をへの字に曲げる彼の子供っぽさがおかしくてたまらなかった。マフィアとして生きるにはきっと彼は強くもないし、大人にもなりきれていないだろう。
眠れぬ夜もあったろうし。
ひとりで泣いた夜もあったはずだ。
「安心して、いいんだぞ」
閉じていた綱吉の目が開く。
「オレが側にいるんだ。何も恐れるもんはねーだろ? 安心して、眠れ」
綱吉は息を潜めるようにして、瞬きもせずにリボーンを見つめていた。
ふいに彼の瞳が潤む。
そのことをいち早く察知した彼は目を閉じた。
涙は流れなかった。
唇だけがわななくように震えただけだ。
布団のなかの綱吉の手がもがくように動いて、リボーンの手を探りあてると、遠慮がちに指先が指に絡んできた。
リボーンは何も言わず、綱吉の手を握った。
わずかに開いた彼の唇が音もなく「リボーン」と動く。
リボーンは頭の下にいれていた枕を取り払い、綱吉の側へもっと身を寄せた。もう少しで額が触れあうような距離まで近づく。びくりと綱吉は身構えたようだったが、目は開かなかった。
「おやすみ。……綱吉」
「うん」
子供のように素直に綱吉は目を閉じたままで頷いた。閉じていた左目の縁から透明な涙がもりあがり、一筋だけ肌のうえを伝い落ちていった。
「ありがとう。おやすみなさい。リボーン」
|
|
××××× |
|
考えることはたくさんあった。
自分のこと。過去のこと。未来のこと。友人達のこと。敵のこと。死者のこと。ファミリィのこと。――そして、彼のこと。
だから、眠ることが出来ないとしても、苦痛ではなかった。
今までで何度か不眠症になったことがあったし、今回は事件が事件なだけに、綱吉なりに「あ、これはヤバイな」と思っていた。案の定、身体は疲れているはずなのに眠ることが出来なかった。周囲の人間を心配させるわけにはいかないので、きちんと眠っているように装ってはみたが、やはり医者であるシャマルや観察眼が鋭いリボーンを騙しきることは出来ないようだった。
綱吉は目を開いた。
すぐ近くに目を閉じているリボーンの顔がある。
五歳のリボーンはまだ知らないのだろうが、リボーンは綱吉の側にいると本当に眠りこんでしまうのだ。このことが発覚したのは、綱吉とリボーンが一緒のベッドに眠るようになってからだった。
普段であれば、かすかな物音にすら反応してしまう浅い眠りしかしないリボーンたったが、綱吉が側にいるときに限り、彼は普通の人間のように無防備に眠り込んでしまうのだった。
綱吉の側だと気がゆるんでしまうから眠ってしまうのだとしたら、綱吉としてはなんだかくすぐったいような嬉しさがこみあげてくる。リボーンはそのことに気が付いてからは、綱吉が眠るまで寝ようとしないし、綱吉が起きる前に起きようとしているようだった。だがしかし、毎回それが実行されることは少なく、綱吉は何度も何度も、あどけない子供の顔をして眠るリボーンの寝顔を見る機会があった。
そのたびに「幸せだなあ」と綱吉は思わずにはいられなかった。
愛する人の寝顔を眺めることができる幸せ。
そんな幸せを噛みしめる日が来るなんて、きっと十八のころの綱吉はまだ知らなかったろう。
綱吉は頭の下へもぐらせていた腕を外し、リボーンの額にかかる前髪へと指先を伸ばす。すべらかな額の肌に触れ、ゆっくりと輪郭をなぞるようにあご元へ滑らせる。わずかに身じろぎをするものの、リボーンは目を開かなかった。
少しだけ身体を近づけ、綱吉はリボーンの額に唇をよせる。片手で横髪をすいて、目元にキスを落とす。そうしてから、綱吉は布団を少しだけめくりあげてゆっくりと布団から出た。リボーンの肩が出ないように布団をかけなおし、綱吉は立ち上がる。机の上にのっているデジタル時計で時間を確認する。
時刻は午前二時十八分。
記憶が間違いなければ、あと十二分しかない。
綱吉は気配を消して物音をたてずにクローゼットへ近づいた。綱吉が着ていたスーツは、奈々の手によってハンガーにかけられクローゼットのなかにある。シャツは、用意のいい奈々が二十七歳の綱吉のサイズに合わせて新しい白いワイシャツを購入していてくれていた。
新品のワイシャツに袖を通し、ブラックスーツに着替える。シャマルが用意してくれたネクタイではなく、クローゼットの扉にひっかかっていた安物だがデザインが気に入って買ったアクセサリ付きの棒タイをシャツの襟にそえて、結んだ。高級感のあるスーツには不似合いかもしれないとは思ったが、当時の綱吉はこの棒タイがわりとお気に入りだったのだ。
今は不在の、十八歳の沢田綱吉。
二十七歳の沢田綱吉としてではなく、十八歳の『彼』として『綱吉』はここにいなければいけない。
襟元、袖元、裾などをチェックして、クローゼットの扉の内側にある鏡を見つめる。
見慣れた自分の顔が鏡に映っている。
すこし、やつれたかな。
鏡のなかの己に微笑みかけ、綱吉はクローゼットの扉を音を立てずに閉めた。
布団にくるまってリボーンは眠っている。
目覚めるような気配はない。
「ごめんね」
音にせず、唇だけを動かす。
机の上のデジタル時計は、午前二時二十六分になっていた。
綱吉は自室を出て、階段を降りて玄関へ向かった。もちろん、足音は一切たてないままに行動している。ダイニングの方から、冷蔵庫の低いモーター音がかすかに聞こえてくる以外、家屋内はしんと静まりかえっている。
玄関に規則正しく並べられている大小様々な靴のなかから、己の革靴を選んで綱吉はつま先をいれる。腹部の前で両手を組んで深く息を吸い込む。ずっと眠っていなかったが、意識は妙にはっきりとしていた。
高校を卒業してすぐ、
三月九日、
午前二時半――。
忘れようとしても忘れられなかった、日付と時間。
未来から過去へ飛ばされたことにも驚いたが、卒業式の日に飛ばされたことに綱吉はもっと驚いた。
そして、感謝した。
なぜなら、『まだ、間に合う』のだと思ったからだ。
過去を変えることは本来ならばしてはいけないことだ。
過去を改変したことにより、未来すら変わってしまう可能性がある。
それでも、綱吉には――、どうしても『変えてしまいたい過去』があった。知らないふりをするには、その事実は綱吉にとっては耐え難いものだった。
伏せていた目を持ち上げ、綱吉は玄関の扉を開いて外へ出た。
人の気配を察知した玄関のライトが自動で点灯し、綱吉の姿を照らし出す。突然に開いたドアと点灯した照明に驚いた『複数の人影』が暗闇の中でびくりと身体を揺らして停止した。その隙をついて、綱吉は玄関から門を抜けて家の前の道路へと進み出る。頭の先から足の先まで黒ずくめで視界は暗視機能つきのバイザーをした男達が沢田家の玄関付近に数名、そして道路側にも同じような服装の男達が十名以上闇夜に紛れて存在していた。男達は誰も話をしない。まるで影のように沈黙したまま、綱吉のことを遠巻きにして取り囲む。
「静かに、してもらえない?」
ほんの小さな声で話しながら、綱吉は素早く視線を巡らせて男達の立ち位置を確認する。
「オレが沢田綱吉です」
ほんの一部の綱吉だけが喋り、その他の綱吉は全力で、どうやったら最小の動きと物音で相手を制することができるのかを必死に考えていた。表と裏とで考えを別離させるやり方は年々に上手くなっていくばかりだ。心のどこかで誰かが苦笑したような気がした。
「ここで騒いだら、あなた達も目立つでしょう? 場所を変えようじゃあないですか」
友人や知人達から、『ふぬけた顔』『頼りなさそうな笑顔』『偽善者面』『人を騙すのが上手い顔』などと酷評を受ける微笑を浮かべて、綱吉はわずかに首を右へ傾ける。途端、背後で何かが動く気配を感知して、綱吉は身をひねり、そのまま右足を軸に回転し、ナイフを突きだしていた男の腕を掴み、突進してきた男の勢いをそのままに腕をひねりあげて男の後方へ身体をすべりこませ、もう一方の手で男の後頭部を強かに殴りつけた。頭部に装着していた暗視用のバイザーが壊れて破片が地面に散乱し、隠されていた男の素顔があらわになる。綱吉の記憶には男の顔はない。『あのとき』は男達の顔など見ることはできなかった。リボーンの怒声で飛び起きて階下へ走ったとき、すでに奈々と子供達が玄関まで引きずられて連れて行かれそうになっているところだった。怒声。罵声。泣き声。叫び声。鼓膜の中で記憶が乱反射する。『あのとき』の怒りと哀しみを綱吉は忘れられなかった。
『あのとき』の後悔を握りつぶすには、今しかない。
ぐったりと力の抜けた男の身体を地面へ放り捨てる。
綱吉は姿勢良く立ち、、軽やかにターンをしながら周囲の男達を睨みつけた。
「静かに。と言っただろ」
ざわりと男達のまとっていた気配が怒気に満ち、周囲の空気の圧力が上がったような気配が綱吉の肌をなでる。
「大人しく、オレの言うことを聞いてくれよ。ここで面倒なこと起こしたくないんだ」
視線の先にいた男の、バイザーに隠されている目を綱吉は射抜くように睨み付けてた。
「こっちはね、一瞬で、おまえらを倒すことができるのを我慢してるんだ。――もう一度しか言わないぞ」
家庭教師である彼が、よく浮かべる挑戦的な微笑みを浮かべている自分を自覚した綱吉は、心の中で大笑いをしながらも、命じることに慣れた口調ではっきりと言い放った。
「場所を、変えよう」
|
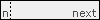 |
|