|
二十七歳の沢田綱吉の帰還により、危ういバランスを保っていたであろうボンゴレの指揮系統が一瞬にして通常通りの確固たるバランスを取り戻した。
綱吉は屋敷に戻るなり、骸、クローム、リボーンを強制的にシャマルの元へ預けると、己がいなかった間の状況報告を獄寺から聞いた。そして、骸を除いた他の守護者達からの報告を一度に聞き、それぞれへの対処の仕方などの指示をした。そのあとで、綱吉は私室へ一度戻って、火事場の焦げ臭い匂いのついた洋服をすべて脱ぎ捨てて、熱いシャワーを身体に浴びた。頭の傷は濡らさないように気をつけながら、綱吉は熱いお湯を肌にかけて、疲労感を忘れようとした。
シャワールームから出て、身体の滴をぬぐい取り、メイドが用意しておいてくれたクリーニング済みのスーツ一式に袖を通した。鏡のなかで一度だけ笑顔の表情を作り、それが不自然でないことを確認してから綱吉は脱衣所から出た。室内の壁にかけられている時計を見て時間を確認する。時刻は午後九時をすぎていた。守護者達は各々に割り振られた仕事をこなしているだろう。綱吉にもやるべきことが山のようにある。だがしかし、ボンゴレとしてやるべき仕事の前に、話をしておかねばならないことがあった。
リボーンから聞いたことを、彼女に確認しておかなければならなかった。これから綱吉は、今回のバズーカ事件の処理に長いこと時間をとられるに違いなかった。そのことが分かっているからこそ、綱吉は彼女と話をしなければならない。
緊張してこわばりそうな指先で私室のドアノブに触れてドアを開き、綱吉は医務棟へ向かった。
ボンゴレの主要メンバーのなかでは、笹川了平、獄寺隼人、六道骸、リボーン、クローム・髑髏が医務棟にそれぞれ部屋を設けられ、安静にしているようにとシャマルから命じられていた。ただし、六道骸だけはシャマルの言うことなどまるきり無視し――というか、彼は見た目でも検診でも身体に異常はなかった――、活動してた。改めて考えてみれば、骸は失われたクロームの臓器を幻覚で補うほどの能力を持っているのだ。己の身体の負傷を幻覚で補うことくらいはやってのけるのではないか――と、事件が解決してから綱吉は思いついた。
すでに、彼女の――クローム・髑髏の病室の位置はシャマルから聞いている。覚悟を決め、綱吉はなるべく颯爽と歩きつつ、彼女の病室へ向かった。
夜の医務棟は照明のトーンが抑えられているせいか、静まりかえりすぎていて、呼吸すら大きな音に聞こえそうなくらいだった。今回の内乱事件で、負傷し、死亡した構成員達が書類一枚では足りないくらいにいる。彼等や彼女達に顔向けできるよう、綱吉は己のみを削ってでも、事件を終息させなくてはならなかった。
入院している患者達の部屋の手前に、病院などで見かけるナースステーションよりも小規模な感じの場所があった。綱吉の姿を見て、若い男性の看護士一名と、三十代から四十代くらいの女性の看護士が頭を下げる。彼等に片手をあげて挨拶をして、綱吉は廊下を歩いていく。突き当たりの、左側の部屋のスライドドアまで近づいていき、綱吉はドアの前に立った。
目を閉じて。
深呼吸をして。
彼女に伝える言葉を頭のなかでもう一度考える。
どれだけの気持ちを込めたら、綱吉の思いがまっすぐに彼女に伝わるかは分からない。しかし、ありったけの気持ちを込めて、綱吉は伝えたかった。
目を開いた綱吉は、ドアをかるくノックした。
「――はい」
返事をしたのはクロームの声ではなく、男性の声だった。
綱吉はスライドドアの取っ手を握りしめて、ゆっくりと腕を引いた。
照明の明度を落としてあるのか、室内は淡い明かりに照らし出されていた。クロームが身体を横たえているベッドのすぐ脇に立っていた男性は、柿本千種だった。紺色のキャスケットに黒縁の眼鏡をかけた彼は、ちょうどベージュのトレンチコートの袖に腕を通しているところだった。
「あ。――ごめん。邪魔だった?」
「別に。もう、帰るとこだったから」
綱吉が入室するのを横目でみながら、千種がベッドに横になっているクロームほうへ顔を向ける。その横顔には表情はない。
「それじゃあ。帰るから。――お大事に」
「犬にお礼を言っておいて。――千種も、ありがとう」
「うん。また見舞いに来るよ、……めんどいけどね」
ほんの少しだけ、唇を微笑の形にして千種はベッドから離れた。入り口の近くに立っていた綱吉を見下ろして、千種は足を止める。
「ボンゴレ、あんまり無理はするな」
「うん。そうしたいところだけどね。千種達に無理させるから、オレも無理しとくよ」
息を吐いた千種は、片側の口角だけを持ち上げて目を細めた。
「ほどほどにしてくれ」
そう言うと、千種は病室を出ていった。
ドアの向こう側で足音が遠ざかっていく気配がするのを聞きながら、綱吉はさきほどまで千種が座っていたであろうスツールへ座った。視線の位置が変わり、すぐ側にクロームの顔が見えるようになる。白いやわらかそうな枕に包帯を巻いた頭を預けたクロームは、眼帯に隠されていない方の瞳を静かに瞬かせながら綱吉を見た。うっすらと上気した頬は薄紅にそまってはいたが、ほかにはこれといって具合の悪そうなところはパッと見ただけでは分からなかった。
「……苦しくない?」
「ええ。薬がよく効いているみたい」
微笑んだクロームが枕のうえでわずかに頭を動かす。ゆるくまとめられている彼女の長い髪が頬にかかるのを、綱吉は指先ではらった。
「ボス。手を握ってくれる?」
「うん。いいよ」
綱吉は望まれるまま、シーツのうえに置かれたクロームのてのひらにてのひらを重ねるようにした。やわらかくて細くて、小さな手のひらを握りしめる。
小さな声をたてて笑い、クロームは綱吉の手を握り返した。
「あの時も、ボスはわたしと手をつないでくれたわ」
「ああ、……リボーンとごたごたしてたとき? そうだったね。骸にオレが眠るのを見張ってろとか言われてクロームがあいつに呼び出されてさ、オレが眠るまで側にいてくれたんだよね?」
「ええ。ボスの寝顔は可愛かった」
「う。人に寝顔見られるのは恥ずかしいな……」
「リボーンは元気?」
「少し離れた病室のベッドで寝てると思うよ」
「……リボーンに会う前に、私に会いに来たの?」
うすく微笑んではいるものの、クロームがわずかに緊張したことが、触れあっている手のひらから感じられた。実際のところ、綱吉自身も緊張していた。相手に緊張をさとられないように落ち着いて呼吸をしつつ、綱吉は笑顔を保って頷いた。
「うん。――リボーンから、聞いたんだ。クロームとリボーンがしてた話のこと」
「そう。なら、話が早いわ。私、ボスのために――」
「だめ。ストップ」
綱吉に言葉を遮られたクロームは、ひらきかけた唇を震わせて、動きを止めた。
「オレは、おまえにそんなことを言って欲しくないんだ、クローム」
綱吉はなるべく優しく言ったつもりだった。
しかし、見る間にクロームが泣きそうな顔になってゆくのを見て、慌ててクロームの手を両手で握りしめる。
「クローム。お願いだ、泣かないで。だって、そういうことは、男のオレから言うものでしょう?」
クロームのまつげが震え、驚いたように綱吉を見た。
綱吉はクロームの片手を両手で包むように握りしめ、身体をベッドのほうへ傾け、クロームの顔に顔を寄せ、微笑みながら囁いた。
「クローム・髑髏さん。オレと結婚してもらえませんか?」
クロームは一瞬、呼吸を止めて綱吉を凝視した。
そして、すぐに息を吐き出して、震える指先で綱吉の手を握った。
「……私、ボスと結婚しなくても、子供は産むつもりよ? なのに、わざわざ、私なんかと籍をいれなくても――」
「私なんか、なんて言うなよ。それに、オレのほうが――最悪なんだから。『オレ達』はおまえに非道いことをさせようとしてるんだ……、知らないで強要するんじゃなくて、分かっていて、おまえに強要させるんだ……、もしかしたら、オレが、結婚してくれって言うのも偽善的で、おまえの人格を否定してるようなものかもしれない……」
「ボス……」
クロームは首を振って、自由だったもう一方の手を綱吉の手の甲に重ねる。華奢で、温かくて、優しい手のひらが、綱吉の手を包むかのように触れる。
「私は非道いなんて思ってない。強要もされてない。私は私の意志で、大好きなあなたの赤ちゃんを産みたいって、そう思ったの。ねえ、ボス。ボスは私のことが好き?」
「好きだよ。とっても大切で、幸せになって欲しいって、ずっとずっと思ってた。――なのに、オレは、自分勝手な理由で、クロームの」
「ボス……。お願い、ボス。聞いて。自分を責めないで。私もボスのことが、あなたのことが好きよ。大好き。幸せになってもらいたい。私はボスからいろいろなものをもらってばかりだった。だから、私がボスに出来ることがあるのなら、私はボスにしてあげたい」
「でも、クローム、オレは――」
「私のことを愛してくれるというのなら、私はそれ以上のことは望まない。きっとボスは全力で私のことを愛して、大事にしてくれるって、そう思うから、私はすべてをかけてあなたに尽くしてもいいと、そう思ってるの……」
「卑怯者で、ごめん」
「そんなことない。本当に卑怯なのは、私」
妙に力のこもった様子でクロームが言う。
綱吉はクロームの言葉の意味がくみとれず、思わずぽかんとしてしまった。
「……どうして? クロームが卑怯だなんて、そんなことないだろ」
「卑怯よ。子供が欲しいっていうボスの望みを建前に、私はあなたと決して途切れない絆を結びたがってるんだもの。ボスの前にある選択肢は少ないことを、私はよく知っていて、そして利用してるの。……ね? 私もなかなか卑怯だと思わないかしら?」
おどけるように、クロームが口元に笑みを浮かべる。彼女がそんな表情を浮かべることはまれだ。綱吉も誘われるように微笑んでしまった。そのことを意識する間もなく、クロームは言葉の続きを口にし始めた。
「それにね、ボス。私はボスの赤ちゃんを産むのが、知らない女の人だったりするほうが、私にっとっては大問題だもの。……ボスはいいの? 赤ちゃん、半分は私の血が混じってしまうけれど」
「オレとクロームの子供でしょう? 可愛いに決まってる」
「そうかしら?」
「たっくさん、愛してあげようね。ぎゅーってしてあげよう」
「ええ。たくさん、大好きだって言って、抱きしめましょう。きっと、みんなが、あったかく愛してくれるわ。だって、その子は、みんなに望まれて、愛されるために産まれてくるんだから」
クロームが微笑む。
綱吉のなかで、クロームの過去がよみがえり、そしてはじけた。
座っていたスツールから腰を浮かし、綱吉はクロームの顔へ顔を近づけた。クロームは何も言わずに静かに目を閉じる。彼女のやわらかい唇に唇を押し当て目を閉じる。ほんの少しだけ離れてから、もう一度、ちゃんとキスをして、綱吉はクロームの顔から顔を離した。しかし、身体を引くことはせず、わずかな距離で綱吉は彼女の顔を見つめた。
伏せられていたクロームの瞼が持ち上がる。
綺麗な、どこまでも純粋さを秘めた綺麗な瞳が綱吉を見て、幸せそうに潤んだ。
綱吉は布団のうえからそっとクロームの身体を両腕で抱きしめた。横になっている彼女の耳元あたりに頭をよせて目を閉じる。
「もう少し、身辺が落ち着いてから、正式に発表するね。――すこし、傘下のファミリィの古株な人達が、身分とかなんとかグダグダ言うかも知れないけど、気にしないで」
「知らない人に何を言われても、私は気にしないから。だいじょうぶ」
「うーん。強いな、クロームは」
布団のうえからの抱擁をといて、綱吉はベッドに両手をついてクロームを見下ろした。シーツのうえの綱吉の手に、クロームの手が重ねられる。白くて小さな手。綱吉が一生をかけて愛し、守り、慈しまなければならない温もりが、綱吉に触れている。
「ボスが側にいてくれるのなら、私は無敵だわ」
「オレも。クロームみたいに強くならなきゃな」
「ねえ、ボス。ひとつだけ、約束して欲しいことがあるの」
「うん。なんでも言って。おまえには言う権利があるから」
「私と結婚してくれると言うのならば、これから先、絶対に私に負い目は感じないで欲しい。私に悪かったなんて思ったりしないで欲しい。その分、私のことを、生まれてくる赤ちゃんを愛して欲しいの」
「うん。分かったよ。約束する。おまえと、おまえが生んでくれるオレの子供をオレは精一杯に愛するよ。約束する。クローム――」
クロームの額へ額を近づけるように身を伏せて、綱吉は精一杯の愛情と想いを込めて彼女に囁いた。
「オレと家族になってくれて、ありがとう」
綱吉の鼻先で、クロームは花がほころぶように笑顔を浮かべ、うっすらと双眸に涙をにじませた。
「私のほうこそ……。私と家族なってくれて、ありがとう。ボス」
二人で、どちらともなく身を寄せ合って、キスをした。
両腕を伸ばしあって、互いの身体に身を寄せ合った。
腕の中にある温もりを生涯守ることを誓いながら、綱吉はクロームの黒髪にキスを落とす。そしうしてから綱吉は、そうっとベッドのうえへクロームの身体を横たえ、乱れたかけ布団をかけなおした。かるく布団を叩きながら、綱吉は姿勢よくベッドの脇に立った。
「また、時間を作って会いに来るね」
困ったように眉を寄せ、クロームが首を振る。
「私に会いに来るくらいなら、身体を休ませた方がいいわ」
「やだよ。オレはクロームに会いたいから、きっと会いに来るよ」
綱吉が片目を閉じておどけると、クロームはクスクスと笑いながら首をすくめた。
「――それじゃあ、待ってる」
ベッドから離れ、綱吉は病室のスライドドアの取っ手を握りしめてドアを開いた。そして室内へ振り返り、クロームと目を合わせ、彼女に笑いかけた。
「怖い夢を見たら、かならずオレのことを呼んでね」
「おやすみなさい。ボス。怖い夢をみたら、きっとあなたのことを呼ぶわ」
「おやすみ。クローム」
白い布団にくるまれたクロームに手を振ってから、綱吉はスライドドアから手を離し、閉まりゆくドアを背にして薄暗い廊下を歩きだした。
|
|
××××× |
|
ほの温かく心地の良い暗闇から突然にリボーンは吊し上げられた。意識が自覚を始める前に、激しい頭痛と嘔吐感にみまわれ、リボーンは立っていられなくて両手をついて地面にへたりこんだ。
手をついた先に視線を落としてみれば、そこは黒かった。涙が滲みそうになる視線を必死に持ち上げ、辺りを確認する。リボーンは、ボンゴレの本邸の敷地内に建っている医療棟の病室のベッドで眠っていたはずだ。だというのに、いま、リボーンがいるのは、暗い、どこまでも暗く黒く、そして空間がどこまで広がっているかすら把握できないほどの闇の中だった。
「――こんばんは」
天から雨粒がひとしずく落ちてきたかのように、リボーンの背後に突如として気配が現れる。
「無理矢理、僕とあなたの精神を繋いでいますから苦痛でしょうけれど、いいですよね?」
地面に膝をついたまま、リボーンは身体の向きを変え、忌々しい男を睨み付けた。
「なにしにきやがった」
一言を口にするだけでも、吐き気がこみ上げてくる。
意識していないと目を閉じてしまいそうなくらい、ひどい頭痛がする。
それでもリボーンは、目の前に立っている、六道骸から視線を外さずにいた。
彼は苦痛そうに顔を歪めているリボーンを薄笑いを浮かべて眺めながら、左右で色の違う目を細めた。
「確認をしに」
「何の?」
「あなたは、クロームと『彼』を共有することを望んでいるんですね?」
短く息を吐いて、リボーンは膝に力を入れて立ち上がった。ぐらりと傾きそうになる身体を気力と意志だけで奮い立たせ、リボーンは直立する。そして、優雅に胸の前で両腕を組んでいる骸を睨んだ。
「共有なんて言葉で、オレ達の関係性を表すんじゃねえ。オレとクロームは、それぞれに全力でツナを愛して、ツナを守るだけだ。あいつが抱えているものは多すぎる。支える奴が増えた方がいいに決まってる」
「綱吉くんだけでなく、クロームのことも泣かせませんか?」
「あいつを? オレがか? ツナを盗られちまうかもしれねぇからクロームに酷いことでもすると思ってんのか? 馬鹿言うな。そんな無様な真似するか。――オレはあいつの愛人なんだ、クロームはあいつの伴侶になる。どちらかと言えば、クロームがオレのことを邪魔に思うんじゃねぇのか?」
「それこそ、馬鹿なことです。綱吉くんの幸せは、あなたの存在なしでは決して得ることは出来ない。そのことをクロームはよく分かっているはずです」
「ツナは、オレのことも、クロームのことも愛するだろうよ。あいつの愛は深く、そして決して枯れることはない。……それはおまえがよく知ってるだろう、六道骸」
それまで愉悦にみちた微笑を浮かべていた骸の顔が引きつったかと思うと、彼は不機嫌そうに組んでいた腕をほどき、舌打ちした。
「ずいぶんと僕のことがおわかりになるようで。ですが、軽々しく分かったような口をきかないでいただけますか? 反吐が出ます。――と、すいません。ついつい、本音が」
とっさに本性を現してしまったことを誤魔化すように、骸はわざとらしく微笑んで、リボーンの双眸をのぞきこむように、じぃっと見つめてきた。硝子玉のように美しいが、それゆえに人間的でない瞳に浮かんでいる感情を、リボーンは読みとれなかった。彼の深淵は、様々な人間を見てきたリボーンですら、のぞき込んでも何も見えないような、暗く深く、そして底の見えないものだった。
「あなたのせいで、二人のうちどちらかが己のことを不幸だと少しでも嘆いた時点で、僕は二人と……、彼の子供を連れてボンゴレから出ていきますからね」
「それをオレが許すとでも?」
「あなたの許しなど、最初から得ようとは思ってません」
せせら笑うように喉をならし、骸が右手を持ち上げ、人差し指でリボーンの額を指さした。
「忘れずに覚えておけ。僕は決しておまえの味方ではないということを」
骸は背徳的なほどにアルカイックに微笑んで、持ち上げていた手を自らの胸元へ引き寄せた。
「おまえが死んだら、僕は喜んでおまえの空席に座る。せいぜい、死なないように努力するがいい」
「黙れ。おまえの言葉はすべて不快だ」
リボーンのうなり声のような声に骸は片側の唇をつりあげ、冷酷な光を宿した紅と蒼の瞳を、獲物を見定める獣のようにゆっくりと細めた。
「お大事に。――そのうち、お見舞いに行きますよ。真っ赤な薔薇の花束を持ってね」
「消えろ!!」
叩き付けるようにリボーンが叫んだ瞬間、世界が激しく揺らいだ。立っていられなくなり、リボーンは地面に膝と両手をついて、どうにか倒れ込むことだけは避けた。頭痛と吐き気が強まり、身体が内側から蝕まれていくようだった。
それもこれも、六道骸がリボーンの精神世界に過干渉してきたせいかと思うと、苛立ちのゲージはまたたくまに限界値を超していった。
ほんとうに。
死んでくれたらいいのに。
怒りのせいでこめかみの辺りが痛むのを感じながら、リボーンは暗闇の中で目を閉じた。
|
|
××××× |
|
クロームの病室を出て、少し歩いた先にあったリボーンの病室のドアの前に綱吉は立った。
先ほど、ほんの少し前に、クロームとキスをした身体で、今度はリボーンの病室の前に立っている己自身を、綱吉は俯瞰していた。身勝手で自己愛に満ちた行動を眺めているもう一人の綱吉は、反対側に立っている綱吉を軽蔑の眼差しを浮かべている。そんな幻が閉じた瞼の裏に浮かぶ。
二人の人間を同時にどちらも愛するということを綱吉はしたことがない。
でも、もう後には引けない。
どちらも捨てる事が出来ないのなら、傷ついても血を流しても、あがいて、腕を伸ばして、生きていくしかない。
深呼吸をしてから、綱吉はリボーンの病室のスライドドアの取っ手を掴んで引いた。どうせ、ドアの前に立ったときから、リボーンは綱吉に存在に気がついているだろうと思ってノックをしなかったのだが――、驚いたことにリボーンは枕に頭をのせて眠っていた。
そうっと扉を閉めた綱吉は、足音をたてないようにしてベッドに近づいていった。リボーンは眉間に深いシワを刻んでいて、夢見が悪そうだ。ぴくっと口元あたりが引きつるように動いて、うわごとのように何かを言ったかのように見えた。
「リボーン?」
ほんの小さな声で綱吉が名を呼ぶと、眼帯に隠されていない右目の瞼がぴくりと震えた。
しばらくすると、長いまつげがふわりと動いて、リボーンの右目が開いた。綱吉は枕のうえに乗っている彼の顔へ顔を近づける。
「――起きたの?」
「……どうした?」
かすれた声でリボーンが言う。
「え?」
「こんな時間に、どうした?」
「ああ、そういう意味か。さっきね、クロームと話をしてきてところなんだ。それで、どうせならおまえの寝顔を見てから執務室に戻ろうと思ってたとこ」
「状況は?」
「こら。そんな身体で何するつもりだよ。オレに任せときなさい」
不服そうに鼻から息をついて、リボーンが目を伏せる。その表情がわずかに曇っているような気がして、綱吉は包帯が巻かれているリボーンの髪に優しく触れながら問いかけた。
「具合が悪いの?」
「悪い」
子供のように素直に言った彼の顔が、ますます不機嫌そうに曇っていくのを見て、なんだか綱吉はリボーンのことが可愛くて仕方が無くなった。指先でリボーンの髪に触れながら、顔を寄せて、彼の目元にキスを落とす。身体の力をぬくように息を吐いたリボーンは、自由に動く左腕を動かして、髪に触れていた綱吉の手に触れた。自然と互いに手を握り合う。リボーンの手はクロームよりも大きくて、すこし冷えていてつめたかった。
ベッドに片手をついて、身体を屈めたまま、綱吉は囁くように言った。
「クロームとね。さっき、話してきたよ」
「そうか」
「プロポーズ、受け入れてくれたよ」
「そうか」と、リボーンは繰り返すように言って、わずかに微笑んだ。おそらくは、綱吉も同じような顔をしているという自覚があった。
何かを叫び出したいような気もしたし、逆に静かに何もかもを受け入れられそうな気もした。いくつもの選択肢があるなかで、綱吉が選び取った選択肢の正しさはすぐには分からない。これから先、長い人生のなかで、正しさがいつかひるがえる日がくるかもしれない。
けれど、今の綱吉にとっては――、綱吉『達』にとっては、デメリットが最も少ない選択肢であることは確かだった。
「結婚式の前に婚約式だよね? いつにしようかな……」
綱吉の言葉に、リボーンは「そうだな」と言ってから答えた。
「暖かくなってからのがいいんじゃねえのか? やっぱり、新しい門出と言えば春だろ?」
「そうだね。そのころには、少しくらいはオレの周りも落ち着いてくるだろうし――。なにより、これから同盟のボス達にクロームと結婚することを納得してもらわなくちゃいけないんだもんな……正直、面倒くさいんだけど、ないがしろには出来ないからなあ」
「反対されたって、やめるつもりねぇくせに」
「――そりゃあ、そうだけどね。反対する人がいたって、全力で説き伏せて了承させるけどね」
「頑固だものな、おまえは」
そう言って、リボーンが意地悪そうに笑う。
綱吉はとぼけるように首をかしげてから、くすんと吹き出した。
「昔はそんなに頑固なつもりなかったけど、最近は、ああ、なんかオレ、頑固かもなーって思うこと多くなったかも」
「それは、おまえが何にも染まらないせいだろ」
「染まらない?」
「長いことこんな世界で生きてるってのに、おまえは闇に染まらずにいるじゃねぇか。だから、次第に世界が見えてきて、自分に出来ることも分かってきたから――、我を貫き通すようになっただけだろ」
「おお。まるで自分のことみたいに、オレのことを言うねえ。リボーン」
「だてに、長い間おつきあいしてる訳じゃねぇからな」
口角を持ち上げて微笑んだリボーンの表情に導かれるように、綱吉は彼の唇に唇を寄せた。性的な意味合いよりも、愛を交わしあうだけのかるいキスを数回繰り返し、綱吉はリボーンの顔から顔を離した。間近にある、リボーンの黒い大きな瞳を見つめているうちに、綱吉は泣きたいような気分になって、唇を噛みしめてこらえた。
そんな綱吉の表情に気がついたのか、握り合っていた手を解いたリボーンの手の指先が、綱吉の頬に触れる。まだ成長途中の、少年の手のひらが綱吉の頬を包んだ。リボーンの手のひらに顔を寄せながら、綱吉は目を閉じる。
「……なんか、裏切ってるような気分になるなあ」
「馬鹿。ずっと話し合ってきたことだろ?」
呆れたようにリボーンが言う。
綱吉は伏せていた目を開いて、ほんの数センチ先にあるリボーンと視線を交わらせた。
「おまえには子孫が必要だ。せっかく秩序を取り戻したボンゴレで、今回以上の内乱が勃発したら、どれだけの血が流れると思う?」
「おまえが、気にしてないのなら、いいんだけれど……」
「だいたい、おまえが気にしすぎなんだ。おまえ、オレ達のことをどれだけ好きかなんて比べようと思ってねぇだろ?」
「そりゃあ! リボーンのことを好きな気持ちとクロームのことを好きな気持ちは比べるようなもんじゃないって、そう思ってるけど……!」
「おまえは精一杯、オレ達のこと愛してくれんだろ? 幸せにしてくれんだろ? なら、いいじゃねぇか、それで」
たまらなくなって、綱吉はベッドに寝ているリボーンを布団ごと抱きしめた。体中傷だらけな彼のことを思って、なるべく力を込めないように抱擁して、綱吉はリボーンの首筋に顔を埋めた。
「オレ、おまえのことも、クロームのことも、大切にするから、大事にするからね」
「ああ。そうだな。おまえになら出来るさ」
持ち上げられたリボーンの手が綱吉の頭に触れた。彼の手がゆっくりと綱吉の髪を撫でてくれる。じわっと心の奥底から込みあげてきたものに耐えきれなくなって、綱吉は強く目を閉じた。左目の縁から涙がもりあがって流れ落ちていったような気配がした。
「オレ達は共犯者だ」
綱吉の頭を片腕で抱くようにして、リボーンが静かに囁く。
「オレ達は、生涯をかけて、クロームと、クロームが生んでくれる子供を幸せにしてやらなきゃならねぇ。それがオレとおまえの罪と罰だ。おまえを諦められないオレと、オレを諦められないおまえが出来る、精一杯のことだ」
「うん――、うん、そうだね」
詰まりそうになる息を吐き出して、綱吉はリボーンの首筋から顔を上げた。そしてリボーンの顔を見下ろす。途端、ぽたりとリボーンの頬へ、綱吉の涙が落ちた。彼は目を細めただけで何も言わなかった。
「幸せになろう。みんなで、絶対に。……幸せになろう。愛してる。リボーン」
泣きながら器用に笑って、綱吉は包帯と湿布に包まれたリボーンの左頬を右手で包み込んだ。
「オレと一緒に生きてくれて、ありがとう」
ゆっくりと息を吐き出したリボーンが、ゆっくりと左手を持ち上げ、綱吉の右の頬へ触れた。つめたいてのひらが綱吉の頬を包む。
「愛してる」
リボーンの言葉が身体に染みこんでいくのを感じながら、綱吉は目を閉じる。
「オレのことを諦めねぇでいてくれて、ありがとうな。ツナ」
互いのてのひらに、互いの体温を感じながら、綱吉とリボーンはしばらくそのまま、身動き一つ、しなかった。
|
|
××××× |
|
気がつくと、クロームは花畑の真ん中に座っていた。色とりどりの花が草原一面をおうように咲きほこり、かすかな甘い花の香りが微風にのって辺りを漂っていた。あまりにも五感を刺激する空間ゆえに混乱したものの、クロームはそれが夢のなかの風景だということを理解した。
すぐに理解できた理由は簡単だ。
クロームのすぐ近くに、六道骸が微笑んで立っていたからだ。
「骸様」
「こんばんは」
「こんばんは」
道化師のように口元だけで笑って、骸は花畑の地平線を眺めたまま口を開く。
「さきほど、リボーンと話をしてきました」
「リボーンと話? なにをお話してきたんです?」
おかしそうに笑った骸は、クロームの方を向いておおげさな様子で両腕を広げた。
「僕の大事な綱吉くんと僕の可愛いクロームに酷いことをしたら許しませんよ!と忠告してきました」
あまりにも楽しそうな骸につられて、クロームは思わず吹き出しそうになってしまった。口元を片手でおさえつつ、クロームは苦笑したままで骸を見上げた。
「そうですか。……リボーン、どんな様子でしたか?」
「ちょう、いらいらしてました。僕としましても、いろいろと溜飲がさがりました」
「それは、よかったですね」
肩を震わせながらクロームは笑っていた。
ふいに、骸の視線がクロームの視線を交わる。
何よりも綺麗で、
誰よりも美しい、
紅と蒼の瞳をもつ、
クロームの唯一の神さまが、
クロームを見ていた。
息を吸い込んだクロームは、六道骸の目をまっすぐに見つめて言った。
「骸さま。――私、ボスの子供を産みます」
優しげな眼差しを浮かべ、骸は頷いた。
「ええ、ぜひともお願いします。――出来ることならば、僕が産みたいくらいですけれど、残念ながら人間のオスは赤ん坊が産めません。きっと、僕と綱吉くんの子供ならば、中身も容姿も完璧な子供が生まれたでしょうに……。残念です」
「――そういうところで本気な骸様が、私は大好き」
「ええ。いつだって、僕は本気です。綱吉くんと、クロームと、千種や犬のためなら、いつだって全力で本気ですよ。僕の、愛する、家族のためならばね」
己自身の言葉にクスクスと笑いながら、骸はクロームの頭に触れる。彼の長い指先がクロームの長い髪へ差し入れられ、ゆっくりと髪を梳く。
「おまえが産んでくれる子ならば、僕は愛することができるでしょう。どこの人間か分からない女の血肉が混じった赤ん坊よりも、可愛いクロームが産む子供のほうが何倍も可愛いでしょうし、何倍も愛おしい」
「そう言ってもらえると、嬉しい……」
「綱吉くんとクロームの血と肉と魂が混じった子供だなんて――、ああ、早く、この腕に抱いてみたいですねぇ」
「ええ。産まれたら、ぜひ抱いてあげてください」
「――僕が」
自嘲気味に笑って、骸はクロームの髪を梳いていた手を己の胸元へそえ、おどけるように首を傾げた。
「この僕が、赤ん坊を抱きたいと思うような日がくるとは……ね」
クロームは微笑んで、骸のことを見つめていた。
六道骸という存在である彼の混沌と憎悪と悪意を、クロームは他の誰より知っている。綱吉の側にいることを選んだ彼は、いまは世界に対して暗い扉を閉じている。それはひとえに、沢田綱吉という存在が、骸の暗き扉の鍵であるからだ。綱吉が不在となった世界を、骸は何の躊躇いもなく破壊するだろうことを、クロームはよく分かっていた。
そんな彼が、赤ん坊を抱きたいという。
おそらくは様々なパラドクスを感じているはずだというのに、骸は両腕に新しい生命を抱きたいという。骸のなかにも、『人間』らしい感情が芽生えていることが、クロームは嬉しかった。微笑んでいても、友好的に見えても、その実、徹底的に人間を嫌っていた骸が、赤ん坊を――、人間を求めてくれることが、嬉しかった。
そうやって少しずつ、六道骸のなかに、何かが芽生えてくれればいいのにと、クロームは心から、心の奥底から願った。
そんなクロームの考えを察したかのように、骸が微苦笑を浮かべた。
「いまは、身体を治すことに集中なさい」
花畑に座り込んだままのクロームへ、背中を丸めるようにして骸が顔を近づける。
「僕の愛する可愛いクローム。おまえの未来が祝福に満ちますように」
神さまの唇が、前髪におおわれているクロームの額に触れる。
触れられた額から不思議な熱が伝わっていくようだった。
クロームは体中に伝わっていく心地の良い熱を感じながら目を閉じた。
「おやすみなさい。骸様……」
すぐ近くで、骸が吐息で笑う気配がした。
「おやすみなさい。クローム」
優しい浮遊感がクロームの身体を包み込む。
そして、クロームは、再び眠りのまどろみのなかへ、しずかに沈んでいった。
|
|
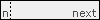 |