|
煙によって遮られていた視界が次第にはっきりと目の前に現れ始める。綱吉は息を吐き出して集中を解き、死ぬ気の炎を消した。奇術のようにあっという間に煙が消えていく。目の前に広がっていたのは、見知らぬ高級そうな内装のホテルの一室だった。綱吉の前の前にいたのはバズーカを構えていた雲雀で、彼はまだ垂れてきそうな鼻血をすすった綱吉を見て苦笑した。
「すいません。面倒かけて」
「別に。僕は楽しかったから、気にしてないよ」
「十代目!」
獄寺の声でハッとして、綱吉は視線を下へ向ける。雲雀よりも近い位置の絨毯のうえに獄寺が正座をしていた。
「ご無事でよかったです! おかえりなさい!」
「え、うん。ただいま。……っていか、獄寺くん、なんか、顔色すっごい悪いんだけど……」
明らかに満身創痍のような獄寺の様子に気が付いた綱吉が室内を見回すと、頭を打ち抜かれた死体が一体と、死んでいるのか生きているのかは分からないが、昏倒している男が一人いた。明らかに何かがあったような空気が室内に漂っている。いきなりの展開についていけず、綱吉は片手を身体の前に差し出して顔をしかめた。
「ちょっと待ってよ。戻ってきたら、もう、これ、どうなっちゃってるの? ねえ、雲雀さん、どういうことですか?」
「戻ってきてもらってさっそくの仕事だけど、君、リボーンのこと助けに行った方がいいよ」
「は?」
「十八の君が言っていたんだけど、彼、焼き殺されそうになってるみたいだよ」
「はあ!? どこでですか!」
「スカルとランボが援護に回ってるはずなんだけどね。いまどうなってるかは分からないんだ。――場所は北地区の『セント・ミッシェル劇場』。ここからは二十分くらいかな」
「え。ちょっと待ってください。急展開すぎて、脳がついていけてないんですけど」
「僕のバイクのキー、貸してあげる。事故らないでね」
バズーカを片手で持った雲雀が、ズボンのポケットを探って鍵を取り出して、綱吉に向かって放り投げた。混乱しつつも、ちゃんと鍵を受け止めて、綱吉は雲雀に頭を下げた。
「――ありがとうございます。えっと、セント・ミッシェル劇場ですね?」
「バイクにナビがついてるよ。住所は――」
雲雀が言う住所を小さな声で復唱しつつ、綱吉は獄寺へ視線を向ける。
「獄寺くん。怪我、深いの? 平気?」
「俺のことは大丈夫ですから。早くリボーンさんのとこに行ってあげてください。きっと、十代目のことをお待ちになってますから!」
血の気の引いた青白い顔で獄寺は拳を握って頷いた。
「十代目、お気をつけて!」
「ありがとう。獄寺くんも、早く治療を受けて」
獄寺の脇を通り抜け、雲雀が立っている部屋のドアがある方向へ歩きながら綱吉は言った。
「雲雀さん、バイク借ります。獄寺くんのこと、お願いします」
「ここの始末は任せておいて」
妙ににこやかに言う雲雀の態度に少々の不安を覚え、綱吉は彼の近くで一度立ち止まって彼と視線を合わせる。雲雀はうすく微笑んで首を傾げる。普段の彼からしてみれば、とても上機嫌な様子だったが、上機嫌だからといって、雲雀が素直に行動する保証はどこにもない。
「面倒だからって、獄寺くんのこと放置しないでくださいね。雲雀さん」
「……おまえ、放置しようとしてたのか。俺のこと」
「馬鹿は放置されてもしょうがないんじゃないの?」
獄寺が呻くように言うのを聞いて、雲雀は嘲笑うように言って一人でクスクスと笑い出す。顔面を引きつらせながら、獄寺は歯を食いしばって立ち上がり、雲雀のことを恨めしげに睨んだ。
「殴るぞ、てめぇ」
「それだけ元気なら大丈夫でしょ」
「えーと。喧嘩はよしてください。クールダウン、クールダウン!」
両手を持ち上げて上下させつつ綱吉が言うと、獄寺は不服そうな顔で息を吐き、雲雀は愉快そうに双眸を細めた。
「早く行かないと、彼、大変なんじゃないの?」
「うっわ! 分かりました! じゃ、いってきます!!」
ばたばたと足音を立てて綱吉はドアへ向かう。
「いってらっしゃいませ!」
朗らかな獄寺の声と、
「幸せになりにいっておいで」
優しい雲雀の声に背中を押されながら、綱吉はバイクのキーを握りしめて部屋から廊下へ飛び出した。
|
|
××××× |
|
「スカルさん! ちょっと、こりゃあ、冗談じゃないぜ!」
車から飛び出したスカルは、背後から聞こえてきたバーミリオンの言葉に何も返せなかった。建物の異変を察知した監視者から連絡を受けて、待機していた部隊すべてを率いて、劇場の前まできて――、スカルは絶句した。
すでに建物の出入り口を思われる場所は炎に包まれており、断続的な爆発音が建物内部から聞こえてくる。一瞬、燃えさかる建物めがけて走り出そうとしたものの、スカルは近づくのをやめた。スカルが一人、炎上する建物へ向かっていっても出来ることはない。
「周辺に爆発を誘導した人間がいるかもしれない! コンビを組んで、周辺に散れ!」
スカルの命令を聞いたボンゴレの構成員達が各々コンビを組んで、建物を取り囲む周辺へ散開していく。舌打ちするスカルの背後で、バーミリオンが携帯電話で消防へ電話している声が聞こえてくる。消防が到着する前に劇場が燃え落ちてしまうほうが早いかもしれない。もしもそんなことになれば、中に入っていった人間は焼死してしまう。
閉じた瞼の裏に焼けこげた死体の残像が浮かぶのを、首を振ってはらいのけ、スカルは泣きそうになる面を引き締めて、燃え上がる建物を仇敵のように睨み付けた。
「爆破させた奴ら、まだそう遠くには行ってないんじゃないっすかね?」
スカルの傍らに立っているバーミリオンが、胸元のホルスターから拳銃を引き抜く。スカルは彼が辺りを見回すのを横目にいれながら、右手をスーツの内側へ差し入れ、拳銃を握りしめて引き抜いた。
「時限爆弾だったらいないだろうが……。リボーン先輩とクロームが入っていったのを確認してから爆発させた確率のが高いだろうからな、少数で行動してる奴らがいるはずだ。……たぶん、爆破のスイッチを押した時点で離脱を開始してるだろけどな……」
突然、建物の外観が音をたてて燃え落ちたて大きな音を立てた。もうもうと煙が立ち上り、十分に距離があるというのに、激しい熱が肌をさす。晴れた青空へ向かって揺れる真っ赤な火柱がまるで蛇のようにうねっている。
「これじゃあ、もう誰も近づけやしない……」
バーミリオンが顔をしかめ、何かを言いかけた瞬間――、
「己の無力さで死ねたらよかったんじゃないですか? カルカッサの参謀さん」
背後に急に気配が生まれた。
反射的に拳銃を持った腕を持ち上げながら背後を振り返る。ほとんど同時に振り返ったバーミリオンとスカルは、銃口の先にいた人物を見て、目を見開いた。
「ろくどう、むくろ」
六道骸は、スタイリッシュな細身の黒いロングコートを身にまとい、両手をコートのポケットに入れて微笑んでいた。スカルが聞いていた情報では、彼は死んでもおかしくないような重傷を負って、森の中へ放置されたはずだった。その後、彼を救出する手だては何も行われていない。クロームからの伝達で、骸自身が救出の必要はないと言ったためだ。
腹部の損傷は臓器の損傷を意味する。
足の怪我からの出血もひどかったはずだ。
生きているはずが、ない。
「六道さん! 生きてたのか!?」
バーミリオンが拳銃を下ろし、驚きと戸惑いがまじったような顔で言った。
「おまえ、生きていたのか?」
骸の全身をくまなく眺め、スカルが呻くように言うと、骸はコートのポケットから両手を出して、ひらひらと顔の横辺りで手を振った。
「はいはい、生きてますよ。死んでなくてすいませんね。……というか、みなさん、僕が生きてたらまずいことでもあるんですか? なんでそんなに驚くのか……。いやな感じです……」
「生存を信じられるような情報がなかったからな。死んだものと思ってたんだ」
「はあ、そうですか。そう簡単に死ねるような生き方してないんで、死んでませんよ。残念ながら」
少々、すねたように唇をとがらせつつ、骸が肩をすくめる。その態度には、死にかけていた人間の雰囲気は皆無だ。傷をかばっている様子もなければ、顔色もいたって正常に見える。
「おまえが生きてるなら、ボンゴレも喜ぶだろう。そうとう、気にしていたからな。おまえのことを」
「そうですか。それは嬉しいですね」
「実は、いま――」
バーミリオンの報告を遮るように、骸が片手をあげる。言いかけた言葉を飲み込むようにバーミリオンが口を閉じるのを見て、骸は女顔めいた美しい顔に微笑を浮かべた。
「現状の説明はいりません。僕は僕で行動して、少々邪魔なものを排除したり、操ったりしていろいろしてたんですから。綱吉くんがいまどこにいるかとか、ドン・トマゾと雲雀恭弥がどう動いていたかということも、すべて分かってますからね」
「相変わらず、人間を逸脱した存在感だな……」
「僕、あなたと違って有能なんです、すみません」
にっこりと笑ってスカルを見下す骸の視線が、スカルをパシリとして扱うリボーンの視線によく似ている。スカルは強い屈辱感で一瞬、頭のなかで火花が散った気がした。何か言ってやろうと息を吸い込んだものの、どんな罵声を浴びせたところで、骸が何の屈辱も感じないことがすぐに分かってしまい、結局は何も言えなかった。
何も言わないスカルを面白そうに一瞥してから歩き出した骸は、スカルやバーミリオンよりも建物へ近い場所まで行って立ち止まった。燃えさかる建物まではまだ数十メートルくらいの距離があったが、圧倒的な熱のせいで目を開けているのもつらいくらいだった。
「どうするつもりだ?」
「僕にしか出来ないことをするだけです」
スカルの問いに、骸は微笑みを返しただけで、すぐに建物へ視線を向けた。
「まったく……、油断もいいところですね。爆弾を使って脅しをしてくる連中が相手なら、呼び出された場所に爆弾があってもおかしくないことに、どうして誰も気が付かなかったんですか? 馬鹿ですか、あなたたち……」
「…………………」
「…………………」
スカルもバーミリオンも何も言い返せない。
嫌味たらしく大げさなため息をついた、骸が右手を身体の横へ持ち上げる。その手に音もなく三又槍が現れると、彼は握りしめた槍を槍先を上にして身体の前に構えた。
「過ぎたことを言ったとしても仕方ありませんしね。――ちょっと集中しますから、僕の身体のこと警護しておいてくださいね」
スカル達の返事を待たずに、骸が目を閉じた。
途端、身体に見えない加圧がかかった。骸が強い幻術を使用し始めた副作用がスカルやバーミリオンの身体に圧迫を与えているのだ。おそらく骸は、建物内部に閉じこめられているクロームの身体に憑依をして、幻覚を作用させているのかもしれない。骸の幻覚は協力だ。彼ならば、燃えさかる劫火の中から、無事にリボーンとクロームを助け出せるかも知れない。淡い期待でスカルの気持ちが大きくふくれあがった次の間、
「バーミリオン!」
一人の男の大きな声がして、スカルはびくっと肩を揺らしてしまった。バーミリオンに向かって走ってきた男は、片手に携帯電話を持ったまま、もう一度バーミリオンの名前を叫ぶ。彼のただごとではない様子に、スカルは嫌な予感がして心臓が痛くなった。
「何だ?!」
「すげえ、スピードのバイクが近づいてくるって、狙撃班から――、ランボさんから連絡あって、それが――」
男がかけてきた道路の向こう側から、けたたましいバイクのエンジン音が近づいてくる。アクセルが全開なのか、地平線にバイクの姿が見えてから、あっという間にバイクがどんどんと近づいてくる。ヘルメットもバイクの車体も真っ黒――だと思われたが、ヘルメットの前面側に血のように赤いペイントで翼を広げた鳥のマークが大きくあしらわれているのが見えた。黒いヘルメットに赤い鳥のペイント――、雲雀恭弥のバイクだとスカルはすぐに思い出した。
「雲雀さんですかね?」
スカルと同じく、雲雀のバイクだと気がついたバーミリオンが言うその声は、目の前まで近づいてきたバイクのエンジン音によってかき消されそうだった。ブレーキをかけきれなかったのか、タイヤから白煙を立ち上らせ、九十度ターンをしながらバイクが停車する。ボンゴレの構成員達が乗ってきた車のすぐ手前でバイクを止めた人物は、バイクを停車指させると、颯爽とシートから降りて、ヘルメットを外した。
ふわり、と色素のうすい髪がヘルメットの下から現れた瞬間、
「えっ」
スカルは口を開いたまま、ぽかんとしてしまった。
「――つ、な?」
雲雀のバイクを運転して現れたのは、綱吉だった。
しかも、二十七歳の、沢田綱吉だ。
彼はヘルメットをバイクのハンドルにひっかけると、辺りを見回し、スカルのことを目にすると、すぐに駆け寄ってくる。
「スカル! バーミリオン! リボーンは?! まさかあの建物ん中じゃあ……――って、え? 骸!?」
スカルが何かを答える前に、綱吉は槍を構えて立っていた骸に気がついて驚いたように目を見開く。綱吉が骸に近づいていくと、骸が槍を手にしたまま、近づいていった綱吉の方へ身体を向けた。彼は綱吉の姿を頭の先から足の先まで眺め、満足そうに頷いた。
「――雲雀恭弥がうまくやったようですね」
「おまえっ、怪我ッ、怪我してなかったか!?」
言うが早く、綱吉は両手で骸の腹部と背中をぺたぺたと触り出す。骸は痛がる様子もみせず、にこにこと機嫌が良さそうに笑いながら綱吉の所行を見下ろしていた。
「あなたの方こそ、何ともないんですか? その様子だと、目は見えるようになったみたいですね?」
「うん。見えるようになってる。心配かけたね。もう大丈夫! ……っていうか、ほんとに、あのなかにリボーンがいるとか言う?」
「ええ。ほんとですよ。あのなかにあなたの愛しいお姫様がいますから、助けてさしあげたらどうですか?」
「うっわ、久しぶりに聞いた。骸の皮肉」
「事実でしょう? ――あなたのお姫様のついでに、僕の可愛いクロームも助けてくれませんかね?」
骸の皮肉に顔をしかめていた綱吉が、ぎょっとしたように身体を震わせ、信じられないものを見るように骸を見た。
「え? リボーンの他に、クロームの中にいるのかよ!? だったら、骸、なんで助けないんだよ!」
「僕、これでも、重傷を負った身なんですよ……? もっと労ってくださいよー、綱吉くん」
骸は突然に落胆したように頭をうなだれ、弱々しく首を振った。スカルから見ても、あからさまに演技的な態度だった。骸の演技的な動作に顔を引きつらせた綱吉は、深く息を吸い込んだかと思うと思い切り叫んだ。
「なに急にしおらしい態度になってんだ! おまえ、殺したって死ぬような男じゃないじゃんか! こういう修羅場なときに頑張らないで、おまえがいつ頑張るっていうの!?」
「うっ。二十七歳の綱吉くんは僕にひどく冷たいですね。過去のあなたはあんなに可愛くて優しくて泣き虫で弱々しくてぐっちゃぐちゃにしたいほど愚かで可愛かったのに――」
「どさくさにまぎれて言いたい放題するな! しかも可愛いって二回言ったろ! 怒るぞ! って、いまはそんな馬鹿なこと言ってる場合じゃないだろ!」
「くふふ! 大人な綱吉くんのつっこみは活き活きしてていいですねえ」
「ばかむくろ! もういいっ!」
叩き付けるように骸に向かって叫んだ綱吉が急にスカルを見た。思わずスカルは姿勢を正して綱吉の視線を受け止めた。
「スカルッ、中にいるのは二人だけなの?」
「え、あ――、ああ、そうだ!」
「分かった。消防と警察に連絡は?」
「してあります。ボス」
バーミリオンが答えると、綱吉は大きく頷いて、右手を挙げた。
「了解。――みんな、ここで待機ね!」
言うが早く、綱吉は燃えさかる建物めがけて走っていく。
「手伝いましょーか?」
「したきゃ、勝手に援護してくれっ」
呑気そうな骸の声に振り向きもせずに、綱吉は走って行ってしまった。
「うーん。いい反応です」
一人で頷きながら、骸が言う。
スカルは半眼で骸を見つめつつ、呆れて息をついた。
「あんた、なにがしたいんだ?」
「綱吉くんが元気で、僕はとても嬉しいです」
「答えになってない」
「いいじゃないですか。どうせ、もうすぐ彼は彼と再会して幸せになるんですから」
言葉のうらに棘がはらんでいるような台詞を言って、骸が双眸を細めて微笑する。先ほど、綱吉の目の前で浮かべていた表情と似通ってはいるが、明らかに肌で感じる温度差がある。スカルが複雑な顔をしているのを横目で見た骸は、舞台役者のように作り物の愛想笑いを浮かべた。
「ようやく我らの王がご帰還です。これで僕たちの世界は再び、幸福に満ちることでしょう」
「……道化師め」
スカルが呆れて呟くと、骸は吐息で笑った。そして、視線を燃えさかる建物へ向け、再び槍を構えて目を閉じる。
スカルもごうごうと燃える建物へ目を向ける。
ちょうど、綱吉が元は建物の入り口だった場所辺りに立ち止まり、片足を引いて、体勢を低く保ったところだった。
|
|
××××× |
|
「どうしたんだ?」
骸が憑依しているクロームが、目を閉じたまま黙り込んでから、数分が経過している。沈黙にたまりかねたリボーンが問いかけると、閉じていたクロームの瞼が音もなく持ち上がり、黒い瞳がリボーンを見た。
「――やっぱりやめます」
「あん?」
「リボーン。僕とクロームとここで心中しましょう!」
にこやかに微笑んで言い放ったクロームの姿をした『骸』は、幻覚の水の膜を一定の状態で保ち、それ以上何もしなかった。一瞬、悪い冗談と思っていたリボーンも、にこにこと笑うばかりで、何もしない『骸』が本気でこの場にとどまることを選んでいるのだと悟り、ぎょっとした。
「いきなりなに言いだしやがる! 気でも狂ったか?!」
「狂ってなどいませんよ。どうやら、もっと良いラストシーンがあるみたいなんで、それ待ちにします」
「もっと良いラストシーン? おまえ、いったい、何を――」
リボーンが呻いて言葉を失った瞬間、出入り口側から激しい破壊音がして、目を開けていられないほどの強風が吹いた。目を細めた視界の先で、瓦礫と共に燃えていた炎が吹き飛んで消えていく。
とはいえ、全部の炎がかき消えた訳ではない。ホールから劇場までの壁が破壊され、炎が逃げ道を得たせいか、新しい酸素が供給されたせいか、大きく開いた建物の穴へ炎の流れが出来る。
ふいに煙のなかから誰かが建物の中へ駆け込んできた。スーツを着た男性だと認識した瞬間、目に入ったのは額と両手にともるオレンジ色の炎だった。リボーンは絨毯のうえに座り込んだまま、息を呑んで目を見開く。
見間違えようもない、死ぬ気の炎――ボンゴレの血族の証、そしてボンゴレ十代目である証だ。
「ツナ!」
リボーンは叫んだ。
「ツナ!!」
煙でむせていた綱吉が、リボーンを見てすぐに駆けだした。燃え落ちてくる瓦礫などものともせず――軽やかにターンをしつつ彼は瓦礫を片手で振り払った――、綱吉は炎の遠心力で通常よりも速い速度でリボーンのところまで駆けつけてきた。『骸』が作り上げている水の膜を少し怪訝そうな顔をして通り抜けた彼は、座り込んでいるリボーンを眺めたかと思うと、錯乱したかのように悲鳴をあげながらリボーンの目の前にへたりこんだ。
「うわあああああ! リボーン、なにそれ! すっごい怪我! いやああぁああ! 顔に傷とか最悪!! なんで? どうして? なんで?!」
叫びながら、綱吉は両腕でリボーンの身体を抱きしめてくる。リボーンは言いたかった言葉も伝えたかった表情も何もかもどうでもよくなって、よく分からない錯乱を続ける綱吉の背中を、拳銃を持ったままの手の脇で叩いた。
「落ち着け、馬鹿。こんなの、すぐに治る」
「すぐに治る訳ないだろう! オレがいない間に何があったての!? ああもう! こんな、こんな怪我して!! 馬鹿! 目なんて怪我して! 視力に影響があったらどうすんのさ! あああぁあああ、もう! どうしておまえがこんな目にあってるの!? ――って、クロームまで怪我してるじゃないか!」
リボーンを腕に抱きしめたまま、綱吉は顔をあげてクロームを見た。クロームは、リボーンを瓦礫からかばった際に、背中と頭を負傷したせいで、ぽたぽたとわずかずつだったが出血している。その赤い血を見た途端、見る間に綱吉の顔が苦痛そうにゆがんでいった。
「クロームも!そんな血だらけになって! ……くそっ!! 今回の件だけは、絶対にオレが最後まで指揮して、一人残らず見つけだして、かならず何らかの制裁を与えてやる! もう決めた、絶対に決めた!」
「――あのう、綱吉くん」
「ん? はい? って、あっ、なんだ、クロームのなかに骸がいるのか……」
いくぶんか、落ち着いてきたのか、綱吉が両腕をゆるめる。リボーンは間近に綱吉の顔を見た。二十七歳の綱吉の顔を見た。綱吉の琥珀色の瞳がリボーンを見る。触れあえるすぐ側に綱吉がいることが信じられなくて、リボーンは普段ならば絶対にしないのだが――まして、六道骸が側にいるのならばなおさら絶対にしなかったろうが――、綱吉の身体へと自らよりかかるようにして、彼の体温に身を任せた。彼の腕がリボーンの背中にしっかりと回され、「もう大丈夫だからね」という綱吉の優しい声がリボーンの頭上から振ってきた。
「僕は不満です」
クロームの顔でむっつりとした表情を浮かべ、『骸』はすねるように口元をゆがめる。
「リボーンとクロームだけ、そんなに心配して、なんで僕だけないがしろなんですか? 僕も一応、生死の境とか、彷徨っちゃってた身なんですけど?」
「……だって、おまえ、元気じゃん」
「……ああ、なんだか急に死にたくなってきました……」
心底落ち込んだように『骸』が呟くのを聞いて、綱吉は苦笑した。
「うそ。冗談。――おまえが無事で、オレは嬉しいよ。骸。……おいで」
綱吉が『骸』に向かって手を伸ばす。『骸』は己にのばされた綱吉の手をジッと見つめた後、まるで猫のようにすうっと綱吉の手に導かれるように彼の腕の中へ身体を寄せる。もちろん、綱吉は片腕にリボーンの身体を抱き留めている。『骸』というか、クロームの身体とリボーンの身体とを片腕ずつに抱きしめた綱吉は、ありったけの気持ちをこめるようにぎゅっと腕に力を込め、リボーン達を抱きしめた。
「二人ともありがとう。……オレのためにこんなに痛い思いして……、ほんとうにごめんね。でももう大丈夫だから。今度は、オレが二人のことを全力で守るよ」
「……ぎゅーっと、なんでさっきしてくれなかったんですか?」
綱吉の肩に頭をもたれさせたまま、クロームの顔で『骸』が囁く。綱吉は悪戯っぽく片目を細め、クロームの髪を指先ですいた。
「え。やっぱり、抱きしめるなら可愛い方がいいじゃない?」
「……クロームだけずるいですねぇ」
「あ、そう? じゃあ、骸のこともあとで抱きしめてやるよ」
「え。本当ですか?」
「そんな奴を抱きしめるくらいなら、オレのことを抱きしめとけ。バカツナ」
「ヤキモチですか? いいじゃないですか、ハグくらい」
「うるせえ。おまえなんかに抱擁だろうとなんだろうとさせるか」
リボーンが顔をしかめると、綱吉と『骸』は似たようなにやついた笑みを浮かべて、くすくすと笑い出す。
「ねえ、リボーン。それってヤキモチ?」
「へえ、ヤキモチですか? それじゃあ、僕はヤキモチをやいてもらえるほど、あなたにライバル視されてるって訳ですね。光栄です」
「てめーら、黙らねぇと撃つぞ」
銃を持った手を持ち上げると、彼等は唇を閉じて視線を交わし合い、すぐに笑いこらえるような顔になる。波状のように生まれた苛立ち任せに、リボーンは引き金を引いてやろうかとも思ったが、せっかく会うことが出来た綱吉に向かって引き金は引けなかった。
「こんなとこじゃ、落ち着いて話せないよ。外へでよう」
「ええ、そうしましょう」
『骸』が綱吉から身を引いて立ち上がる。リボーンも立ち上がろうとした瞬間、ふわっと綱吉の腕に足下をすくわれ、そのまま彼の胸へ軽く抱き上げられてしまった。リボーンも驚いたが、『骸』も驚いたようで、眼帯に隠されていない片目を見開いて動きを止めた。『骸』とリボーンの視線が絡む。『彼』は笑いをこらえるようにリボーンから視線を外したが、次の間、耐えきれなくなったように吹き出した。羞恥心でリボーンは己の顔が熱くなっていくのをまざまざと感じて背筋が寒くなった。
「こら! 降ろせ!」
「え。やだ」
「歩けるから降ろせ! 馬鹿!」
「だめ、だめ。リボーン、大人しくオレに抱き上げられてなよ。大怪我してんだからんさ」
「外にスカルや他の奴らがいるだろ!?」
笑顔を浮かべるばかりで綱吉は一向にリボーンを下ろす気配はない。
「うん。いるけど――、気にしない気にしない」
「降ろせ! 撃つぞ!」
手に持っていた銃の銃口を綱吉の眉間へ押しつける。綱吉は銃とリボーンを見比べたあと、穏やかに双眸を細めた。
「リボーンはオレのことは撃てないよ」
確かに、リボーンには綱吉は撃てない。
舌打ちして、リボーンは拳銃を動かしにくい右手へ移動させ、自由になる左手で綱吉のあごを掴んで、力任せに押しやったが、彼は首を振ってすぐにリボーンの手を外してしまう。
「降ろせって言ってるだろ!!」
「だから、いやだって言ってるだろ? はいはい、大人しくしててね、オレの可愛いバンビちゃん」
絶句したリボーンの額に、ちゅ、と綱吉がキスを落とす。
「……バンビちゃん……」
笑いをこらえきれない様子で『骸』が唇を噛んでリボーンを見る。かあっと首筋の後ろが熱くなるのを感じながら、リボーンは思い切り八つ当たりだと自覚しつつも、『骸』を睨んで叫び声を上げた。
「うるせえ! なまあったかい目で見るんじゃねえ!」
「いいじゃない、リボーン。ちょっとくらい大人しくしてよ。オレ、いま、実感してるんだからさあ。おまえが腕のなかにいるんだって――。おまえのもとへ帰ってこられて、オレは本当に嬉しいんだよ、リボーン」
静かに、穏やかに言いながら、綱吉はリボーンの頭に頬を寄せる。綱吉の両腕から、そうっと大事なものを抱えるように抱きかかえられていることがリボーンにも伝わってくる。甘やかな痺れのようなものがリボーンの内側から外側へ向かって溢れていくような気がした。リボーンが愛した沢田綱吉は、やはりたった一人しか、目の前にいる沢田綱吉しかいないと――そう思うと、心が震えた。
「ツナ」
名を呼ぶと、彼は幸せそうな顔をして、リボーンの顔を間近に見つめて目を細めた。
「ね? だから、大人しく、オレの腕のなかにいて。オレにおまえを感じさせて?」
「――熱烈な愛の告白ですねえ」
わざとらしい台詞を言って、骸が小さく舌を出す。
せっかくの綱吉との逢瀬だというのに、いちばん側に居て欲しくない人間が側にいることに、リボーンはかるく絶望を感じた。リボーンが半眼で睨み付けても、骸はにやにやと笑うばかりで、気を利かせるつもりが一切ないことを体言していた。
「おまえの存在のせいでなにもかも台無しだ」
骸は瞳をぐるりと回して、肩をすくめる。何か言ってやろうとリボーンが息を吸い込んだところを、綱吉がさらにリボーンの身体を抱き上げ、リボーンの首筋あたりに顔をよせた。ふわりとした彼の髪がリボーンの首や顎に触れてくすぐったかったが、リボーンは大人しく綱吉のやりたいようにさせてやった。そのぐらいのサービスを許すくらい、いまのリボーンは綱吉に対して寛容だった。そして、リボーンの中にある、綱吉への愛情にも寛容だった。
「好きだよ、大好き。愛してる。ああ、よかった、あのまま、戻れなかったらどうしようかと思ったよ……、リボーン、リボーン、オレ、ほんとに嬉しい……」
うわごとのように言いながら、綱吉の唇がリボーンの首筋をたどり、あごに触れ、そして唇に触れる。深くないが、数回に渡って唇が触れる。一瞬、リボーンは『骸』の表情を見ようとしたが、『彼』は目を伏せて、うっすらと微笑みを浮かべているだけだった。
キスに満足したのか、にっこりと笑った綱吉の顔がリボーンの間近にあった。間抜けだとも言えそうな、ゆるみきった綱吉の顔を眺めているうちに、もう何もかがリボーンのなかでどうでもいい事のように思えた。
綱吉が幸せならば、もう何もかもどうでもいい。
「……勝手にしろ」
抵抗をやめてリボーンが身体から力を抜くと、綱吉は嬉しそうに「ありがとう」と言った。そして、リボーンを抱き上げたまま歩いて、骸の側へ近寄っていく。
「先生の許可がでました」
「よかったですねぇ」
おかしそうに笑いながら、『骸』は何度も頷いた。
そして『彼』は、右手に槍を持ち、左手を胸元にそえ、上目遣いに綱吉を見つめた。
「さあ、ご命令を。――マイ・ボス」
綱吉の瞳が『骸』を見つめ、そしてリボーンを見つめた。
そうしてから、彼は、優しく、やさしく笑って、頷いた。
「みんなで、オレ達の『家』に帰ろう」
「――はい」
『骸』は片手に槍を持ち、淑女がドレスの裾を持って一礼するようにわずかに膝を曲げて、かるく頭を下げる。
「僕達の『家』へ帰りましょう。みんなが、あなたを待っています」
両手で地面と水平に槍を構えた『骸』が目を閉じる。
途端に、三名を囲んでいた半円型の水球が勢いを増し、けたたましい水流音をたてながら範囲を広げていく。
黙って『骸』が作り出した水球の流れが建物の炎をかき消していくのを眺めていたリボーンの顔のすぐ近くに綱吉の顔がある。彼はリボーンの顔をうすく微笑んだまま眺め、リボーンの頭に頬を寄せ、猫が甘えるような仕草をする。リボーンは自由に動く左手を綱吉の髪に差し入れた。
「ずっと、おまえに逢いたかったぞ。ツナ」
綱吉は泣きそうなくらいに微笑んで、リボーンの顔のすぐ近くで目を閉じる。右目の縁から一筋だけ、涙が頬をすべり落ちていった。
「オレも。……ずっと、逢いたかった。おまえに逢いたかったよ、リボーン」
力強い綱吉の腕に抱かれたまま、リボーンは左腕を伸ばして綱吉の頭を腕の中に包み込むように抱きしめた。
もう絶対に離しはしない。
そう思いながら、リボーンは綱吉のやわからな髪にキスをした。
|
|
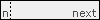 |