|
トマゾ・ファミリィの男に導かれ、コロネロとラルは音を立てないようにビルとビルの合間に存在する暗い路地を歩いていた。背後は主立った商業ビルが建ち並んでいる大通りがある。トマゾの男とコロネロ達はそんな大通りを背面にして、何本かの通りを隔てた裏通りへと向かって歩いていた。
二人とも接近戦用の装備でいつもよりも体重が増しているものの、そういった重量で動きが牽制されるような鍛え方はしていなかったし、むしろ重装備であればあるほど気が引き締まるような訓練に耐えてきた二人だ。裾の長いコートの下にある武器で、数十人を相手にしても渡り合えるくらいの物量を装備してきた。戦闘において、コロネロとラルはプロだ。それは彼等がマフィアではなく軍人なのだから当たり前だった。たった一人を殺害する殺し屋ではなく、敵を全滅させるために戦うのが軍人だ。とはいえ、現在のコロネロとラルは特定の軍には所属していないので傭兵だった。二人とも名は広く知られている存在なので、引く手は数多だ。今回もとある紛争の沈静化のために依頼を受けたのだが、沢田綱吉に降りかかった災厄を知ったがために、依頼が滞ってしまっている状態だった。ぎりぎりで契約を結ぶ前だったのでよかったものの、もしも契約を結んでしまえば傭兵たるもの契約を破棄する訳にはいかず、綱吉の危機だというのに何も出来ないところだった。
沢田綱吉。
日本人でありながら、初代ドン・ボンゴレ、ジョットの血を引いた由緒正しきマフィアの申し子――、ブラッド・オブ・ボンゴレ、気高き孤高の王座に座るべき人間。
幼いころから、現在に至るまで、コロネロもラルもずっと綱吉のことを見守ってきた。彼から見ればコロネロもラルもまだ十代半ばの子供だったろうが――、コロネロ達から見れば綱吉は出来の悪い弟そのものだった。彼はよく泣いたし弱音は吐くしで、子供のころは本当にこんな人間がマフィアになんてなれるのかと、二人で呆れていたものだったが――、結局彼はドン・ボンゴレとしてボンゴレの頂点となり、めまぐるしい日々を送るようになった。
綱吉がドン・ボンゴレとして就任した際のパーティのとき、ラルが綱吉は長生きできないタイプだと言ったのを、コロネロは今でも覚えている。おそらく、ラルは綱吉が優しすぎることを心配して、彼が精神的に病んでしまい、死んでしまうのではないかと思っていたのだろう。彼女の心配は取り越し苦労だったのか、綱吉は二十七歳を迎えた今も元気にドンとして生きている。
それでも、コロネロはラルの言葉をふいに思い出す。
『沢田はきっと、長くは世界に留まってはいられない。『あれ』はマフィアとして生きるにはきれいすぎる――、そういう奴はこの世界では永遠に敵を作り続けるし、そいつらを殺し続けるなんてこと……、『あれ』に出来ると思うか?』
コロネロは答えられなかった。
ラルは苦笑しようとして失敗したかのような、落胆したような顔で目を伏せた。
俯いた彼女の髪に触れたいと思ったがコロネロの指先はぴくりとも動かなかった。
もう、だいぶ前の話だ。
時刻はすでに夜になろうとしていた。夕刻というには暗く、夜と言うには明るすぎるような――曖昧な時間がたゆたうように世界に存在している。
細い路地が途切れ、通りに面している場所に、上下とも黒のスーツに身を包んだ青年が立っていた。彼の周囲には三名ほどの壮齢の男達が立っていて、三名とも驚くほどに体格のよいレスラーのような大男達だった。
「ボス」
コロネロ達を案内してくれた男が控えめな声音で言う。
「へーい、はいはい」
あちこちに毛先が跳ねた髪型に、耳、首、腕、指とあらゆる場所に装飾をつけた青年――若きドン・トマゾ、内藤ロンシャンはコロネロ達に気が付くと、両腕をばたつかせるオーバーなリアクションをしながら歩み寄ってきた。
「おっそーい、コロちゃん、ラルちゃん。俺っち、まちくたびれー」
おどけるように片目を閉じたロンシャンの態度に、ラルが辟易したように両眼を細める。彼女が彼のような男のことが一番理解できないと思っていることをコロネロは重々承知だったが、いまはそんなことを確認している場合ではない。
「相変わらずだな、トマゾ」
ラルが揶揄するように言っても、ロンシャンは気が付かないのか、両手で作った銃をラルに向けて撃つふりをしながら身体を揺らして笑った。
「俺はいつだって元気っすよー、だってロンシャンだから!」
「……………………」
何か言いたげな雰囲気でラルがますます半眼になるのを横目に見ながら、コロネロは嘆息して、にまにまと笑うロンシャンをかるく睨み付けた。
「仲間はこれだけなのか?」
「んーん。散開して、囲んでんのよ。建物の北側でマングスタが待機してて、表側にはパンテーラがいるよ。それぞれに二十人の兵隊付き。俺んとこは潜入部隊だから、俺とこいつらだけなんだけどねー」
「本当に、ここなんだろうな?」
「表向きは設計事務所らしいんだけどねーえ。電気とかガスとかの公共料金が異常でねえ、調べてみたら、ここに送られてくる荷物の種類もおかしいし、出入りしてる人間も――なんかさー、同業者くさいしさ。そんで、ちょっと人を使って調べさせてみたり、情報屋さんとやりとりしたら、ぼっふんぼっふん埃がでてきてさぁあ、こりゃあ当たりなんじゃないのォと思ったのよ。設計事務所だなんて語ってるけど、表に出せない研究をしてる研究施設なんじゃないのかなーってね」
「……ちゃんと調べたんだろうな」
「ラルちゃん、疑り深い! でもそんなとこがラルちゃんらしい! 俺っち胸きゅん!」
がばっと両腕を広げたロンシャンに怯えるようにラルがびくりと身体を揺らす。ロンシャンの好みにラルは引っかからないだろうし、ラルの好みはロンシャンとは真逆の位置だろう。彼女と彼に会話をさせていると話はすれ違うばかりか、まったく進まずに道に迷い出してしまいかねない。
コロネロはさりげなく、ラルのことを背後におしやりつつ、会話の主導権を主張するように張りのある声音を出す。
「そこまで言うのならば確証があるんだろうな? コラ」
「まあねぇ、あるっすよ、証拠! 結婚式の襲撃で使われた拳銃と同じロットナンバーの拳銃がうちの目の届く範囲で取り引きされてさー。そこの前に、その拳銃が取り引きされたのが『ここ』で、『ここ』からまた違うところに転売されたらしいんだけどさ。ただの設計事務所が武器密売してるんなら、他にも悪いこととかしちゃってそうじゃない?」
「気配を気取られてはいないんだな?」
「だいじょーぶっしょ。なんの変化もないし。コロちゃんたちが加勢に来てくれるって連絡入ってたから、それからにしようかと思ってたからね。包囲してちょっと時間経ってるけど、特に変化はないよん」
「ラル。おまえはここにいてくれ」
不服そうにラルが片眉を跳ね上げ、コロネロを睨み上げる。彼女の目線は大きなサングラスで覆われていたが、それでも不機嫌そうな瞳のひかりがコロネロのことを射抜くように見たのは分かる。
「なに? オレのほうが待機組だってのか?」
コロネロは隠すことなくロンシャンのことを指さして言った。
「じゃあ、おまえ、こいつを一緒に行って、冷静でいられんのか? コラ」
「……………………」
開きかけた唇を閉じて、ラルは片手で犬を追い払うような仕草をした。そしてすぐに振った手を右耳へ滑らせる。
「何かあったらすぐにオレを呼べよ」」
「ああ。必ず報告する」
耳に小さなイヤホン、襟元に高感度の小型マイクをコロネロ達は装備している。オンとオフは腕時計の横のスイッチで切り替わるように作られている。これらの装備品はボンゴレから支給されている彼等独自の機械だった。
ロンシャンは、彼の周囲にいた屈強な男達と短いやりとりをしてから、コロネロと向き合った。相変わらず、緊張感のかけらもないだらしのない顔をしている彼に多少の不安を覚えながらも――、コロネロは潜入場所であるビルを視線で指し示した。
「まずは俺とトマゾとで潜入して、内部を探る。俺達だけでバズーカの奪取まで出来れば、そのままここを離脱すりゃあいいし、もしも騒ぎになるようだったら、トマゾファミリィの力を借りるぞ、コラ」
「どーぞどーぞ。うちは、血の気の多い奴しかいないからさー、時々どんぱちやらないとハジけちゃうからさ、大騒ぎ大歓迎!」
「大騒ぎすんのは最悪のケースの場合だけだからな、勘違いするんじゃねーぞ」
「わかってるって! コロちゃんてば、心配性なんだからー!」
ばしばしと背中を片手で叩かれる痛みを感じながら、コロネロは脱力しそうになる身体に力を入れる。横目でラルを見やれば、彼女はうろんそうな目でロンシャンとコロネロを見て、盛大な溜息をついて顔を伏せる。
「行くぞ。トマゾ」
「はいはーい!」
遠足へ向かう子供のような返事に背中を押されつつも、コロネロは闇が滑り落ちてきた静かな世界を見据え、腰に下げていたホルスターからサバイバルナイフを引き抜いた。
|
|
××××× |
|
商業用のテナントビルの裏手に回ると、通常のビルには不似合いな電子キーの配列が並んだ物々しいドアがわざとへこんだ壁位置に設置されていた。通路からは死角になっていて、一見するどドアがあることなど分からないようになっている作りだ。
うさんくさいな。
胸中で呟きながら、コロネロはドアの周囲へ視線をはしらせる。案の定、ドア付近には監視カメラが二台ほど設置されていた。映るか映らないか、ぎりぎりの範囲でコロネロ達は立ち止まる。
「どうするんだ?」
「いいものもらってきてるんだよーん。うちのね、技術部だってね、ボンゴレには敵わないだろーけど、頑張ってんのよ」
歯を見せるようにして笑ったロンシャンは、スーツのポケットに両手を突っ込んで、何かを取り出した。それはフロッピーディスクほどの大きさの薄いカードのような代物だった。
「なんだ、それ」
「これはねー、その場でそれらしー映像をとって――」
と、言いながら、ロンシャンは二台のカメラに写らないぎりぎりの位置を動き回り、カードをかざすようにした。戻ってきた彼の手にあるカードには、デジカメで撮ったかのように扉の周辺の風景が映っていた。
「これをカメラんとこにひっつけておくのよ。名付けて、『こりゃー誰も気づくまい!フォトカード』どうよ? どうよ? すごくない?」
「ネーミングセンスが最悪すぎるぞ、コラ」
「えー、俺はいいと思うんだけどなー」
ぶつぶつ言ったあとで、ロンシャンは監視カメラに近づいていったかと思うと、器用にもその場でジャンプをしてカメラのレンズにカードをかぶせるようにして設置する。しばらく経っても、カメラの異常を察知して人が駆けつけてくる気配はない。コロネロとロンシャンは裏口の扉に改めて近づいていった。
扉のドアノブの付近には数字キーの配列と、カードのスリット部分が設置されている。ロンシャンはスーツの懐側に手を入れたかと思うと、
「テレテテッテテー! じゃじゃーん、どこでも開いちゃう電子カード! バーイ、ボンゴレ科学技術部」
懐かしいアニメの決まり文句をもじったような台詞を小声で言って、黒いカードを一枚取り出した。ロンシャンは偽造カードをスリットにさし入れ、迷いなく暗証コードの数字八文字を迷いなく打ち込んだ。スリットに差し込まれたままのカードの角で点滅していた小さな四角い光が赤から青へと変化すると――、かちりとドアの鍵が開く。開いたドアの感触にロンシャンがご機嫌な様子でコロネロを振り返る。コロネロは頷いて、「気をつけろよ」と注意を促してからロンシャンにドアをあけるように目で指示をした。
八文字の暗証コードを覚えていられるだけの集中力がロンシャンにあったのかと、少しだけコロネロは彼への偏見を改めようかと思った――が、ドアを開いてビル内に侵入した彼が無様な声をあげながら、どべしゃと床に転んだので、偏見は偏見のままで定着させてしまうおうと思った。刹那、妙な異臭を感じたような気がして、コロネロは眉をひそめ――、
「なにして、ん……だ……」
呆れ顔のままで言いかけたコロネロは絶句する。
「あーちゃー」と言いながら立ち上がりかけたロンシャンも動きを止める。
彼は顔の前まで持ち上げた片手を見て、「うーわー」と間延びした声を上げた。
「ひっでー……」
彼がつまづいたのはスーツ姿の男の――死体だった。俯せに倒れているので死に顔は分からなかったが、男の側頭部が割れているのか、大量の血液と髄液のようなものが廊下一面に流れ出ている。男の身体の下や周囲には、持ち出そうとでもしたのか分厚いバインダーや、びっしりと細かい文字が並んだ紙が散乱していた。飛び散った血で汚れているものもあれば、真っ赤に染まってしまっているものもある。コロネロは持っていたナイフの柄を強く握りしめ、周囲を警戒したが、生きている人間はコロネロとロンシャンの二名しかいないようだった。
「ちょっとー、これ、ひどくない?」
ロンシャンが振り返り、右手をコロネロに向かって突き出す。ロンシャンの右手は真っ赤になっていた。落胆したように、がくりと頭を垂らしてから、ロンシャンは立ち上がった。汚れた手を見下ろした彼は、どうしようかと迷った末、死んでいる男の傍らに座り込むと、男の洋服で手を拭き始めた。
最低限の照明だけが点灯しているせいなのか、通路は薄暗い。そんな中でも、コロネロは己の目に映っている光景が異様であることが分かった。頭を割られた男が一人――、ではなかった。ロンシャンが手の血を拭っている男の死体よりも、奥の通路にも転々と倒れている人間の姿が確認できる。うめき声も聞こえてこないし、どの人影も動く様子はない。
気が付いてみれば、通路に充満している空気は澱んでいて、血生臭さに満ちていた。火薬の臭いが混じっていないので、戦場の臭いというよりは、殺人現場の臭いそのものだった。
あらかた手の汚れを拭き終えたのか、ロンシャンが立ち上がった。子供のように唇を突き出すようにして息をついた彼は、落ち込んだ顔でコロネロを見た。
「――これってどゆこと?」
「そりゃあ、こっちが聞きてーぞ、コラ。おまえ、いったい何をしてたんだ? こんなことになってんのに気づきもしなかったのか?」
「えーっと……、防音設備、完璧なんだねー」
「そういう問題か、コラ」
「だってさー、いったい、なんだってーのよ。……うえぇ、手ェ洗いたいんだけど……、しょんぼり」
神経質そうに爪の間に染みてしまった血液を睨み付けていたロンシャンは、両手を開いたり閉じたりしながら、奥へと視線を向ける。
「騒がれる心配はないみたいだし、奥行ってみよーよ」
「危険なんじゃねぇか?」
「大掃除してくれた人がいたら、お礼でも言えばいいんじゃないの?」
「そう簡単にいく訳ねぇだろ……、おいっ」
コロネロが言い終える前にロンシャンが無防備な様子で転々と死体が倒れている通路を進んでいく。慌ててコロネロも後を追った。
敵なのか。
味方なのかは分からないが――。
緊張が高まっていくのを感じながらも、コロネロは転々と死体が転がっている通路を奥へ進んでいった。なんてことのない普通の扉の手前に、裏口と同じ数字のテンキーが並んでいる端末が添えられている扉があった。
扉の前に立ったロンシャンの横顔には笑みは浮かんでいない。彼は滅多に見せることのない真剣な眼差しで扉を眺めたあと、裏口同様にカードを使用して扉のロックを解除した。カードをポケットにしまったロンシャンは、腰の後ろへ手を回すと、特殊警棒を取り出した。彼は右手に握った警棒を上から下へ向かって勢いよく振り下ろす。かしゃんと軽い音を立てて、鈍色の警棒が伸びた。
「そんじゃー、行くよ」
声音だけは明るく言って、ロンシャンは扉を開けてすぐに壁へ背中をつける。コロネロが扉の向こう側へ先に飛び込む。扉の先は階段になっており、非常灯のような微かな明かりが点々と階下への段差を照らし出している。倒れている人間はいなかった。だがしかし、微かに声のようなものが聞こえたような気がしてコロネロは耳を澄ます。
声はもう聞こえなかった。
鼻先にわずかに匂う火薬と血の香りが、今から行く先の危険を予感させる。コロネロはじっとりと手のひらに汗をかいていることを自覚する。冷静さを失ってしまっては生き残れない。感情をなくして理性だけで動かなければならない。そんな場所をコロネロは知っている。
「コロちゃん」
背後からロンシャンが怪訝そうな声を出す。コロネロは片手で「行くぞ」と階下を指し示し、大振りのサバイバルナイフを逆手に構えて、慎重に薄暗く長い階段を下りていく。
警報が鳴る様子もなかったし、見張りがいるようでもなかった。
階段が終わった先は円形のエントランスになっていた。無機質な銀色の床面には五名の男が倒れており――、死んでいた。どの死体も頭を割られている。容赦のない一撃が加えられたことは明らかだ。
ロンシャンは警棒を右手に握ったまま、床面に広がっている血だまりを見て双眸を厳しく細めた。軽口を言うことさえ忘れているような彼の様子が、コロネロはすこし新鮮だった。どんなにお調子者だとしても、『死』と向き合うときだけは真摯であるというだけで、その人物の深層が分かるものだ。
階段を降りた真っ正面の自動ドアが奇妙に歪んで半壊していて、砕けた破片が辺りに散らばっていた。ドアの奥から聞きづらいわめき声がかろうじて耳に届いた。ロンシャンを見てみれば、彼も声が聞こえたのだろう。コロネロと視線を合わせてしっかりと頷いた。
コロネロは左手をコートの下へ入れ、胸元のホルスターから拳銃を引き抜いた。少なくとも生きている人間がいることは確実になった。右手にナイフ、左手に拳銃を握って、コロネロは短く息を吸って吐いた。
「トマゾ。油断するな」
「ラジャー」
片目をつむてロンシャンが応じるのを横目に、コロネロは物音をたてないようにゆっくりと半壊しているドアをくぐりぬけた。まっすぐに続いている廊下は、相変わらず非常灯のようなわずかなグリーンライトが灯っているだけで薄暗い。細長く続いていた廊下をしばらく行くと、通路が途切れてひらけた空間が広がっているのが見えた。通路から見える狭い範囲にも、数人の人間が床に倒れ伏しているのが見えた。
室内からは見えない死角に立ったコロネロは壁に背中に深く息を吸い込んだ。コロネロとは反対側の壁に背中を預けているロンシャンの顔は無表情だった。普段の彼とはまるで別人のような雰囲気がロンシャンを覆っている。普段は愚か者を演じてるのか――と思わせるような変貌ぶりである。思わずコロネロがロンシャンの顔に視線を奪われていると、室内の様子をうかがっていたロンシャンの視線がコロネロを見た。彼はコロネロと目が合うと、ウィンクをして微笑みを浮かべて口角を持ち上げる。
行くよ。
声に出さずにロンシャンが言うのに頷いて、コロネロは拳銃を持った腕を前につきだして通路から室内へ飛び出した。わずかな時間差を置いてロンシャンも通路から部屋へ踏み込んだ。
室内は天井が高くとても広く、ホールと言ってもよかった。室内の壁際にそって短い階段で繋がった段差が設けられていて、あちこちに机が並べられ、そのどれもにパソコンがのっていた。ホールの奥の壁際には何の用途に使用するか分からない大きな機械がいくつも並んでいる場所があった。ある者は机にもたれるように倒れ、ある者は何かの書類を握ったままうつぶせに倒れている。死んでいるのか、それとも意識を失っているだけなのか判断はつかないが――、室内にはざっと確認しても十人以上の人間が倒れていた。
部屋の中央――、何かの実験のためなのか、それとも複数の人間に企画などを発表するための場所なのか、わずかに一段ほど高くなっている円形の舞台のうえに――、男が立っていた。
男は倒れている白衣の男の首を革靴の底で踏みつけていた。先が赤くそまったトンファーを握りしめている『彼』のスーツの袖からのぞくシャツは元は白かっただろうに、今は真っ赤に染まっていた。
「ひっ、ば?」
コロネロ同様に驚いたロンシャンが引きつったように声をあげる。
当たり前だ。
獄寺隼人からの情報では、『彼』は今回の事件からは手を引いて、違う仕事をしている――はずだった。『彼』の気まぐれはよくあることで、これまでも急に予定の仕事をキャンセルして、違う仕事を始めることがあった。だがしかし、『彼』がそういった行動に出た場合、そうした方が良い結果を生む場合が多い――というか、『彼』の選んだ仕事や方法のほうが良かった場合しか、なかった。
『彼』は――、
雲雀恭弥は、現れたコロネロとロンシャンを見ても驚きもしなかった。表情の無い顔でコロネロ達を見て「ひ、ば?」と呟いて首を傾げるだけで、雲雀は特に何もせずに倒れている男の首を踏みつけていた。
ぎこちなく流れる空気を壊したのはロンシャンの口笛だった。構えていた警棒を下ろしたロンシャンは、ホールの中央に立っている雲雀へ踊るような軽い足取りで近づいていく。
「イインチョ! ワオワオ! なにしてんのー、こんなとこで!」
コロネロはロンシャンの後を歩いてついていった。雲雀の目がロンシャンを見て、コロネロを見る。ぴくりとも表情は動かない。まるで日本人形のように、流麗な目元には感情はなかった。
「君達の方こそ、何をしているの?」
「俺達はツナちゃんを襲撃した関係者がここにいるって情報があったから潜入しに来たのよ。そしたらイインチョが居たってわけ。イインチョはなにしてんの?」
「見て分からないの? 群れてる奴らを咬み殺してるんだ」
「へーへー、群れてる奴らを咬み殺してるんだーって! そんなんで納得するわけないっしょ! 俺の出番は!? 俺の見せ場は!? どこ、どこ、どこなのよ!」
大げさな身振りで落胆を示し始めるロンシャンの態度にコロネロは少し動揺した。考えてみれば、雲雀とロンシャンの相性は最悪だ。どちらも人の話を聞かないところは一緒でも、性格が絶望的に正反対すぎる。たった一人で訳の分からない人間二人の相手をするとなると面倒なことになることは簡単に予測できる。コロネロの脳裏にラルの姿が浮かんだが、彼女と彼らの相性も悪い。落胆が肩にのしかかってくるのを感じながら、コロネロはナイフをホルスターにしまい、左手に持っていた拳銃を右手に持ち直して口を開く。
「コラ。落ち着け、トマゾ」
「これが落ち着いていられるかっての!」
地団駄を踏むようにして暴れながら、ロンシャンは警棒を握っていない左手で拳を作って嘆きだした。
「くそう! 格好良く敵地を制圧して、あわよくばツナちゃんに「ロンシャンてば、すごい! 格好いい!」って言ってもらえたりしちゃうところだったのに! なんてこと!?」
コロネロはぞわっとした悪寒を感じ、反射的にロンシャンの服を掴んで引っ張った。案の定、雲雀が振り上げたトンファーの先が、元はロンシャンの頭があった場所をすごい勢いで過ぎていった。ひぅん、と空を裂いたトンファーの動きに怯えたようにロンシャンは口を閉じ、きゅうに大人しくなった。
「うるさい」
冷淡な目つきでロンシャンを睨み付けて雲雀が言う。
ロンシャンはへなへなとその場にしゃがみ込んで、小さな声でなにやらぶつぶつと言い始める。ちらりとロンシャンを見たあとで、コロネロは雲雀へ視線を戻した。雲雀はコロネロの視線を受けると、わずかに顔を左へ傾ける。
「なに?」
「雲雀……、おまえ、いつ、侵入したんだ?」
「一時間くらい前かな」
「は? そのころには、うちの連中が包囲してたはずなんですけどぉ?」
しゃがみこんだままでロンシャンが問うと、雲雀は唇に意地悪そうな笑みをのせた。
「北側の非常口から入ったんだ。なんか、うるさいのがいたから黙らせておいたけど」
「ちょっとおおお! うちのファミリィになんてことしてくれてんのよ! イインチョ!」
バネ仕掛けのように飛び上がって雲雀につかみかかろうとしたロンシャンの服を掴んで、コロネロは強く引いた。「うぐぇ」とうめき声をあげながらロンシャンは後ろへよろめき、コロネロの隣に並ぶ。恨めしそうに半眼となったロンシャンは子供のように唇をつきだしてコロネロを睨んだ。
「トマゾ。ちょっと黙っててくれ。話が進まない」
「なんだよー、コロちゃあーん」
「撃たれたいか?」
「すんません」
コロネロに銃口を突きつけられたロンシャンは両手を顔の横に持ち上げて口を閉じた。銃口をロンシャンから外して床へ向け、コロネロは視線を雲雀へ戻す。彼は、返り血で汚れたスーツの袖を気にするように眼前へ持ち上げていた。腕ごしにコロネロの視線と視線を交えた雲雀は、腕を下ろしてコロネロのことを見下ろした。成長途中のコロネロから見れば、雲雀のほうがまだわずかに背が高い。
「雲雀、ここは当たりだったのか? それともハズレだったのか?」
「僕が意味のない事すると思うの?」
馬鹿にするなとでも言いたげに嘆息をした雲雀は、双眸を細めて口角を持ち上げる。
「――当たりだったわけだな」
「はぁん。よく分かるねえ、コロちゃん」
「長いつき合いになるとな。嫌でも分かっちまうんだぞ。コラ」
コロネロとロンシャンのやりとりを聞いていた雲雀は、微笑するのをやめて普段どおりの無感情な顔になると、ずっと首筋を踏みつけていた男を冷酷に見下ろした。
「時間を無駄にするのは嫌いなんだ。――ねえ、青い鳥の居場所を教えてくれない?」
言いながら、雲雀は男の首を踏みつけている足に力をこめる。男は苦しげに唇を動かし、みるみるうちに目を見開いていく。持ち上げられた男の両手が雲雀の足を掴むも、すでにダメージを受けているのか、ろくな抵抗になっていなかった。
「僕、気が短いってよく言われるんだ。――だから、早く、答えて……?」
雲雀の言葉に男が首を縦に振る。それは痙攣しているだけのようにも見えたが――、雲雀は男の首から足をどかした。盛大に咳き込みながら男は床のうえを転げて、のど元を両手で押さえて身体を震わせながら呼吸をし始める。
コロネロは隣に立っていたロンシャンを見る。彼は表面上は無表情を保っているようだったが、その裏に隠れた「雲雀への恐怖」が透けて見えた。コロネロの視線に気がついた彼は、唇の片側だけを持ち上げて、反対の目を細めた。
雲雀が行った脅しくらいではコロネロは驚いたりしないし、恐ろしいとも思わなかった。もっと酷い脅しや拷問のやり方をコロネロは知っていたし、実際に目にした事もあった。ロンシャンもまだドンとしては年若い。綱吉同様に、マフィアには不向きな性格といえる彼もまた、綱吉と同じ悩みや葛藤を抱えているのかも知れなかった。
ようやく普通に呼吸が出来るようになった男は、床のうえに座り込むと、怯えた目で雲雀を見上げた。次にコロネロとロンシャンの顔と手元を見て、彼はすぐに雲雀へ視線を戻す。
「『あいつら』のところへ連れていけば、殺さないでくれるか?」
雲雀はその場にまったく不似合いな優しい顔をして、血にまみれたトンファーを身体の前に構えた。
「君が誠実な人間ならば、死ぬのはもっと先になるんじゃないのかな?」
|
|
××××× |
|
片足を引きずるように歩きながら歩く男のすぐ後に雲雀が続き、ロンシャンとコロネロがそのあとに続いて歩いていた。
ホールになっていた部屋の奥にあったドアの端末を男が操作して開き、現れた廊下を四人は歩いていた。
雲雀は右手にトンファーを握りしめ、ときおりリズムをとるようにくるりとトンファーの切っ先を回した。そのたびに男がびくりとするので、反射的にロンシャンも同じように肩を揺らしてしまう。背後でコロネロが苦笑するような気配があったが、ロンシャンは振り向かずに前を向いていた。
「妙なことをしたら頭蓋骨を割るから。すぐに死ねないから、あまりおすすめしない死に方だから気をつけてね」
「イインチョ、ぐろい、ぐろすぎる」
低く呟いたロンシャンの声を聞きつけたのか、雲雀が妙に機嫌の良さそうな顔でトンファーを握っている右手を持ち上げた。ぞわりとした悪寒がロンシャンの背筋を駆け上っていく。
「君の頭蓋骨で試してみてもいいけど?」
「ノーッ! ノーサンキュー!」
ロンシャンのことを鼻で笑い、雲雀は持ち上げた腕を下げた。
「だいたい。なんで君がうちのことでうろついてるわけ?」
「だいたい。なんでイインチョがここにいるわけよ?」
ほとんど同じタイミングで二人の言葉は重なった。雲雀が何か言うかと思って間をあけてみたが、彼が何も言わないので仕方なくロンシャンの方から口を開く。
「ゴクちゃんが言うには、イインチョ、ツナちゃんのこと殴って戦線離脱したんじゃなかったわけ?」
「僕は僕がしたいようにするだけさ」
「あっ、そう……。こんなに頑張ってる俺っちの出番はなんですか、これで終わりってかー? ひどいよなあ、イインチョ、美味しいとこもってっちゃうんだもんなー」
「ぶつぶつうるさい。殴るよ」
「殴らないでちょーだいよ! 会話、会話しよーよ、イインチョ! トーク、トゥー、ミー!」
「トマゾ、すこし黙ってろ。本気で苛々してくる」
背後から不機嫌そうなコロネロの声音が突きつけられ、ロンシャンはがっくりと肩を落として小声で呟いた。
「……コロちゃんも冷たいし、イインチョは極寒だし……。あーもう、ツナちゃん、俺、ツナちゃんにむしょうに会いたいよ……、マイ・ベスト・フレンド!」
ロンシャンが祈るように両手を組んで歩きながら目を閉じるふりをすると、
「噛み殺すよ?」
「頭いてえ」
雲雀の冷たい声とコロネロの荒々しい声が重なるように前と後ろから聞こえてきた。細長く息を吐いてロンシャンは目を開いて組んでいた両手を下ろす。
四人は一列になって黙々と歩く。
廊下の左右には数字の端末が埋め込まれたドアが数メートルおきに点在していた。おそらくは小規模な研究部屋が設けられているのかもしれなかった。似たような研究施設をトマゾも保有していたし、ドンとしてロンシャンも施設へ視察に行くことも多々ある。研究施設というものは、やはりどれも同じような構造なんだなあとロンシャンがぼうっと考えていると、ふいに前を歩いていた雲雀が立ち止まる。あやうく衝突しそうになったロンシャンが息を呑みこみつつ立ち止まると、雲雀が肩越しに少しだけロンシャンを振り返った。彼は何も言わずにすぐ前を向き、「ここ?」と男に問いかけた。慌ててロンシャンは男の様子を見るために少し身を乗り出した。
男は、雲雀がトンファーの先で指し示した左側のドアを横目に見ながら何度も頷く。
「キーワードは?」
男は八桁の数字を言った。
雲雀はなめらかな口調で八桁の数字を間違いなく繰り返した。男は震えるように何度も頷いた。挙動不審な様子で視線を彷徨わせながら男は引きつった顔で雲雀のことを媚びるように見た。
「こ、これで――、いいんだろ?」
「うん。これでいい。――ありがとう」
無感情なままに礼を言った雲雀の右腕が素早く動き、男の後頭部へトンファーを叩き付けた。男は悲鳴をあげる間もなく壁へ前のめりに衝突して、ずるずると床の上に倒れていった。
「イインチョ……」
呻くように言ったロンシャンの声音など聞こえなかったように、雲雀は端末のキーを叩いた。電子ロックの解除音がして――、雲雀がエンターキーを押すとドアがスライドした。
室内はロンシャンが考えていたよりも奥行きがあって広さがあった。幅は普通の部屋ほどしかなかったが奥行きが十メートル以上ありそうだった。部屋の奥にはたくさんのバインダーが並べられた棚や大きな工具が整理された棚がずらりと並んだスペース、そして広く大きなステンレス製のテーブルがあり、その上には様々な器具やパーツが雑多に置かれていた。そんな煩雑としたスペースの手前、どこにでもありそうな円形のテーブルのうえに五台のデスクトップパソコンが並べられ、周辺機器へと縦横無尽にケーブルが伸びている。生物を拒絶するような空間だとロンシャンは思った。
デスクトップパソコンの並びの向こう側に誰かが座っているのが見えた。雲雀は颯爽と室内に足を踏み入れていく。ロンシャンとコロネロもあとに続いた。
「ミスター・フィリアーノ?」
ロンシャンの声に反応するように、パソコンの向こう側から白衣の――女性が現れた。
年はロンシャンと変わらないか、もしかしたら年下とも思えるくらいに若い。事前に入手した情報では、ボヴィーノ秘蔵の十年バズーカの初期設計に関わっていたフィリアーノは齢七十を超す老人のはずだ。
「フィリアーノの、娘? いや、孫娘ってところか?」
コロネロの独り言のような声がロンシャンの耳にかろうじて届く。
ミス・フィリアーノは、黒いタイトなスカートに白いブラウス、そのうえに白衣を羽織っていた。赤茶色のウェイブした髪を頭の上でひとつにまとめあげていて、驚いて後退した彼女の動作にあわせて、結われた髪の毛先がふわりと揺れる。よく見れば、彼女の顔の右側には殴られたのかアザが出来、唇の端が切れたのか、かさぶたのようなものが出来ているのが見えた。女を殴る奴は死ねばいいのに――とロンシャンは内心で彼女を殴った人間を呪った。
「あ、あなた、たち、は?」
「ボンゴレに害があると困る人間達、ってところかな」
ロンシャンの言葉にミス・フィリアーノは大きく緑色の目を見開いた。
「ボヴィーノのオメルタを破ってバズーカを作ったのは君たち?」
雲雀の問いかけにミス・フィリアーノの形相が見る間に怒りのものへと変化する。
「祖父はオメルタを破ってない!」
吠えるように言った彼女は、パソコンがのっている机に手を伸ばしてた。彼女はカッターナイフを握りしめて、身体の前につきだした。刹那、雲雀が攻撃の態勢に入るのではないかとロンシャンは彼の動きに細心の注意をはらった。彼がどんな行動をするかは予測はつかない。相手が女だから殴ることはない――なんてことは雲雀には通用しない。彼は殴りたい時に殴るし、やりたいことを我慢するような人間ではない。
「じゃあ、なんで十年バズーカが作れたんだ?」
コロネロが落ち着いた様子で問いかける。彼もまた、右手に拳銃を握りしめている。だがしかし、コロネロは雲雀と違う。注意すべきはミス・フィリアーノと雲雀の動きだけだ。それならば、戦闘に特化していないロンシャンの集中力でどうにか見定めることができるだろう。ミス・フィリアーノは、カッターナイフを握った右手を震わせながらも、気丈な態度で一歩も後ろへ退かなかった。
「私と祖父は、あいつらが持ってきた古い設計図を見て、バズーカを作っただけよ! 祖父は元はボヴィーノの研究施設にいたけど、そのときもバズーカの設計の初期段階に関わってただけで開発には携わってない。――未完成の設計図を持ち出した人間がいなきゃ、私達だってこんな、……こんな酷い目にあったりしなかった!!」
「君達が作ったバズーカのおかげで、いろいろと厄介なことになってるんだけど、どう責任とってくれるの?」
責任イコール死。
そんな図式がロンシャンの頭のなかに浮かんだのと同様に、ミス・フィリアーノの思考にも思いついたようんで、彼女は悔しげに唇を引き結んだ。今にも左目の縁から涙がこぼれ落ちそうになっているのが、離れているロンシャンの目にも分かる。
短く息を吸って、ロンシャンは両腕を広げながら雲雀とミス・フィリアーノの間に飛び出した。背面のミス・フィリアーノに背中を刺されないかと思いつつも、前方にいる雲雀をに向かってロンシャンは片手を突き出す。
「ちょーっと、イインチョってば、威嚇しちゃだめでしょーが。女の子には優しくやさしーく!」
雲雀は表情を変えなかったし、構えた腕も下ろさなかった。ミス・フィリアーノと共に雲雀に殴られる可能性が上昇したが、いまはもうロンシャンに引き下がるという選択肢はない。その場で回れ右をして、ミス・フィリアーノの方を向く。彼女はロンシャンの動きに驚いたようにびくっと大きく肩を揺らしたが、カッターナイフで襲いかかってくるようなことはなかった。
「えっとー。オレ、トマゾでドンやってる、ロンシャンって言うの。よろしくねえ。――丸腰だから、ね? それ、刺さないでね? オレ、痛いの苦手なのよ。ねえ、君、名前は?」
ミス・フィリアーノは唇を開きかけたが、思い直したようにまたきゅっと唇を結んでしまう。
かつり。
かつり。
と、硬いものがぶつかり合うような小さな音が近づいてくる。
ミス・フィリアーノの視線が背後へと動きかけ、すぐにロンシャンへと戻った。明らかにつよい動揺に惑うように、彼女の視線が彷徨い始める。かすかな物音が近づいてくる気配を雲雀もコロネロも察知したのだろう。彼らが身構えるような気配を背中で感じながら、ロンシャンは出来るだけ優しげにミス・フィリアーノへと笑いかけた。
「ミス・フィリアーノ。親父さんと君が作ったバズーカで、俺の大事な大事な友達が大変な目にあってるんだ。どうやったら入れ替わりを元に戻せるのか、君は知ってる?」
「私、は――」
「もう一度、同じバズーカで本人を撃てばいい」
明朗な男性の声がバインダーや器具類が並べられた棚の合間から聞こえてきた。
「あいつらはそれを知らない。知っているのは私と、この子だけだ……」
かつり、かつりという音と共に、棚の影から姿を現したのは、白衣を着た老人だった。赤茶色のうすい髪、丸いレンズの眼鏡、――ミス・フィリアーノとよく似た面差しの老人は、右手で杖をつきながらロンシャン達のほうへ近寄ってくる。どうやら片足が不自由のようで、歩き方がぎこちなかった。
「お祖父ちゃん!」
カッターナイフを机のうえへ放り投げ、ミス・フィリアーノが近づいてきたフィリアーノに抱きつくようにして飛びついた。フィリアーノは、ミス・フィリアーノの身体を片腕で抱きしめながら苦笑いを浮かべる。
「どうしてすぐに私を呼ばない?」
「お祖父ちゃんを危ない目に遭わせるわけにはいかないわ」
口ごもるミス・フィリアーノの背中を何度か撫でてから、フィリアーノはロンシャン達を見た。丸眼鏡のしたの双眸は理知的で、データとして知っている彼の実年齢よりもずっと若い印象がした。
「すまないね。レリッタに悪気はないんだ、非礼は許してやってくれ。君達は私に用事があるのだろう? 私はちょうど奥の部屋で仮眠をしていたところだったんだ。最近は起きている時間が短くてね。こまめに仮眠をせねば、頭がろくに動いてくれない。――君達は? ボンゴレの人達なのかい?」
「そうだ」
コロネロが肯定する。
フィリアーノは、ミス・フィリアーノ――レリッタに自分から離れるように言って優しく笑いかけた。レリッタは頷いて、フィリアーノから離れ、彼の近くに立った。
深く息を吐き、両手で杖をついたフィリアーノは厳しい面もちでロンシャン達を見据え、話し出す。
「入れ替わったあとで、時空を歪めて固定することは永遠には続かない。早く撃たないと、入れ替わった人物の存在自体が消滅する恐れがある」
「なにそれ! ツナちゃんが消えちゃうってこと!?」
「手遅れにならないうちに彼をバズーカで撃って、乱れた時間軸を正さなくてはならない」
重々しく息を吐き出して、フィリアーノはロンシャン達を見ながら話を続けた。
「あいつらは、現在を生きるボンゴレを、まだ幼い子供時代のボンゴレとを入れ替えて、殺してしまおうと計画していた。実際は、現代のボンゴレと十歳のボンゴレとを入れ替える計画だったが――、私が故意に時代設定に細工をした。子供の彼を惨殺することに荷担はしたくない」
「だから、ツナは九年と半年前なんていう中途半端な時代と入れ替わることになったのか?」
「せめて十八を過ぎたボンゴレならば……、あるいは――困難を乗り越えてくれるやもしれぬと――」
「困難?」
雲雀の硬質な声音が室内に凛として響く。
「あなたは自分の行動を弁護しているだけだ。あなたがもたらした困難とやらは、必ず過去の沢田綱吉になんらかの影響を及ぼすだろう」
「責任の所在が明らかなことは、私自身がよく理解している。ドン・ボンゴレの抹殺という計画に荷担した事を否定するつもりはない。覚悟はもう出来ている」
フィリアーノは雲雀の視線から目を逸らさなかった。
「ふぅん。そう」
雲雀は急に興味を失ったようにフィリアーノから視線を外し、あろうことかあくびをした。自由な行動を貫く彼の態度に面食らったように、その場にいた全員が雲雀に注目をした。
「雲雀……」
呆れたようにコロネロが雲雀の名を呼んだが、彼は聞こえないかのように勝手に部屋の中を物色するようにゆっくりと歩き出した。短い溜息をついたコロネロは「あいつのことは放っておいてくれ」と言い、フィリアーノに話の続きをするように片手を振った。
フィリアーノは軽い咳払いをしてから、気を取り直したかのように話を再開した。
「私は、ドン・ボンゴレが誰を愛していようとも構わない。彼はとても良い人間だ。――私はずっとこの世界で生きてきた。死んだほうがよかったと思うこともあったし、死んだ方がよかった場面に何度も出くわしてきた……。そんな世界で生きてきた私にとってはドン・ボンゴレは異端児だったよ。あれはとてもいい青年だ。長いこと、暗闇にいた私のような人間には、まぶしいくらいの逸材だ……。たとえボンゴレの血筋が絶えようとも、彼の意志だけはきっと彼の死後も必ず残るだろう」
沢田綱吉の意志、そして彼が行ったすべてのこと――。
たとえ子孫を、血を残せなかったとしても、沢田綱吉が生きた事はなくなったりはしない。血脈もファミリィの歴史も大切なものだろう。そして同じく、人として誰かを愛することも大切なことだ。世界には様々な大切なことがある。それは人によって様々で、誰かが大切なものを守るために、誰かが傷つけられることは――、よくあることだ。
わずかに眉を寄せていたロンシャンを見て、フィリアーノは理知的な瞳をやわらかく細め、何度か頷いた。ロンシャンの考えていたことを察しての頷きなのか、それとも先ほど己が言った言葉に満足して首肯しているのか――ロンシャンには分からなかったが、彼が綱吉の敵でないことは分かったような気がした。
「バズーカは奥の保管庫にある。奴らが持っているのは、この子がすり替えた偽のバズーカだ。撃ったとしても、何の変化もないカラの弾丸が爆発するだけの、手品の道具みたいなものだ。あんなクズ達に、これ以上バズーカで好き放題させるわけにはいかない」
深呼吸をしたフィリアーノは、己の仕事はすべて終えたというように、朗らかな顔で笑った。
「さあ、私を殺すんだろう? 苦しみたくはない。一撃でお願いしたい」
「お祖父ちゃん!」
フィリアーノの身体にレリッタは飛びつく。しかし、フィリアーノはレリッタを見ず、まっすぐに雲雀を見ていた。
「この子は私に命じられて仕方なく従っていただけだ。悪いのは私だ。私ひとりの生命をもって、購いとしてくれ」
「いや! 私も殺して! お祖父ちゃんだけが悪い訳じゃない! 私もバズーカの制作に関与したわ!」
「レリッタ!」
「一人きりで置いていかれるのは嫌! お願い! 一緒に殺して!」
悲鳴のように叫んで、レリッタがフィリアーノの身体の前で両腕を広げる。ロンシャンは視線だけで雲雀の動きに注意していた。ロンシャンかコロネロの二人だけだとしたら、きっとフィリアーノ達のやりとりを見てしまっては、殺すことにためらいを感じてしまうだろう。そういった躊躇いや迷いが己の生命を危険にさらすと分かっていても、同情と憐憫だけはどうしようもない。
だがしかし、雲雀は違う。
ロンシャンは雲雀が躊躇するところを見たことがない。
フィリアーノとレリッタがオメルタを破ったのならば制裁を与えるべきだ。それが掟、それが秩序だ。それはロンシャンも嫌になるほど理解している。腹の辺りがむかむかとして吐き気がこみあげてきて、ロンシャンは無意識に舌打ちをした。
「そのぐらいにしてくれないかな」
冷静すぎるほど、落ち着いた雲雀の声が、混乱しかけている室内に凛とした強さで響いた。泣き出していたレリッタと、彼女のことをかばおうとしていたフィリアーノ、そして雲雀の動向に注意していたロンシャンとコロネロの動きが制止する。
雲雀はトンファーを握った両手を身体の脇に下ろし、面白くなさそうな顔で室内の面々を見回し――、レリッタに視線をあわせると、右目を細めた。
「バズーカ。あるんでしょう? だったら今すぐ、それをここに持ってきて」
レリッタが迷うようにフィリアーノの顔を涙目のままで見あげた。
フィリアーノはレリッタの肩を優しく叩き、微笑みながら頷く。
「レリッタ」
「分かった」
頷いたレリッタが走り出し、フィリアーノが現れた棚と棚に挟まれた細い通路に姿を消す。
とりあえず、雲雀の凶行がなかったことへ安堵の息を吐きつつ、ロンシャンは両肩を落とした。すると、雲雀が急にロンシャンに近づいてくる。意味もなく殴られるのかと身構える前に、雲雀が口を開いた。
「バズーカさえ手に入れば僕はそれでいい。――あとは、ロンシャン、君に任せるよ」
「うええ? 俺っちに、ってどゆことよ! イインチョの場合、ここは有無を言わさずに二人とも撲殺!かと思って、止めるタイミングをうかがっていた俺っちの思惑はどーなるのよ!」
「そんなの僕は知らない」
あっさりと言ってのけ、雲雀はぽかんとするロンシャンを放って話を続ける。
「フィリアーノ親子がボヴィーノのオメルタを破ったかどうかは曖昧だろ? 調べてみれば、ボヴィーノの古い資料を横流しした、本当にオメルタを破った人間が出てくるかもしれない」
「こいつらに罪はないとはいいきれないが、それでも情状酌量の余地はあるってことか、コラ」
コロネロが苦笑いを浮かべ、目線でフィリアーノを指す。
わずかながら皮肉ぽい笑みを浮かべ、雲雀があごをひく。
「お人好しな君達にこそ、お似合いの仕事だろ」
「で、てめーは何をするつもりだ?」
「素晴らしいカーテンフォールのために、あと一仕事しなきゃいけないみたいだからね。僕は忙しいんだ。君らがボヴィーノにうまく交渉できるとは思えないけど頑張ってみればいいんじゃないの? 徒労に終わらないようにせいぜい努力しなよ」
軽い足音をたててレリッタが棚と棚の間から小走りに現れた。両腕には白いテーブルクロスのような布地にくるまれたバズーカを重そうに抱えている。彼女は雲雀の前まで行くと、包みをおずおずと差し出した。トンファーを素早くホルダーへ収納した雲雀は、レリッタの手から包みを片手で受け取ると、双眸を細めて機嫌よさそうに頷いた。
「ありがとう」
微笑した雲雀の顔にレリッタが目を奪われたように見とれる。普段、人形のように表情を変えない雲雀だったが、少しでもやわらいだ表情を浮かべると劇的な程に印象が変わる。波が引くように笑みをひそめた雲雀は、ロンシャンとコロネロを一瞥すると、バズーカを持っていないほうの手をかるく挙げて左右に振りながら二人に背を向けた。
「じゃあね」
入室したドアから雲雀が出ていく。
遠ざかっていく足音を聞きながら、ロンシャンはゆっくりと息を吐いた。
「……イインチョ、ツナちゃんの居場所知ってんのかねえ?」
「不気味な奴だな、相変わらず」
コロネロがロンシャンに近づきながら拳銃をホルスターにしまう。レリッタはフィリアーノに寄り添うように立ち、怯えたような目でロンシャン達を見ている。ロンシャンは反射的にレリッタに微笑みをかける。彼女はぎこちない顔で笑おうとして失敗して、落ち込んだように顔を伏せた。
「で、どうするんだ? トマゾ」
「どーするって……。ツナちゃんのことは、イインチョに任せておけばいいんじゃないの?」
「まあ、……そうだろうな」
「そうそう。だから、コロちゃんと俺っちがすることって言ったら、もちろん、決まってんでしょーよ」
「何をするつもりだ?」
苦笑したコロネロが肩をすくめる横で、ロンシャンは両手を叩いた。突然の音に驚いたレリッタとフィリアーノが身体を揺らす。両手を広げ、ロンシャンはフィリアーノ達のほうへゆっくりと近づいていく。
「さあ、レリッタちゃん! ミスター・フィリアーノ! こんな暗い部屋を出て美味しい食事とかご一緒しましょーよ。話はそれから!」
「え、……どう、して?」
「まずは美味しいご飯で元気になってから、だよ。レリッタちゃん。あなた達二人の身柄は、俺、ドン・トマゾがしっかり、ちゃんと引き受けるから! 絶対にイヤな目にも苦しい目にもあわせないよ! そんなこと、ドン・ボンゴレだって望んじゃいないだろうしね!」
「ドン・トマゾ……」
小さな声で何かを言ったレリッタの背中を、フィリアーノがゆっくりと何度も撫でている。ロンシャンは片手を持ち上げて、うつむいているレリッタの肩に触れた。彼女は泣き笑いのような表情でロンシャンを見上げる。目の縁から涙が一筋こぼれ、顎先へと滑り落ちていった。
「ドン・トマゾ。――それではあなたの立場が」
「ミスター! 何か食べたいものがあったりする? それか、美味しいレストランの場所教えてくれれば、そこまで行っちゃうけど?」
フィリアーノの言葉を遮るように、ロンシャンが明るく言うと、彼は困ったように笑ってあごをひいた。
「ありがとう。ドン・トマゾ」
「やだなー。まだ感謝するには早いんじゃない? ねえ、コロちゃん」
背後にいるコロネロへ言葉を投げる。肩越しに振り返ると、彼は両手を腰にあて、胸を張るようにして立っていた。とても十代半ばの年齢の少年とも思えぬ雰囲気をまとい、コロネロは勝ち気な様子で笑みを浮かべる。
「ミスター。俺は元・アルコバレーノのコロネロだ。トマゾだけでなく、俺もきちんとあんたらの身柄について保証する立場に立つ。だから、不安にならないでいいぞ、コラ」
「ちょっとォ! コロちゃん! 俺だけじゃ不安だってかぁ?」
「……不安だろ、当たり前だ、コラ」
意地悪そうに片目を細めるコロネロをロンシャンは睨みつけた。レリッタが泣いた顔で笑い、フィリアーノが優しげに双眸を細めた。
ロンシャン達が生きている世界は暗く重く、
幾度と無く道を失いそうになるような世界だ。
救いたいと思った命も容赦なく消えていくような世界だ。
そんな世界にロンシャンはいる。
ロンシャンが愛する人達もいる。
だからロンシャンは笑う。
笑って、笑って、笑い飛ばす。
ろくでもない世界だとしても、絶対に諦めたりしないと、神様に向かって舌を出す。
なんとなく、懐かしい中学生時代の思い出がロンシャンの脳裏をすぎさっていった。騒がしい日々、懐かしい日々、愛すべき日々――。すべては今に、未来に繋がるための日々。
「トマゾ。なに、にやにやしてるんだ? コラ」
怪訝そうな顔でコロネロが眉を寄せる。
ロンシャンは声を立てて笑い、たてた人差し指を口元に添え、片目をつむった。
「きっと、すべて、うまくいくさ! だって、みんな、大好きなツナちゃんのために動いてんだもん、うまくいかないはずはないって!」
コロネロが苦笑しながら「まぁな」と呟いて肩を落とすように息をつく。フィリアーノの達に向かって、ロンシャンは礼儀正しい執事がするように、身体の前に腕を添えて優雅に一礼をする。そして顔を上げ、にっこりと笑った。
「さあ、美味しいご飯を食べて、いっぱい笑いましょう!」
|
|
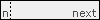 |