|
「ただいま。待たせちゃって、ごめんなさい」
待合い室に小走りで戻った綱吉は、ドアを開けて入室しながら口を開く。ソファに足を組んで座っていたディーノと、その向かい側に座っていたスカルが反応するように開いたドアへ顔を向ける。クローム・髑髏がいないことに気が付いた綱吉がそのことを言及するまえに、ディーノが口を開いた。
「あいつと話はできたのか?」
「ええ。仲直りしてきました」
綱吉の言い方がおかしかったのか、ディーノはクスッと笑って優しい顔をした。
「仲直り、か。……具合は大丈夫そうだったか?」
「具合ですか? 憎まれ口たたけるような感じだったんで、ディーノさん、気にしなくていいと思いますよ」
「おー、なんだか辛辣だなぁ、ツナ」
苦笑しながら呟いて、ディーノは落ち込んだように背中を丸める。彼の近くへ近寄り、綱吉はディーノの肩に手をのせた。
「オレが言いたいことはですね……。ディーノさんが考えているよりも、リボーンはディーノさんのことを怒ったりはしてないってことですよ」
「そっか。……まあ、うん……。あとで、きちんとあいつと会って話をするよ」
「それで、あのう……、クロームはどこに?」
「獄寺に呼び出されていった」
スカルが簡潔に言った言葉を受け取るように、ディーノが続けて言う。
「たしか、了平に獄寺が普段やってる事務処理をやらせるらしくって、それの補佐にって――」
「……え? 了平さんに、獄寺くんがやってる事務処理を任せるんですか?」
「ベッドでじっとしていられん!とか言って暴れようとするから、苦肉の策で仕事まわしたらしいぞ」
「それは……、えらい賭けですね。了平さんって事務処理とか、なんか苦手そうなイメージがあるんですけど……」
「了平だけだと不安だからってクロームをつけたらしい。クロームの代わりに、誰かをおまえの護衛にすぐに寄越すって言ってたから、誰かが来るだろ。さて――!」
ぱん、と両手で太股を叩いたディーノは勢いよくソファから立ち上がって、両手を頭上に持ち上げて背筋を伸ばした。
「ツナの元気な顔もみれたし、リボーンも無事だって分かったしな。今度は俺が俺のファミリィを安心させる番だな」
「そうしてください。いろいろありがとうございました」
頭を下げた綱吉の肩を叩いて、ディーノはソファから立ち上がったスカルを見て片目を閉じる。
「スカル。ツナのこと頼むな」
「ああ。任せておけ」
片手を上げてディーノのウィンクに答え、スカルは頷いた。スカルの態度を確認してからディーノはまるで幼子の頭を撫でるように、わしわしと綱吉の頭を片手でなで回して、にっこりと笑った。誰もが見とれてしまうような美貌に惜しげもなく、愛情が込められた微笑を浮かべて、ディーノはわずかに顔を右へ傾ける。
「何かあったら連絡くれよ? 俺はいつだって、おまえのヒーローになりてぇなって思ってんだからさ」
綱吉はくしゃくしゃになった前髪ごしにディーノを眩しげに見上げる。マフィアという世界で綱吉よりも長く生きている彼は、まるで十年近く前のディーノと同じように、優しく優しく綱吉に笑いかけてくれる。きっと彼自身にも辛く悲しい事件は降り注いでいるに違いないというのに、それでもそんな杞憂を一切感じさせないようにして、彼は生きている。まだまだ自分は未熟なんだろうなと思いながら、綱吉は彼を安心させるためだけににっこりと笑顔を浮かべた。
「なに言ってるんですか。ディーノさんはいつも、オレの憧れのヒーローですよ」
「お世辞でも嬉しいぜ」
にぃ、と笑ったかと思うと、ディーノは片手を振って室内から出ていった。
綱吉は近くに立っているスカルへ視線を向ける。彼はブルーブラックのスーツの上下、紺地に白い細いストライプのシャツをノーネクタイで着用している。年の頃はリボーンと同じくらいだとすると十代半ばくらいだったが、身長のせいかもう少しだけ年齢が上のような容姿に見えた。
彼の身長は綱吉と同じくらいだったので、顔を横に向けるとサングラスをかけているスカルの目線あたりに視線がゆく。サングラスのせいかスカルの視線がどこを見ているかは判別しにくかった。目元がサングラスで覆われているにしても、スカルの顔立ちが整っているような印象がするのは、形のよい鼻筋と唇、そして頬からあごへのラインがきれいな卵形の形をしているせいだろう。
「なんだよ?」
落ち着かない様子で視線を彷徨わせてスカルが呻くように言う。
「スカル、サングラスとか外さないの?」
「外さない」
「素顔、見たいなあ」
「見せものじゃない」
スカルのサングラスへ綱吉が指先を伸ばすと、彼はバッと後方へ飛び退いた。
「やめろっ」
黒い手袋をはめた両手を身体の前につきだし、警戒心をむきだしにしてスカルが叫ぶ。
「いいじゃない。へるものじゃないのに」
「オレの素顔なんて見てどうするんだ?」
「え。……かわいいのかなあと思って」
正直に綱吉が言うとスカルは小さな声で「おまえもそう言うのか、ちくしょう」と呻いて悔しそうに赤い顔で眉をしかめた。彼はわざとらしい咳払いをひとつして、綱吉のことを見た。
「どうするんだ、これから」
「うーん。それじゃあ、鳥籠に戻っても良いかな?」
「うん? わざわざ、また閉じこもるつもりか?」
「違うよ。あそこに、いろんな資料をおいてきちゃってるし、まだ読み途中の報告書とかあったし……。なにかまだ、気が付いてない箇所があるかもしれないでしょう?」
「そういうことか。分かった。行くぞ」
前を行くスカルが開いたドアをくぐり、綱吉は廊下へ出た。
しばらく歩いていくと、屋敷と医療棟を繋ぐ渡り廊下へと辿り着く。渡り廊下はちょうど綱吉の腰の高さあたりから硝子張りになっていて、その向こうには朝日を受けてきらきらとみずみずしい庭園の緑が広がっている。
「――うっ、わッ」」
よそ見をしていたせいか、綱吉は何もないところで躓いて転びかけた。動きの気配でそのことに気が付いたスカルが振り返り、呆れるように息をついて体勢を立て直す綱吉を見る。
「足下くらいちゃんと見て歩け」
「ごめんなさい」
綱吉が追いつくのを待ってからスカルは歩き出した。長い渡り廊下を歩き終え、わずかな階段を上った場所にある扉をスカルが開く。先に綱吉を通らせてからスカルも続いて屋敷の中に入る。毛足の長いふかりとした絨毯を靴底で踏みしめて、綱吉とスカルは肩を並べるようにして歩いた。
廊下を歩いて二階へ続く、ゆるくカーブした階段を上がっていく。まるで高級なホテルのような装飾に彩られた屋敷の様子に綱吉はまだ慣れていなくて、黙ったままあちこちを無意識に見回してしまう。掃除が行き届いた絨毯を踏みしめながら、綱吉は隣を歩いているスカルへと視線を移す。
スカルは綱吉の視線を受け取ると、わずかに首をかたむけた。
「ねえ、スカル。リボーンと話すことってある?」
「あるにはあるが。そんなに親しい訳じゃないぞ」
ふぅん。
と相づちを打ってから、綱吉は次の質問をした。
「たしかスカルのいるカルカッサって、たしか敵対ファミリィじゃなかったっけ?」
「昔はそうだったんだけどな。最近は、敵対っていうより、持ちつ持たれつ、な感じだな」
「へえ。それって、スカルのおかげだったりするのかな?」
「うん?」
「スカルが、ボンゴレとカルカッサのパイプ役なんだよね? おまえ、まだ小さいのに、すごいねえ」
感嘆するように綱吉が言うと、スカルがぴたりと足を止める。道順でも間違えたのかと綱吉が足を止めるが、綱吉の記憶に残っている道順どおりならば進む方向に間違いはない。それに曲がり角も階段もない場所なのだ。立ち止まる必要性はない。
「スカル?」
すこし背中を丸めてスカルの顔を覗き見ると、彼はむっすりとした顔をしていた。唇をへの字に曲げた様子はどこか、幼いころのランボと似通っていて、綱吉は思わず微笑ましい気持ちが身体の奥底から生まれるのを感じた。
綱吉が微笑むと、スカルはますます不機嫌そうな顔になったかと思うと、胸の前で両腕を組んで上目遣いに綱吉のことを睨み付けてきた。とっさに綱吉は姿勢を正して、スカルの言葉を待った。
「あのな。ボンゴレ」
「うん?」
「あんた、十八歳なんだろ? オレは十四だぞ。四歳しか変わらないのに、小さいとか言うな」
「あー……、ごめん。小さいは言い過ぎた。若いのに苦労してきたのか落ち着いてるなって、老成してるとか、言えばいいんだっけ? あれ?」
「言い方変えても、失礼だぞ、おまえ」
「うっ。すいません」
苦笑いで綱吉が謝罪すると、スカルはおおげさな態度で溜息をついて肩を落とす。小声で「ごめんね?」と続けると、彼は「もういい」と力なく言って首を振った。
唇を結んだスカルが、サングラスごしに綱吉と目を合わせる。瞬き三回分くらいの時間ほど綱吉と目を合わせていたスカルは、和んだかのように唇をほころばせた。目線が隠れていても、なんとなく「ああ、きっとサングラスを外すと整った顔をしてるんじゃないのかなあ」と思わせるような、魅力のあるやわらかい微笑がスカルの口元に浮かぶ。
「なんか目線が近い気がするな」
「そう?」
「変な感じがする。いつもオレがあんたのことを見上げていたからな」
「オレも変な感じがするよ。オレが知ってるスカルは、まだほんとうに小さかったし……、それにあんまり会える機会がなかったからなあ。おまえ、なかなか会いに来てくれないんだもの」
「そりゃあ、昔は敵同士だったんだしな。おいそれと、会いに行くはずないだろ」
懐かしむように言って、スカルが綱吉から目をそらす。横顔の、頬がわずかに赤らんでいるように見えた。
「ねえ、スカル――」
綱吉はスカルに顔を近づけ、サングラス越しに驚いたように見開かれた彼の瞳をジッと見つめた。
「室内でサングラスかけてると暗くないの? 見えてる?」
「急に近づくなっ」
悲鳴のような声を上げてスカルが後ろへひっくり返るような勢いで飛び退いた。スカルの機敏な動きに驚いている綱吉の視界に動く黒い塊が映る。綱吉の意識はスカルよりも黒い物体に引き寄せられる。
「こんちわー」
足音も気配すらも感じさせずに綱吉達に近づいてきたのは、ヴァリアー隊の制服に身を包んだひょろ長いシルエットの――、ベルフェゴールだった。ふわりふわりとした金糸の髪のうえに華奢なティアラをのせた彼は、踊るような足取りで近づいてくると、綱吉の側に来て立ち止まった。
「なにしてんの?」
「ベル、さん」
「さん、はいらないって言ってるじゃーん」
特徴的な笑い声をたてて、ベルが笑顔を浮かべる。ベルは長い前髪のせいで目元が隠れているため、彼の口元がチェシャネコのように三日月型になっていても、前髪に隠された両目に殺意と狂気が浮かんでいることがあってもおかしくないような相手だった。
ベルは綱吉よりもてのひら一つ分以上背が高い。痩せているというよりは痩せすぎた体型と色素の薄そうな白い肌が、不健康そうな雰囲気を醸し出している。綱吉もあまり筋肉が付かない体型をしているが、ベルはそれ以上にうすい身体をしているようだった。
猫のようにしなやかな細い身体は戦うには不向きのようにみえる。彼の身体のどこに『生来の暗殺者』としての資質が隠されているのだろうか、と思わずにはいられない雰囲気がベルにはあった。それでもベルが恐ろしい暗殺者で、恐ろしいほどの加害者であるということを、綱吉は知っている。
出会った十四歳のときから、十八歳という四年という年月の間に経験した事柄から、綱吉は知ってしまった。
ベルフェゴールが『真実の狂気』を抱えた人間なのだと思い知った事柄があった。それはいま思い出すだけでも気分が悪くなるような、そんな事件だった。
六道骸とはまた違ったベルの『狂気』を綱吉は本当に理解が出来なかった。おそらく、生涯、理解することは出来ないだろうと思った。
綱吉はベルの性格が嫌いではない。狂気性が薄れているベルは陽気で明るく、小さい男の子のように、いつになっても悪戯っ子のようなところがある。だから綱吉は彼のことが嫌いではない。
嫌いではないが、彼から感じる恐ろしさだけは、綱吉にはどうすることもできなかった。
「俺のことはベル、ベルでいいんだって! ねえ、ツナヨシ。あんまりつれないことするなよ。王子、かなしくなってきちゃうじゃん」
ベルはにっこりと笑いながら、綱吉の肩に片腕を回す。猫がすりよるように、綱吉の頭に頭をすりよせ、くすくすとベルが笑う。やわらかい金糸の髪が綱吉の頬にあたり、くすぐったかった。
「王子さ、ちょうど定期連絡しに来たら、ハヤトに掴まっちゃってさー。ツナヨシの護衛しに行けって言われてさぁ」
「え。そうなんだ……。それじゃあ、よろしくお願いします」
「もう、駄目だって。ツナヨシー」
「え?」
「敬語やめなよ。俺とツナヨシの仲じゃん。仲良くしよーぜ」
肩に回されていたベルの手がツナヨシの頬を包む。ひやりとしたベルの指先に頬を撫でられ、綱吉はびくりと身体を震わせてしまった。その様子を見たベルは、にやにやと笑いながら綱吉の身体に身体を密着させてくる。どきりどきりと心音が身体の内側から大きく響いてくるのを感じながら、綱吉はそうっと口の中に広がってる唾液を飲み込む。
ベルが敵でないことは確かだろうが、それでも彼への恐怖心だけはぬぐいきれない。何を言えばいいのか分からなくなった綱吉が唇をぱくぱくとさせていると、近づいてきたスカルがベルの前に立って片眉を跳ね上げてベルを睨んだ。
「ボンゴレが怯えるから、それ以上はからかうな」
「うーん?」
うろんそうにスカルを見たベルは、綱吉によりかかったままの体勢で首を傾げた。
「えーっと、だれだっけ? どちらさん?」
「カルカッサの、スカルだ」
「あー、カルカッサんとこのね。マーモンと同じ、元アルコバレーノでしょ? 俺はベルフェゴール、よろしく。ベルでいいよ」
そこまで言ってからベルは綱吉の身体から離れ、スカルに向かって白い手を差し出した。スカルは彼の手を一瞥してから、手を差し出した。スカルの手には黒い革手袋がはめられたままだったが、ベルはスカルの手を手袋ごしに握った。
「オレもスカルと呼んでくれて構わない。それにあんたのことなら知ってるさ。プリンス・ザ・リッパー」
妙に艶やかな微笑を浮かべてベルがスカルの手を離した。
わざとらしく綱吉と視線をあわせるように背中を丸め、ベルは幼い子供を相手にするかのように甘ったるい優しい声を出した。
「で、ツナヨシはどこに行こうとしてたの? 王子、病棟にツナヨシがいるって言われたんだけど。すれ違いになんなくてよかったよ」
「え。そうだったの? ごめん。ベルが来るなんて思ってなかったから……」
「今から鳥籠に行く途中なんだ」
「へえ! ツナヨシってば、また籠の鳥になりにいくの?」
「違うよ。あの部屋にいろいろ置いてきちゃってるし、それにあそこ、けっこう居心地よくて――」
鼓膜を突き破るような甲高いサイレンが突然に鳴りだした。呼吸をつまらせた綱吉の腕をスカルが握って引き寄せ、ベルが身構えるように両手を持ち上げた。サイレンは断続的に続く。近くのドアから執事らしき人間が飛び出してきた。男は廊下に立っていた綱吉達を見ると驚いたように目を見開く。
「こいつのことは任せておいてくれ。おまえはおまえの仕事をしろ」
スカルの低い声音に男はしっかりと頷いたかと思うと、「ボス、お気をつけくださいませ」と素早く一礼するとどこかへ走り去っていった。
サイレンは鳴りやまない。スカルがぴったりと綱吉に寄り添うように立ち、スーツの内側に手を入れて拳銃を取り出した。安全装置を外したスカルは拳銃のグリップを握りしめて顔をひきしめる。尋常でない空気を感じ取った綱吉の身体は指先にまで緊張が行き渡り、今にも膝から崩れてしまいそうになる。両手の拳を握りしめると、かちりと指輪と指輪がぶつかりあうような感覚がする。見下ろした手の指には、大空のリングと霧のリングがあった。脳裏に一瞬、包帯だらけのリボーンの姿と血塗れの骸の姿がちらつく。座り込みたくなる衝動を面には出さず、綱吉は近くに立っているスカルの腕を掴んだ。
「これは、いったい何のサイレン?」
「非常警報」
ベルが歌うように言う。
「誰かが監視所を突破してボンゴレの敷地に入ったってこと。――ツナヨシ。離れるんじゃないよ」
周囲を警戒するように視線を巡らせながらベルがちらりとスカルを見る。
「スカルの戦闘スタイルは何?」
「格闘技は一応できるが、銃撃の方が自信がある」
「獲物は?」
「ベレッタのM92。予備の弾倉は五つある。ボウイナイフも一刀所持している」
「りょーかい。じゃあ、スカルが後衛。俺が前衛でオッケィ?」
「オーケイ」
「どこへ行こうっかねえ」
「鳥籠に行くぞ。あそこはどこよりも頑丈な部屋のはずだ」
「まあ、そっだろうねえー。じゃあ、行こうか。ツナヨシ」
「――う、うん。分かった」
スカルに腕を掴まれて歩き出そうとした綱吉の視線は、窓の外の風景につなぎ止められた。美しく整えられた庭の木々をなぎ倒しながら車が二台、ものすごい勢いで屋敷に向かってきていた。
「――車……?」
スカルに腕を掴まれたままで綱吉は窓際へ近寄った。
途端、ぐいっと腕を引かれ、綱吉はスカルの身体に身体をぶつけてしまった。
「ばか! 窓際に近づくんじゃない!」
「え」
「そうそう。狙撃されちゃったら大変でしょーよ。ま、ボンゴレの屋敷の硝子は全部防弾硝子だとは思うけど、用心しといた方がいいね」
窓をはさんで、スカルと綱吉、ベルとに別れて、三名は壁に張り付いた。窓からそっと顔を出して綱吉は庭園を眺める。ボンゴレの人間が車を銃撃してるが車は停車しない。
「うっわ、なんであれ停車しないの?」
「自動操縦になってるんだ。運転手がいない」
綱吉の横から顔をのぞかせたスカルは、どこから取りだしたのか、いつの間にか小型のスコープを目元にそえて、庭を眺めている。車はどんどん迫ってくる。誰も車を止めることができない。すでに屋敷まで距離がない。車が綱吉の視界から消えた途端、どん!という建物を揺らすほどの音と衝撃があり、間髪をいれずに爆発音が鳴り響き、窓枠の硝子が内側に向かって吹き飛ぶ。気がついてみれば、スカルの腕が綱吉の頭をかばうように回され、綱吉はスカルの胸元へ顔を寄せていた。
「ぶつか、った? 何台? 一台だけじゃないよね?」
スカルの腕に抱き寄せられたままで綱吉が言うと、彼は真剣な眼差しで外を睨み付けている。 割れた窓の向こうでは大勢の人間が怒鳴りあい、大騒ぎになりつつたった。
「なんともないな?」
「うん」
「襲撃?」
ベルの問いかけにスカルは短く唸る。
「これが先方隊だとしたら、すでに連続して攻撃部隊が来るはずだ。しかし、それがないとなると、この騒ぎは――警告か、もしくは宣戦布告か」
外を見たままでスカルは続ける。
突然、唸るようなサイレンの音が急に止んだ。綱吉とベルが思わず天井を見上げる。どこにもスピーカーなど見あたらなかったが、悲鳴のように続いていたサイレンの余韻が天井のどこかにあるように綱吉には感じられた。
「非常警報が止んだということは、周辺の包囲が完了したということだろう。とりあえず、ボンゴレ側は警戒レベルをランクSにするはずだ。ボンゴレ。部屋に行くぞ。事態が落ち着くまで、やはりあんたは鳥籠にいるべき――」
スカルの話の途中で綱吉は彼の腕を振り払った。驚いたようにスカルとベルが綱吉を見る。何かを叫ぼうと思っても言葉が声にならなかった。スカルとベルを説き伏せられるほどの言葉を言えそうにない。悔しげに唇をゆがめ、綱吉は彼ら二人に背中を向けて走り出そうとした。が、その腕をスカルに掴まれる。
「何処行くんだ!?」
「現場に行くッ」
「馬鹿! 鳥籠に戻るんだ!」
「嫌だ!!」
「我が儘を言うな!」
「ワガママなんかじゃない! これはオレの戦いなんだろ! だったらオレに戦わせてくれよ! それのどこがワガママなんだよ! 邪魔をしないで!」
「じゃあ、正直に言うが、今回の内乱を治めるのには『あんた』の力量じゃ無理だ! 悪いが、圧倒的なほどに経験値が不足してるうえ、『あんた』はこっちの世界に染まってなさすぎるんだ。そんな状態じゃあ、またいつ錯乱に陥るか分かったものじゃないだろう!」
綱吉の腕を強く掴んだスカルは、まるで己の身が切られているかのように、苦しげな顔をして言葉を続けた。
「『あんた』が死んだりしたら、ボンゴレはおしまいなんだ! それは、分かるだろ?」
サングラスごしのスカルの視線が、探るような色を浮かべて綱吉を見つめている。サングラスのレンズに今にも泣きだしてしまいそうな綱吉自身の顔が映っている。
『あんたの力量じゃ無理なんだ』
改めて言葉にされると綱吉は痛感せざるを得ない。
空白の、九年と半年という時間の存在を、意識せざるを得ない。
「そんなに簡単に死んだりなんてしないよ、頼むよ、お願いだよ……」
泣きだしたいのを必死にこらえながら、綱吉はスカルの腕を掴んだ。ぶるぶると手が震えているのをおさえることすら出来なかった。
「お願いだよ……、スカル、ベル……。オレ、オレは、ここにいていいんでしょう? ここに、いる、意味っていうのが、オレにも、あるはずでしょう? だって、オレが……、『オレ』が立っているのは、この場所なんだから……」
「……ボンゴレ……」
うなだれた綱吉の腕をスカルが手放す。
ぶらりと、綱吉の腕が身体の両脇に力無くたれる。
割れた窓の外から激しい喧噪と怒号が風と共に吹き込んでくる。幾度か嗅いだことのある、何かが燃えて焦げる臭いが綱吉の鼻腔をさすように刺激する。ごくりと飲み込んだ唾液すら苦く感じられた。
戦場なのだ。
綱吉は自覚する。
ここは間違いなく『戦場』で、
そして、十八歳の沢田綱吉が選ぼうとしている『未来』そのものなのだ。
いまここで、この場から逃げ出すことは、己の未来を否定するようなものだ。
綱吉は両手の拳を握りしめる。
逃げたくはない。
逃げたくはない。
何度も繰り返す。
逃げたくはない。
だって。
ここは。
愛すべき彼等がいて。
懐かしい彼等がいて。
みんなが綱吉のことを大事にしてくれていて。
泣きたいほどに嬉しくて喜ばしくて幸せで素晴らしい『未来』なのだ
だから逃げたくはなかった。
だから守りたいとおもった。
沢田綱吉の、
自分自身の手で守りたいと思った。
痛くても辛くても怖くても、ここに立っていたいと思った。
『彼等』がいてくれるのならば、立っていられると思った。
「ボンゴレ」
「ツナヨシ」
スカルとベルの気遣わしい声音が静かに綱吉の耳に届く。
短く息を吸って、綱吉は想いをこめて言葉にした。
「頼むよ、オレは、『オレ』から、逃げたくないんだよ……。お願いします。オレを、行かせてください……、お願いします」
綱吉は深々と頭を下げる。ぽたりと片目だけから涙が落ちていったが、必死に涙をこらえたのでそれ以上は涙はこぼれてこなかった。
ほんの少しだけの沈黙だったろうが。
綱吉にとっては長すぎる沈黙だった。
「まーったく。他人行儀なんだからなあ、ツナヨシは」
ふわり、と綱吉の頭のうえに何かがのせられる。顔を上げるとベルがすぐ近くに立っていた。綱吉の頭のうえにのせていた手のひらを引いたベルは、顔をもちあげた綱吉と目線を会わせるうに背中を丸めて、右手の人差し指でこつんとツナヨシの額をはじいた。
「いいよ。ツナヨシが命じるんなら、王子は仕方がないから言うことを聞いてあげる」
ベルの右手が綱吉の胸元を指し示して、前髪にほとんど隠れている左目をぱちりとウィンクさせる。
「だから、ツナヨシは大勢の人間のうえに君臨する皇帝らしく、兵隊に命令すればいいんだよ」
「ベル……」
「さあ、我らが永遠の君主サマ! ご命令を!」
おおげさな態度で一礼をするベルの横で、スカルは片手に拳銃をぶらさげたまま、もう一方の手で額をおさえて天井を向いた。
「――どーしてこう、ボンゴレの周りは……」
「……まわりは……、なに?」
スカルは呆れたような笑みを浮かべて綱吉を睨むと、ため息混じりに囁きながら歩き出した。
「あんたに中毒になってる連中ばっかなんだろうな、っていう話」
「え?」
聞こえなかった綱吉がぽかんとしていると、ベルが「よしよし」と言いながら綱吉の頭を撫でてくれた。見上げると、ベルは綱吉の背中に手をそえて唇に笑みをうかべる。
「いいのいいの。ツナヨシはツナヨシでいてくれていいんだよ。だってねえ、ツナヨシがツナヨシじゃなくなったら、すごい残念だもの」
「はぁ……、うん?」
曖昧に頷いていた綱吉の顔に顔を近づけてベルは囁く。
「だいたい、ジャンキーなのはスカルだって一緒のくせにねえ」
「うるさい。行くんだろ、え? 行くぞ! ボンゴレ!」
「うぇっ? はい!」」
何故かスカルに怒鳴りつけられ、綱吉はびくっと身体を揺らして早足でスカルのもとへ駆ける。靴底でじゃりじゃりと砕けた窓ガラスを踏みながら走りだすと、背後でベルの笑い声がした。走りながら振り返った綱吉と目が合うと、ベルはにっこりと笑って走り出す。
一人ではない。
スカルとベルが一緒にいる。
独りではない。
左側にはスカル、右側にはベル、そして中央には綱吉。
三人は目に染みるような黒煙をあげている衝突場所に向かって廊下をひた走った。
|
|
××××× |
|
廊下を走り、階段を駆け下りた先――、玄関ホールは大勢の人間が外と内へ向かって行き来していた。スーツを着ている者が大半だったが、それらに混じって白衣の男女が右往左往している。
「ボンゴレ。外だ」
スカルが先行するように先を行く。そのあとを綱吉は追いかけた。ほこりっぽい空気にむせながらも大きく左右に開け放たれている玄関ドアから外へ飛び出す。あちこちから「ボス」「ボンゴレ」「沢田さん」などと綱吉に向かって声がかけられる。綱吉は表情を引き締め、彼らを一瞥して頷いた。その頷きは形だけのパフォーマンスにすぎなかったが、『ドン・ボンゴレ』が混乱する場所へやってきてくれたというだけで、場の空気が見違えるように活性化したことが肌で感じられる。
うまくやらなくてはいけない。
心臓の音が身体の外にまで響いているような錯覚、極度の緊張をおさえるように、綱吉は丈の長い外套の舌で両手の拳をきつく握りしめた。
なぎ倒された植木から直線上の屋敷の壁に二台の車が衝突していた。片方の車はまるで爆発でもしたかのよに大破して燃え上がっていた。その奥に、もう一台車がある。衝突したときに正面からではなく斜めに激突したのか、ぐしゃりと左半分だけがつぶれ、奇妙な感じに右半分がそっくりそのまま残っているようだった。思わずひるんでしまうくらいに炎上している車の炎が屋敷の壁を焦がしている。灰色の煙をあげて燃える炎の周辺には、煙にむせていたり、崩れた瓦礫で負傷した人間に手を貸していたりする男達がいた。火事場を囲むように十数人の男達がその場にいた。庭園の遠くのほうからも怒号のような会話が聞こえてくるが、何を言い合っているのかは綱吉の耳には届かなかった。
燃えさかる炎で肌がぴりぴりとあわだつのを感じながらも、綱吉は近づけるだけ現場に近づいていった。頭の傷口を手で押さえていた五十代くらいの金髪の男が綱吉の姿を見て、目を見開く。「ボス!」という男の声によって周囲の人間達にも綱吉の存在が伝わり、波紋のようにさざめきが広がっていく。
綱吉は大きく息を吸い込んで、うなり声をあげるように燃える炎に負けじと大声で叫んだ。
「――怪我人は!?」
「ボス!」
「すいません、こんなことになっちまって!」
「危ねえから、こっちに来ちゃあ駄目ですよ!」
口々に男達が声をあげる。
「まずは負傷者の救助を優先させて! 科学班はいるの!? いるのなら爆発物が他にないかどうかの確認を! 科学班にまだ連絡をしていないのなら早く連絡をとって!」
「はいっ」
若そうな男が大きく頷いてどこかへ走っていった。
「ボス!」
綱吉の指示を仰ぐかのように、楕円方の細い眼鏡をかけた男が近寄ってくる。一瞬、男が訝しげな顔をして綱吉のことを眺めた。いくら混乱している場だからといっても、やはり十年近い歳月の誤差には気がつくのだろう。男が疑問を口にする前に綱吉は先手をうって先に口を開いた。
「状況は?」
「重傷者はすでにドクター・シャマルのところへ運びました。軽傷者はいまから医務棟へ向かわせます」
「消防車に連絡は?」
「警察と消防への連絡はランチアがしてくれたはずです」
「うちに消火剤はないの?」
「屋敷の地下に保管されてるはずです」
「すぐに手配して。これ以上の被害の拡大を防いで!」
「わかりました」
男は頷いて、近くにいた男を三名ほど従え、火事場よりも向こうへ走っていった。すでに怪我人は退避したらしく、周辺に残っているのは呆然と炎を見上げている数名の男達のみだ。
「危ないですから。ボス、下がっててください」
頬に傷のある男が優しげに笑って、綱吉達を後方に下がるように腕を差し出した。「ありがとう」と短く礼を言って綱吉は後ろへ下がった。それでもちりちりと髪が焼けてもおかしくないような熱風が肌を撫でていく。
「――お見事じゃん」
ひそめた声音でベルが言う。
肩越しに振り返れば、彼はにぃっと口元だけで笑う。
綱吉は表情を凛々しく保ったままで、ゆっくりと息をはいた。
「……うまくできてるのなら、よかったよ」
「ボンゴレ!」
綱吉の声音にかかるようにひときわ大きな声が横側からかけられる。綱吉達が先ほど飛び出した玄関側から長身の男が大股で走ってくるところだった。特徴的な頬の傷跡と、類い希な長身で、彼がすぐに誰か綱吉は思い出すことが出来た。
「ランチアさん!」
ランチアは火事場を苦々しげに見上げて顔をしかめる。黒い切れ長な瞳が綱吉を見て不安そうに揺れる。
「こんなところへ出てきては駄目だ。まだ他に爆発物があるかもしれん、危険だ。この屋敷ではなく、違う邸宅へ守護者共々移動したほうが――」
「ランチアさん」
綱吉は渋面を浮かべているランチアの腕に触れて首を振った。
「きっと、どこにいたとしても、オレは危険なんですよ。だったらどこにいても同じです」
ランチアは何かを言おうとして口をひらきかけたが、結局は唇を結んだ。スカルが一歩ほど前へでてランチアに問いかける。
「車は何台突入しようとしたんだ?」
「五台あった。上空からヘリが一台援護に回っていてな、そちらを迎撃するのに手間取っているうちに通過されたらしい。三台はくい止めることが出来たんだが、二台は駄目だったようだ。一台は衝突と同時に爆発。もう一台は正面から衝突せずにハンドルがきられたうえ、減速したらしいと目撃した者が言っていた」
「……一台が爆破、もう一台は――」
ぶつぶつと言いながらスカルが歩き出す。つられて綱吉が歩き出すと、ベルとランチアも黙ってついて来た。
ごうごうと音をたてて燃える車とは、五メートル以上離れた場所に、減速して壁にぶつかった車は、綱吉達から見ればバックバンパー側が最初に目に入る。左前方がぐしゃりとつぶれている以外、反対側の右前方から右の後方にかけては、ほとんど損傷がないように見える。スカルは無言のまま、無事な車体側が見える位置まで歩いていった。くるりと身体を反転させて車体を見たスカルは身体をぶるりと揺らすようにして硬直させた。慌てた綱吉は走ってスカルの隣へ行き、彼と同じように壁に激突した車を振り返った。
車の車内は真っ赤な液体がぶちまけられていた。一瞬、それが血液かと思って綱吉は身体が冷たくなるのを感じたが、てらてらとした輝きのおかげで、赤い液体がペンキだということにすぐ気がつけた。悪趣味な装飾だと思って眉をひそめると、黒い車体の後方に赤いペンキでてのひらほどの幅で文字が記されている。イタリア語だった。綱吉が脳内で一生懸命翻訳しているうちに、ベルが早口のイタリア語でペイントされている文字を読んだ。綱吉がベルを見上げると、彼はもう一度イタリア語で言ったあと、日本語でゆっくりと言い直した。
「『古き血を守るために新しき血を流せ』って書いてあるんだよ。いったい何のことだっての」
「……誰かを守るために、誰かを傷つけるってこと?」
「そんな感じなんじゃないの?」
声に出さず、何かをぶつぶつと呟いていたスカルが息を呑んで、ベルと会話していた綱吉を見た。サングラスの奥で彼の目が大きく見開かれる。
「え」
スカルの視線が綱吉からずれ、後方を見上げるようにして見た。せり上がってきた不安感にかられ、綱吉はスカルの視線を追うように背後を振り返る。目線の先には灰色の煙がもうもうと上がるなか、豪奢な屋敷がそびえ立っている――その向こう側にある『建物』を思い出して、綱吉は全身から血の気が引いて、悲鳴をあげそうになった。
綱吉が勢いよく振り向いたせいでランチアが驚いたように目を開く。
「病棟――、病棟のある方は!?」
「病棟? 異変はないようだが――」
「ランチアさん、ここのこと、任せます!」
ランチアの返事を聞かずに綱吉は外套の裾をばさりとはためかせて身をひるがえして駆けだした。すぐにベルとスカルが横に並んだ。綱吉はスカルの目を見た。スカルは綱吉と目が合うと頷いた。全身の肌が泡立つような感覚を感じながら綱吉は両手の拳をきつく握りしめた。
「どうしたっての?」
開け放たれたままだった玄関から屋敷に飛び込みながらベルが言う。綱吉が全力で走っていても、隣を走るベルにはまだ余裕があるのか、彼は息を乱す様子もなく不思議な顔をして首を傾げた。
「こっ、『これ』が、『今回のこと』と関係あるのなら、相手は、オレと、リボーンを、殺したいんでしょ? リボーンのところに、警護は?」
「屋敷に突っ込んでくるとは思ってなかったからな、警護なんてつけてないはずだ」
スカルの言葉に綱吉は奥歯を噛みしめたあとで、呻くように言った。
「いくら凄腕のヒットマンだってあの怪我で襲われたらどうなるか分からない」
「りょーかい。リボーンの部屋はどこ?」
「第一手術室の、隣だ!」
スカルの言葉にベルは「分かった」と言って頷いた。
「先に行くよ」
言うが早く、ベルが走る速度をあげる。みるみるうちにベルの姿が先行していくのを見ながら綱吉は走った。スカルはどちらかと言えば綱吉と同じくらいの体力らしく、ほとんど二人は肩を並べるようにして走った。走っているせいで心臓がつよく脈打っているのか、それとも確信に近い嫌な予感が的中している可能性を示唆して、どきりどきりとしているのか。もはや綱吉には分からなかった。豪華な装飾が施された屋敷の廊下を走り、渡り廊下の扉を開いて医務棟へ続く廊下を走り抜ける。綱吉達がきた道順とは違うアプローチがあるのか、渡り廊下の外を白衣の人間が大きな鞄を持って走り出ていったり、逆に負傷者を腕に抱えるようにして連れてきている場面が渡り廊下の窓硝子ごしに見ることが出来た。短い階段を上り、医務棟の扉を開けて中へ入る。
消毒薬の匂いが鼻孔をつき、緊張感はさらに強まっていく。何名かの看護士がどたばたと何かを両手に抱えながら廊下を行き来しては、どこからか怒声ともとれるような声が必死に指示を出している声が聞こえてくる。
走って向かってくる看護士とすれ違いながら、綱吉の足取りはだんだんとゆっくりとしたものになっていた。激しく呼吸に喘ぎながら壁によりかかる。その隣に立ったスカルも、綱吉同様に身体全体で呼吸をするかのようだった。二人はどちらともなく視線をあわせ、忙しく行き交う白衣の看護士達――ほとんどが女性だったが男性もいた――にぶつからないように注意しながら、病棟の奥に向かった。
奥へ向かうほどに緊迫した空気の密度があがっていく。枝分かれしたようにいくつかの手術室がある場所にくると、どの部屋も赤い手術中のランプが灯っている。
「ボンゴレ……」
スカルが小さな声で綱吉のことを呼ぶ。
気がついてみれば、綱吉はスカルの右腕の袖を掴んで立ち止まっていた。掴んでいた袖を放し、綱吉は握った片手を唇に寄せる。
怖かった。
奥へ行って、もしもリボーンが死んでいたりしたらと思うと恐ろしくて仕方がなかった。
もしも。
彼が死んでいたら。
どうしたらいいのだろうか。
ふいに体中から力がぬけそうになって、綱吉は片手を彷徨わせて壁に触れた。壁に身体をよせて息を吐く。
「ボンゴレ。しっかりしろ」
「スカル、……もしも、リボーンが、し、ん、――」
「馬鹿なことを言うな!」
スカルが綱吉の手首を掴んで強く引いた。彼に手を引かれるままに綱吉は歩をすすめる。廊下の左右には互い違いの位置に五、四、三、二、と手術室の扉があった。番号がカウントダウンされていくのを横目に見ながら綱吉は歩いた。
シャマルに案内された第一手術室の隣――、集中治療室のスライドドアは閉まっている。足が止まりかける綱吉の手を強く掴んで引き寄せ、スカルは唇を引き結んで思い切りドアを引いた。
カーテンが閉め切られた室内は少々薄暗かった。ベッドの傍らに立っていたベルは、開いたドアに反応して機敏に振り返る。ふわりと軽そうな金色の髪がゆれて、すべらかな頬に毛先がこぼれおちる。
ベルは片足を引いて立ち位置を変え、右手でベッドを指し示しながら首を振った。
「いない」
「え」
「いなかった」
「あの身体で動くなんて無茶すぎる!」
素早く言ったスカルが綱吉の手を放して、ベッドに走り寄った。両手をベッドのシーツのうえにのせてすぐに綱吉へと振り返る。
「温かいからまだ近くにいるはずだ!」
「うっし! じゃあ手分けして捜そっか」
「ちょっと待った。三人で別れるのはナシだ。ベル、あんたがボンゴレと一緒に行ってくれ。オレよりは、あんたのほうが戦闘能力はきっと上だろうからな」
「あららぁ? ずいぶんと過大評価してくれるんじゃないの?」
「過小評価ではないな。――あんたなら、たとえ顔を知ってる相手だって、裏切り者と分かれば躊躇せずに殺すだろ?」
ベルが首肯するのを見てから、スカルはスライドドアに飛びついて勢いよくドアを開ける。ドアの付近に立っていた綱吉を見てスカルは言う。
「オレは病棟の周囲を検索する。ボンゴレ達は屋敷の――、そうだな、執務室に行ってみてくれ」
「執務室? ツナヨシがいつも仕事してる場所じゃん」
「リボーン先輩が自分の意志で病室から出ていったのならば、十中八九、ボンゴレの身を案じて部屋を抜け出した可能性が高い。だから、一番最初に向かうとしたら、執務室のはずだ」
「りょうかーい」
「頼んだぞ」
ベルが片手を持ち上げてひらひらとさせる。
スカルは綱吉のことをじぃっと見つめ、立ちつくしている綱吉の二の腕辺りに触れた。
「気を、しっかり持てよ? ――綱吉」
優しい声音でスカルが綱吉の名前を呼んだ。
沢田綱吉。
それが綱吉の名前だ。
ドン・ボンゴレという名前もまた、綱吉を示す言葉だ。
「……うん、うん、大丈夫、落ち着いてきたから、大丈夫」
綱吉はしっかりと頷いて、スカルの肩に指先で触れる。
「スカルも、気をつけて?」
「ああ」
わずかな微笑を見せたスカルは、颯爽とした様子で廊下を走り出していった。
「オレらも行こうよ、ツナヨシ」
いつの間にかすぐ後ろにいたベルが囁く。
彼に促されて綱吉は病室を出た。視界のすみでスライドドアが音もなく閉じていくのを感じながら、綱吉は深く息を吸い込んで前を向いた。近くの手術室からは緊迫した医師の声が術中であることを示すかのように漏れ聞こえてくる。
「行こう」
そう言って、綱吉は走り出す。全力疾走とまではいかないが、急いで来た道を戻った。途中で執務室の場所が分からない綱吉にかわって、ベルが先行して走り出す。まるで体重を感じさせない身軽な様子でベルはほとんど物音さえ立てずに走る。獲物を追う獣のようだった。対して綱吉の方はというと、外套をまとっているせいか、次第に身体を重くなってきているような気がして、気をぬくと足がもつれてしまいそうだった。すれ違う人々のすがるような視線や気遣うような仕草に、綱吉は出来るだけ強気な表情を浮かべて、相手を安心させるようにつとめた。どんなに苦境に立たされていようとも、トップに立ってる人間は不安そうな顔をしては駄目だと、何度も何度もリボーンに教えられていた。黒い髪、黒い瞳、小綺麗な顔立ち、皮肉ばかりいう唇、ガンオイルと火薬の匂いがする指先、トレードマークのようなボルサリーノ、そして黒ずくめの姿――。
声には出さず、心の中で何度も名前を呼ぶ。
リボーン。
リボーン。
リボーン。
おまえがいなくなったらオレはいったい、どうしたらいいの?
たったひとりで、血路に立てって言うの?
おまえが此処にいないのなら、オレが此処にいる意味も理由もないじゃないか。
そこで綱吉は愕然とする。
親友でありかけがえのない友である守護者達や、
幼いころからよくしてくれた愛すべき知人達よりも、
リボーンという殺し屋の少年たったひとりの存在が、
どんなに沢田綱吉という人間のなかに根深く食い込んでいるのか、思い知った。
人が死ぬのは悲しい。そして苦しい。だけれど、人は死ぬものだ。やがて喪失の痛みも風化し、思い出として刻まれる。そうやって受け入れていくものだと綱吉は理解している。だがしかし、リボーンの死だけは、受け入れられそうになかった。彼が死んだらきっと綱吉は己を保っていられる自信がない。発作的に死にたくなるような気がした。
ふいに、リボーンと交わしたキスの感触が思い出される。微笑んだ顔、怒った顔、気遣わしげな顔、意地悪そうに笑う顔、次々に浮かんでくるのはリボーンのことばかりだった。
死んだりしたら絶対に許さない。
どこまでも追いかけていって殴ってやるからな。
物騒な言葉を胸のうちで毒づくも、激しい焦燥と不安で綱吉の魂は潰れてしまいそうだった。片手で胸元をおさえながら走っていると、ふいにベルが走る速度を落としてきて綱吉と肩を並べた。
「苦しい?」
綱吉は胸元をおさえていた手を外して首を振った。
「平気。……オレのせいで、ベルのことも巻き込んじゃって、ごめんね」
ベルは「にしし」と楽しそうに笑い声をたてた。
「別にいいよー。俺、こういうスリル大好きだし、それにこれも仕事だしね」
「仕事?」
「ボンゴレ十代目の護衛なんて仕事、なかなかうちには回ってこないんだよ?」
「そんな、もんなの?」
「ボンゴレはボンゴレ、ヴァリアーはヴァリアーだからね。うちんとこに依頼がくれば、ツナヨシの護衛とかもするんだろうけど、だいたいは守護者の連中がするだろうしね。それに、ボンゴレにはいい人材がいるだろーし。――とはいえ、ヴァリアーだって負けてないけどね」
「そ、そうなんだ」
「ツナヨシも、十八なのに、大変でしょ?」
「オレ? オレは……」
呼吸に喘ぎながらも、長い前髪に隠れそうになっているベルの瞳を綱吉はまっすぐに見つめた。
「オレは、好きで、この場所に立とうと思ってるんだから、大変でもいいんだ」
綱吉の答えを聞くとベルはまるで子供のように満面の笑みを浮かべて、何度も何度も頷いた。
「うん、うん。それでこそ、ツナヨシ! ――っと、あそこだ!」
数メートル先にあった扉を指し示してベルが叫ぶ。どきりと綱吉の心臓がひときわ大きく高鳴った。扉の前で立ち止まり、綱吉は壁に片手をついて息を整える。急な運動のせいか、がくがくと膝が震えている。ぎゅっと拳を握りしめて、綱吉はベルを見上げた。
ベルは綱吉の視線を受けると片手を持ち上げて、ドアノブを握った。
「開けるよ」
「うん、……うん、お願い」
綱吉の目の前でベルが扉を開いた。
執務室はカーテンが引かれたままのせいか日中だというのに薄暗かった。ひっそりとしていて人の気配はない。ベルが扉を開けたまま、執務室のなかに入っていく。一通り部屋を確認したあと、奥にあった扉を開けて隣の部屋へ入っていく。綱吉はぼんやりと扉に寄りかかるようにして室内を眺めていた。
未来の綱吉がいつも仕事をしている場所だ。一人で使うには大きな机のうえには、様々な大きさの写真立てが置かれている。きっと綱吉の知らない『綱吉』が映っているに違いない写真が飾られているのだろう。調度品のなかには綱吉の趣味にあうものがたくさんあった。初めて訪れたというのに、ずっと前から過ごしていたかのような錯覚がふわりと綱吉の脳裏をかすめて消えていった。
奥の部屋から戻ってきたベルは綱吉と目を合わせると首を振った。握った拳を額にあてて綱吉は唸るように呟いた。
「――どこ……、どこに行ったんだろう。まさか、拉致されてたりとか」
「あの騒ぎのなかで? 警備レベルがSランクだってのに、脱出できる隙間なんてあるもんかな……?」
「まだ、探してないところがあるよね? もう少し、建物の中を探して――」
「十代目!」
遠くから聞き慣れた声に呼ばれ、綱吉は身体を揺らすようにして振り返った。全速力で走ってきた獄寺は、執務室の扉を閉めたベルとその近くに立っていた綱吉を見て、涙が浮かんでいる目元を震わせる。
「獄寺くん! どっか違うとこに行ったんじゃ?」
「ちょうど、車庫に向かおうとしたら警報がなったんで、慌てて戻ってきたんです! ご無事でしたね!」
「あのね、獄寺くん、オレ、オレは無事なんだけど、リボーンが病室にいなかったんだ!」
「え!?」
「スカルが病棟の周りを捜してくれてるんだ、オレ達はスカルに教えられて、もしかしたらリボーンがここにいるかもしれないって――」
「そうなんですか。リボーンさんが。いま、ちょっと屋敷の中が慌ただしくなってますが、人員をさいて捜索するように命令を出しておきますね」
「お願いできる?」
「ええ、もちろんです」
優しげに頷いた獄寺の顔が厳しく引き締まる。綱吉が面食らっていると、背後から軽い足音がして、長い金髪を首のうしろでまとめたメイドが現れた。顔が蒼白でいまにも体を震わせてうずくまってしまいそうな彼女は、両手で何かを大事そうに持っていた。
「――どうした?」
「緊急回線でお電話が入ってます」
「誰からだ?」
「ヴェネツイアの養護施設からです、複数の人間から銃撃を受けたという報せが――」
「クソッ! やっぱり波状攻撃してきやがったな!」
苛立たしげに呻きながら、獄寺はメイドが差し出した電話の子機を受け取る。メイドは気がぬけたのか、絨毯のうえにへたりと座り込んで頭をうなだれた。細い背中が震えているのに気が付いたが、綱吉も気が動転しているのでうまく慰める自信がなかったので黙って彼女を見つめるしかなかった。獄寺は綱吉達から視線を外し、壁際のほうを向いて電話を耳に押し当てた。
「もしもし! 現状は――、……あ?」
「え」
「あ」
立ち上がったメイドがまるで下から突き上げるように獄寺に体当たりをした。よろりと数歩よろめいた獄寺の顔が驚きに染まり、次の瞬間には苦痛へと変わる。びくりと身体を震わせた獄寺の手から受話器が絨毯の上に落ちた。
「ご、く、……で……」
綱吉の吐息のような呼びかけで停止していた時間が動き出す。女が獄寺から離れ、近くの壁に背中をぶつけるまで後退した。両手に握られていたのはペティナイフ、刀身は真っ赤になっていた。一瞬で駆け抜けていった寒気が綱吉の思考を凍り付かせる。瞬きすら忘れて獄寺へ視線を移すと、彼は脇腹のあたりを押さえてつよく歯を噛みしめて呼吸を引きつらせた。出血はあまりなさそうだが、スーツが赤黒い染みがじわじわと広がり始めていた。
獄寺へ手を伸ばしかけた綱吉は、妙な胸騒ぎがしてベルの身体に両腕で横から飛びついた。案の定、ベルの両手にはナイフが握られていた。まさに手を振り上げようとしていたベルは綱吉に抱きつかれたせいで身動きがとれず、迷惑そうな顔をして「離してよ、殺せないじゃん」と訴えて綱吉の腕を外そうと身体を揺らした。
「だ、だめ、ベル! 殺さないで!」
「この女、ハヤトのこと刺したんだよ? いいじゃん、殺しても」
「駄目、すぐに殺しちゃ駄目だよ! この人になんでそんなことしたのか聞かないと」
「面倒くさいよ。殺そうよ。正当防衛じゃん」
「駄目。やめて。お願いだから、やめて」
綱吉が必死の形相で首を振ると、ベルは不機嫌そうに顔をしかめたが、暴れるのをやめた。ベルを拘束していた両腕を解いて、綱吉は壁を背にして立っている女性と距離をおいて向き直る。
両手でペティナイフを持ったまま、メイドの女性は短く引きつるような呼吸を繰り返すばかりで、緑色の目を限界まで見開いて綱吉を見つめている。なるべくそうっと、囁きかけるように綱吉は声をかける。
「なんで、獄寺くんを刺したの?」
「すみません。すみません、わたし、……わたしには、こうするしか――」
ぼろぼろと両目から涙をこぼしながら女性はペティナイフを絨毯のうえに落とした。血に汚れた手で白いエプロンを掴み、声をころして泣いていた女性は、ハッとしたように顔をあげ、絨毯のうえに転がっていた受話器を右手で指し示した。
「で、電話を」
ベルが女性を威嚇するように睨みつけているのを横目に、綱吉は獄寺の近くへ行き、足下に転がっている電話を手に取った。その際、小声で獄寺に「大丈夫?」と問うと彼は脂汗がういてきた顔に無理矢理に笑顔を浮かべて「へいきです」と言った。
深く息を吸い込み、十から一までの数字を心の中でカウントダウンする。
冷静に。
冷静に。
焦りも動揺も押し隠せ。
沢田綱吉を消せ。
ここにいるのは、
ドン・ボンゴレ。
静かに息を吐き出してから受話器を耳に当てる。獄寺の手が綱吉の腕を掴んだが、綱吉はそちらを見ずに、何もない壁を睨みつけた。
「もしもし」
『ご機嫌はいかがですか? ドン・ボンゴレ?』
ゆっくりとした喋り方のせいか、綱吉のおぼつかないヒアリング能力でも相手のイタリア語は完璧に聞き取れた。
「誰だ?」
『私が誰かということは問題ではありませんよ。問題なのは、あなたの行動です』
「この女の人に何をしたんだ?」
『おお、それではミセス・ロージは無事に仕事をやり遂げたということですね。たいへん、よろしい』
喉の奥を震わせるような笑い声をたててから男は言葉を続ける。
『彼女の家族を、素敵な高性能爆弾をセットにしてさしあげただけですよ。ついでに、ボンゴレが経営している養護施設二件とと養老院一件にもいくつか爆弾をセットしたことを、彼女に伝えただけです。ミセス・ロージ、あなたが私たちの人形にならないのならば、家族だけでなく、百人を超える人間が爆死しますよ、とね』
「どうして彼女に獄寺くん刺させた?」
『あなたと誰かが一緒にいるようならば刺すように言っただけですよ。人質が一人増えれば、よい保険になる』
「要求は?」
ぐ、と獄寺の手が綱吉の腕を強く掴む。
「駄目です、十代目」
「何を言ってるの、ツナヨシ」
獄寺とベルの非難の声を綱吉は一切無視した。
「要求があるんだろ? 言ってみろ」
『あなたの身柄を拘束させていただきたい。返事がノーの場合は、ミセス・ロージの家族と養護施設、養老院を爆破させていただきます。――いかがでしょう? 我々の招待に応じていただけますかね?』
「爆弾が仕掛けられているという証拠は?」
『証拠が欲しいのならば、ひとつ爆破させてみせましょうか? そちらのお屋敷に突っ込んだ車に乗せていたのはほんの挨拶がわりですよ? 施設周辺に設置した爆弾はもっと性能のいいものを用意させたましたから』
「リボーンは、どうしたんだ?」
『リボーン、ね』
ふいに男の声音の響きが低くなる。どろりとしたものが背中側から迫りきたように綱吉の心がびくりと痙攣した。
『あの呪われた子供こそ、呪われたまま滅びてしまえばよかったものを……』
「リボーンに何かしたのか!? あいつに何かをしたんだったら、オレはあんたのことを絶対に許さないからな!」
綱吉が激昂すると、受話器の向こう側がしん、と沈黙する。獄寺が小さな声で「十代目」」と気遣わしげに綱吉を見ている。顔色が悪い獄寺の身体に綱吉は触れる。彼は首を横に振った。駄目です、十代目――と言いかける彼の唇の動きから目をそらし、綱吉は受話器に向かって声を尖らせた。
「オレがイエスと言えば、爆破はしないんだな?」
「十代目ッ」
『ええ。お約束しましょう。――ミセス・ロージの手首とあなたの手首を手錠で繋いでください』
「手錠なんて――」
言いかけた綱吉は、絨毯のうえでうずくまっていたロージがエプロンのポケットから真っ黒な手錠を取り出すのを目にして顔をしかめる。ベルと獄寺の冷たい視線に怯えながらもロージはよろよろと立ち上がり、泣き濡れて赤くなった目で綱吉を見た。綱吉はロージを落ち着かせるように、優しい顔をしてしっかりと頷いて見せた。
「分かった。いいよ。ロージさん。あなたの手とオレの手を、それで繋いでください」
「すみません。ドン・ボンゴレ。わたし、……わたし、ッ」
「あなたが悪いわけじゃないですから」
ロージが震える手で己の右手と、差し出した綱吉の左手首に黒い手錠をかけた。冷たく重い感触が手首を飾るのを見下ろしている綱吉の耳元に、毒のように男の声がよどみなく注がれる。
『ミセス・ロージの身体には爆弾が仕掛けられています。あなたが逃亡したりすれば、彼女もろともあなたも吹っ飛びますので、お気をつけ下さいね。さあ、では、車庫へ向かってください。彼女の言うとおりの道を通ってパーティ会場に向かうんです。車は、途中でこちらの用意したものに乗り換えていただきますからね』
「悪いけど、オレ、運転出来ないよ。手錠されてるし」
『片腕で運転くらい出来ると思いますがね……。では、ミスター・ゴクデラにお願いすればよいでしょう』
「彼は怪我をしてる」
『怪我をしているからいいんですよ。早く手当がしたいのならば、迅速に行動しなくてはね』
「ふざけるな!」
『ふざけてなどいませんよ。――運転手のミスター・ゴクデラ、同乗者はミセス・ロージ、そしてドン・ボンゴレ。この三名だけで行動してください。他に追跡者などをつければすぐに分かりますし、発信器の類も周波数を把握ずみなので、用意しても仕方ありませんよ。そうですね。時間を決めましょう。そこからパーティ会場までは一時間もあれば到着できます。出発がもたついたり、途中で小細工をしようとしたら間に合いませんよ? 間に合わなかった場合は、一件ずつ、爆弾を爆破させていきますから。お急ぎ下さいね』
「いまの状況で車なんて出したら目立つぞ」
『では目立たないように考えて行動してください』
面白がるように受話器の向こう側で男が声を震わせて笑う。虫の羽音のように耳障りな笑い声が鼓膜に触れる。嫌悪感と苛立ちから握りしめていた電話を床へ叩きつけたい衝動にかられたが、理性に制された綱吉の手は電話をちゃんと握りしめていた。
『さあ、電話を切りますよ。電話が切れたらすぐに行動です。分かりましたね?』
「おまえを許さないからな」
『アリデヴェルチ。ドン・ボンゴレ』
綱吉は通話の途切れた電話をベルに差し出した。ベルは怪訝そうな顔をして受話器と綱吉の顔を見比べて眉をひそめる。
「なに? どういうこと?」
「ベル。ごめん。きみはここにいて。屋敷の中にリボーンがいるか捜して欲しい」
「はあ? なにそれ? 電話の相手んとこに行くんでしょ? 王子もついてくよ」
「駄目。相手はそれを望んでない。もしかしたら、相手がリボーンのこと拉致した可能性もあるし、……要求を違えることはしたくない。獄寺くん。運転とか出来そう?」
舌打ちをするベルから視線をそらして、綱吉は獄寺を見上げた。彼は汗を浮かばせながらも、しっかりと頷いた。
「え、ええ。出来ます」
「運転手は獄寺くんじゃないと駄目だって言うんだ。じゃなきゃ、養護施設とか養老院に設置した爆弾を爆破するって……。ごめん、怪我してて辛いのに君じゃなきゃ駄目だっていうんだ」
「大丈夫です。男、獄寺隼人。十代目とボンゴレの為ならば頑張れますから――。ちょっと、失礼します、ね……。傷口、ちょっと、応急手当してきます」
強がるように笑顔を浮かべて獄寺が執務室のなかへ入っていった。部屋のどこかに応急セットがあるのかもしれなかった。綱吉があとに続いて獄寺の手当てを手伝おうと歩みかけた前に、ベルが立ちはだかるように立った。ひゅん、と空気を裂く音がして、綱吉の眼前にデザインナイフの切っ先が突きつけられる。苛立ちを隠そうともしないベルの瞳が冷酷な輝きをたたえて綱吉を見下ろしていた。
「……ベル」
「なんだよ。別に。馬鹿正直に行くことないじゃん。俺も連れていきなよ。全部、俺がぶっ殺してあげるからさあ」
「出来ない。ばれたらタダじゃすまない、そんな危ない道は選べない」
「なに言ってんの? ツナヨシの命を危険にさらすよりは、その他大勢の命を犠牲にするべきでしょ? ツナヨシは一人しかいないじゃんか」
「ベル。それは違うよ。ロージさんの家族も、ロージさんも一人しかいだろ? 誰だって誰かの変わりになんてなれないし、誰だって一人しかいないんだよ」
「ツナヨシが危ないって分かってんのに行かせたくない」
怒りにまみれていたベルの表情がゆらぎ、ナイフを持っていない方の彼の手が綱吉の胸ぐらを掴み上げた。普段は前髪に隠されているベルの両目が綱吉の両目を射抜くように見た。ベルの目が怒りとも哀しみともとれるような色合いをのせてつり上がっているのが見えた。
「おまえがいなくなったら、どれだけの人間が悲しむのか、おまえは知らないんだ」
悔しげに唇を歪めるベルの頬へ手を伸ばし、
「ごめん」
綱吉は持っていた受話器を手放して絨毯のうえに落として目を閉じた。
刹那の逡巡。
ベルの肩に手をのせた綱吉は、一瞬で額に炎を宿して床を蹴った。壁に一度足をつき、勢いに任せてベルの頭へ思い切り振り上げた足を振り下ろす。防御の態勢になるまえに綱吉の足はベルの側頭部に当たり、勢いついたまま彼の身体を床へなぎ倒した。がづん、と鈍い音を立ててベルの身体は床に衝突し、わずかに跳ねて動かなくなる。彼の頭から外れて転がったティアラが少し離れた壁にぶつかって停止する。
「十代目!?」
物音に驚いた獄寺が、シャツの前をはだけたまま室内から走り出てきて、床に倒れているベルと、ハイパー化している綱吉を見て目を見開く。
「……手当て、終わったの?」
綱吉の問いかけに獄寺は何度もうなずき、「上着、もってきます」と言って部屋に戻っていった。
綱吉と手錠で繋がれていたロージは急な展開についていけないのか、表情少ないままに綱吉の額の炎をジィッと見つめていた。
「ごめんなさい。ロージさん。怖かった?」
「いいえ……」
ロージは首を振った。年のころは三十代半ばくらいだろうか。小さな子供がいてもおかしくないような年齢だな、とぼんやりと思う。彼女の家族の事を思うとそれだけで苦い気持ちが胸の内側から外側に向かって染みてくるようだった。
絨毯に俯せに倒れたベルの傍らに綱吉は片膝をついた。
目を閉じたベルの頬を手のひらで包む。彼の側頭部に額を寄せ、綱吉はきつく目を閉じた。
「ごめんね。ベル。――ごめんなさい……」
動かないベルの頭を撫でて綱吉は立ち上がる。
獄寺がシャツの第二ボタンあたりまで開き、スーツの上着のボタンをせずに袖を通した姿で姿を現した。手当をしたといっても止血が出来た程度だろう。長い間放置していればいるだけ獄寺の身体に負担がかかる。綱吉の不安な気持ちを感じ取ったのか、獄寺はナイフでほころびたスーツのあたりを片手で覆い、汗の浮いた顔でにっこりと笑った。
「ご心配なく。動くことに支障はありません」
ごめんなさい。
心の中で謝罪して、綱吉は表情を引き締めて獄寺を見上げた。彼は綱吉と目が合うと双眸を厳しく細めてうなずく。
「行こう。一時間で到着しないと爆破されちゃう」
「分かりました」
獄寺がかるく走り出すのと同時に綱吉も走り出す。少し先を行く獄寺の背中から、隣を走るロージへ視線を動かす。彼女は涙で濡れた顔をしている。綱吉を見た彼女の目が申し訳なさそうに再び濡れていくのを見て、綱吉は心が締め付けられる思いだった。
「ロージさん。大丈夫だから。きっと、あなたの家族も、あなたも助けてみせますから。こんな酷い悪夢なんてすぐに終わらせますから……」
綱吉はロージの手を握りしめた。冷え切っていたロージの手は強ばっていたが、綱吉の手をゆっくりと握り返してきた。ロージと視線を交わしあう。
「だから、もう少しだけ我慢して」
「はい。……はい、ボス」
震えるような声音で言ってロージは何度も頷いた。
綱吉は前を向いて、言葉を続ける。
「約束したんだ、リボーンと。オレに出来ることをするんだって。だからオレは絶対に負けたりなんかしない。オレの手でみんな――、みんな守ってみせる」
肩越しに獄寺が振り返り、笑みを見せる。
「さすが、俺が敬愛する十代目です。俺はいつの時代のあなたであろうと、心から誇りに思います」
綱吉は視線で獄寺の想いを受け取る。前を向いて走り出した彼は、十字路を右へ曲がった。続いて綱吉とロージも少し減速して角を曲がる。ばさりと外套の布地が風にはためく。ふいに、綱吉は右手で胸元をおさえた。ポケットには小さく硬い感触、リボーンの拳銃の銃弾がスーツの胸ポケットに一弾だけ入っている。
お願いだから無事でいて。
おまえが死んだら、オレは後悔しても後悔しても足りないんだから。
死ぬ気になればなんだって出来るって教えてくれたのは他でもない、おまえなんだから。
「生きてろよ」
声に出さずに吐息で囁き、綱吉はスーツの上から胸元をつよく押さえつけた。
|
|
××××× |
|
ベッドから起きあがれない笹川了平の頼みで、医療棟から騒ぎの渦中である屋敷へやってきたクロームは、出入り口付近でボンゴレの構成員の男から現状を聞き出した。
綱吉が現場に姿を見せたことを男から聞いたクロームは少し驚いた。正体がばれていないのはおそらくは人々が混乱しているせいで、綱吉の体格や髪の長さなどに構っていられないからだろう。しかし、こういった現状に慣れていない綱吉が屋敷の中を歩き回っているのだと思うとクロームは不安になった。
事情を知ってからも、クロームは綱吉の姿を捜そうと屋敷の中を急ぎ足で歩き回った。ときどきすれ違うメイドや執事、構成員に問いかけても誰も知らないという。そもそもボンゴレの屋敷はとても広く、階段があちこちにあるのですれ違いになることが多々ある。
談話室を確認しても誰もいなかった。すぐにクロームは執務室を目指して歩き出す――、しばらく行くと廊下の壁によりかかるようにして立っている人間がいた。白いシャツに黒いスラックスで、何故か足下は素足だった。
「え……、どうして……」
頭に白い包帯を巻いたリボーンだと目視できた瞬間、彼はずるりと壁に寄りかかって崩れるようにその場にしゃがみ込んだ。
「リボーン!」
声をあげてクロームはリボーンに駆け寄った。蒼白の顔にじっとりと汗をかいていたリボーンは、寄り添うように座り込んだクロームの顔を見ても表情があまり変わらなかった。ぜいぜいと息をするばかりで何も言わない。
「どうしてここにいるの?」
「おまえ、は――」
「了平さんに言われて、様子を見に来ていたところだったの。どうして、あなたがここにいるの?」
「つ、ツナは――」
「ボスなら鳥籠に向かったんじゃないの?」
「いなかった」
クロームは息を呑む。
「談話室にも、食堂にも、いなかった……」
「執務室は?」
「わからねー。まだ、確認してねーんだ」
リボーンは唇を引き結んで首を振った。彼の瞼は半分ほど落ちかけていて、今にも意識を手放してしまいそうだった。ごくりと唾液を飲みこんだリボーンは奥歯を噛みしめるようにして、壁に手をついて立ち上がる。クロームは両腕で彼の身体を抱えるようにして支えた。すると、ばたばたと慌ただしい足音が近づいてくる。クロームが目線を向けると、廊下の向こう側から赤髪の男が走ってくるところだった。あごにヒゲを生やした彼が、嵐の部隊所属のバーミリオンという男だということをクロームは瞬時に思い出す。
「あ! リボーンさん、クロームさん。うちの隊長、ハヤトのこと見なかったか?」
「いいえ。見てないわ」
「おまえ、ツナのこと見なかったか?」
クロームの言葉に重ねるようにリボーンが言う。リボーンの普通でない様子を感じ取ったバーミリオンは、顔をしかめてあごを引いた。
「俺はボスの姿は見てねぇ。ハヤトもボスの身柄を確認しにこっちに来たはずなんだ。第三邸に向かうために車庫に行ったら警報が鳴りやがって……、駆けだしていなくなったハヤトが戻ってこねえし、携帯電話も繋がらねぇんで、いま、手分けして屋敷んなか捜してるとこなんだが――」
「執務室に行くぞ」
「ええ」
「あ、はい」
クロームの手を借りながらリボーンが歩き出す。
バーミリオンも同じように歩き出した。
廊下を歩き、いくつかの通路を曲がっていく間、三人とも口を開かなかった。他の二人は分からないが、クロームは、何か嫌な予感が胸のあたりに漂っていて気分が悪く、話をしたくなかった。嫌なことを口に出すことはあまりしたくない。綱吉の姿を一目見ることが出来れば、脳裏に浮かぶあらゆる危機的な状況を一掃することができる。それがどんなに幸せなことか、きっと思い知ることができるだろう。
数歩先を歩いていたバーミリオンが通路を曲がった途端、何も言わずに走り出した。その反応の仕方が異常だったので、クロームの心臓はどきりとした。手が触れていたリボーンの身体も一瞬こわばった。
クロームとリボーンが互いに身を寄せ合いながら角を曲がると、数メートル先の廊下に誰かが倒れていて、近くにバーミリオンが座り込んでいた。
「クローム……ッ」
動かない身体のもどかしさからか、リボーンが苦しげにクロームの名を呼ぶ。クロームは頷いて、今にも膝から力が抜けて座り込みそうなリボーンの歩行を助けながら、出来るだけ急いで彼等に近づいていった。
「……ベル」
「おい! しっかりしろ!!」
バーミリオンが倒れているベルフェゴールの肩を掴んで強く揺するが反応はない。リボーンを近くの壁にもたれかからせ、クロームは周囲を観察した。何かがあったとしたら、その痕跡が何かあるはずだ――、と考えながら辺りを見回していたクロームの目が少し離れた廊下の隅に釘付けになる。ベルがいつも頭にのせているティアラが壁際に転がっていた先に、鈍い銀色をしたものが、廊下の照明の光を受けて鈍く光っているのが見えた。クロームは落ちているものに近づいていく。
「気を失ってるだけみてぇですね」
バーミリオンの困惑した声音などクロームの耳にはほとんど届いていなかった。銀色のものが視認できるようになったからだ。
銀色のナイフ。
刀身が赤く濡れたペティナイフが落ちていた。
「……血……」
リボーンが呻くように何か言った。
クロームはその場で振り返る。
壁から離れたリボーンは、色の濃い絨毯のうえに膝をつく。おそるおそる伸ばした指先で絨毯に触れて――、持ち上げる。
白い指先が赤黒く湿って汚れていた。
「誰、の、血?」
クロームの問いの答えを知る者はここにはいない。
赤く汚れた指先を見下ろしていたリボーンは、急に顔を上げる。包帯に隠されていない右目がきつい光を宿してバーミリオンを睨み付けた。
「バーミリオン! うちの敷地内と敷地外を隔てている門をすべて閉鎖しろ!」
「え」
「いいから早くしろ!! これ以上、後手に回ると取り返しがつかなくなる! 門を施錠後、この騒ぎの前後に出庫した車を確認をするんだ、――間違いなく、うちの誰かが車を運転して外へ出て行ってるはずだ!」
「了解!!」
威勢のいい返事を残して、バーミリオンが走って姿を消す。
短く唸り声をあげながら一人で立ち上がったリボーンは、手を貸そうと近づいていったクロームを見て、低く吠えるように言った。
「クローム、オレを医療棟へ連れて行け。シャマルを引っ張ってきて、オレの身体を動けるようにさせるんだ」
「でも、リボーン……」
「おまえは、『あいつ』が死んでもいいのか」
「いや!」
悲鳴のように叫んで、クロームは首を左右に振った。
「そんなのいや。絶対に、いや!」
「なら、オレを犠牲にしてでもあいつの命を選べ」
「――馬鹿なことを言わないで。誰かを犠牲にして誰かを選ぶことをボスは望まないわ。あなたも犠牲になるなんて言わないで。あなたが死んだら私は泣くわ」
漆黒の、美しい瞳を一心に見つめながらクロームはリボーンの右手を両手で握りしめた。クロームの手よりも少しだけ大きい少年のてのひらを握りしめながら、クロームは震える声で訴えた。
「絶対に泣くわ。だから、そんな悲しいことは言わないで」
リボーンはクロームの両手で包まれていた片手を黙って見下ろしていた。
しばらくして、彼はクロームの手をやんわりと掴んだ。そして微苦笑のような表情を浮かべて、「そうか」と吐息のような言葉で答えた。
刹那、執務室の中から甲高い電子音が響きだした。クロームもリボーンも驚いて身を震わせる。廊下にリボーンを残し、クロームは執務室のドアを開いて素早く中に入った。カーテンが閉め切られた薄暗い室内――、執務机の上で何かが光っている。近づいていくとそれは携帯電話だった。素早く携帯電話を掴んで部屋を出てリボーンの元へ戻る。彼はクロームが持ってきた電話を見ると無言で片手を差し出した。頷いて、クロームは彼の手に携帯電話を託した。
片手で器用に折り畳み式の携帯電話をひらいたリボーンは、包帯に覆われていない右耳に携帯電話をおしあてる。クロームもリボーンに身体を寄せて、携帯電話に耳を近づけた。
「誰だ?」
『そちらは誰だ?』
「………………」
『リボーンか?』
少し小さいが男の声がクロームの耳にも届く。
「そうだ。オレがリボーンだ」
『ならば話は早い。リボーン。ドン・ボンゴレの生命が大事ならば我々の指示に従え』
「沢田綱吉をどこへやった?」
『貴様の生命と引き替えに無事に返そう』
「……それはできねえな」
『己の生命が惜しいのか?』
リボーンがシニカルに笑って唇を歪める。
「命が惜しい訳じゃねーさ。あいつのためにオレが死んだりしたら、あいつは何の躊躇もなく後追い自殺するぞ? あいつはそういう奴だ。オレがよく分かってるんだよ。阿呆が。そんなことも分からねーから、こんなことをしでかしてるんだろうけどな。かくれんぼなんてしてねーで出てこいよ。相手をしてやるぞ?」
『――どうやらなぶり殺しになりたいようだな』
憤りを押さえ込んだような男の声音をリボーンは鼻先で笑い、あっさりと切り捨てた。
「過剰な悲劇的演出で酔ってるようなパフォーマーなんぞに、殺されてやるようなリボーン様じゃねえんだよ。くそが。あいつに何かしてみろ。血の一滴も残さずにこの世界から末梢してやる」
『それでは、貴様の死体は豚にでも食わせるとするよ。アルコバレーノ。死んで、ソドムの購いをしろ』
通話はそこで切れた。
リボーンは携帯電話を冷たく一瞥してからふたつに折り畳み、シャツのポケットへ入れた。
「誰?」
リボーンは肩をすくめて息を吐く。
「だいたいの目星はつくが……、オレの敵だってことは確かだろうな。これで確定だ。ツナが拉致られた。たぶん、獄寺か……もしくはスカルが一緒だろう。大人しく敵の言うことに従ったことと絨毯の血痕から考えて――、誰かが怪我をしてて、互いにかばい合ったんだろう。とりあえず、ツナだけが拉致された訳じゃなく、獄寺かスカルが一緒ならば少しはマシな状況ってことか――」
独り言のようにぶつぶつと言い始めたリボーンの背中にクロームは片手で触れる。リボーンの黒い瞳がクロームを見上げて、ゆっくりと瞬いた。深い思案のなかへ潜りかけていた瞳がクロームをとらえ、そして真っ直ぐに見上げてくる。
「手を貸すわ。医療棟へ行くんでしょう?」
「わりぃな」
クロームはうっすらと汗を滲ませているリボーンの顔を見つめながら、静かに宣言した。
「私も行く」
「あん?」
眉をひそめてリボーンが言う。
「なに言ってやがる」
「元・霧の守護者として、あなたの動かない手と見えない目のかわりになる」
「前線を退いて何年も経つおまえが役にたつのか?」
「十代の、いちばん記憶に残るあいだ、ずっと戦っていたのよ? 忘れるはずもない。それにまだ私の一部は骸様と繋がっているの。そこらへんの術者よりは力になるわ」
クロームは片手を胸元にそえ、心の底から思っていることを声に出した。
「私を犠牲にしてもいいのよ。リボーン。私はボスの幸せのためならばこの身を捧げても構わないと思っているわ。だから、私を好きなように使っていいのよ」
リボーンがひどく驚いた様子でゆっくりと目を見開いていく。
衝撃が波紋となって消えていくかのように、リボーンは細長く息を吐いて目を伏せた。
「――そうか」
彼は伏せていた目を開いてクロームを射抜くように見た。漆黒の、形のよい目には確固たる強い意志が宿り、勇猛な気高さすら秘められているようだった。
「おまえも、そうとうの馬鹿だな」
「……あなたもそうでしょう?」
リボーンは双眸を細め、口角をつりあげる。
クロームも微笑んで、片手を右目に添えてあごを引く。
「そして、きっと――。あの人も」
「ねーぇ、あのさァー」
気怠そうな声が下方からかかり、クロームとリボーンは下を向く。床に俯せの体勢のまま、ベルが顔だけをあげて不満げに唇をへの字にしていた。彼はクローム達の視線を受けると、両手を絨毯について身体を起こした立ち上がった。動いたせいでどこかが痛んだのか、ベルは眉間に深いしわを刻んで片手を頭のうしろへ回す。
「あー、いてて。俺も、その馬鹿に加えてもらいたいんだけど、いい?」
「ベル。――誰にやられたの?」
「ツナヨシだよ、ツナヨシ! 手加減してくれねーんだもん。ちょう痛かった! クソッ! あ、――ハヤトは? くそっ、やっぱり追いていかれちゃったのかよ。ひっでーな、二人とも」
「いったい、何があったってんだ?」
リボーンの問いかけに、ベルは事の経緯をすらすらと答えた。
どうして、綱吉が相手の言うことに従ったのか。
誰が血をながしたのか。
原因と現状の結果が繋がったとしても、最悪なことに違いはない。
「ベル。携帯電話持ってるか?」
「んあ? んー、持ってる」
上着の胸ポケットから薄型の携帯電話を取り出したベルは、リボーンにそれを手渡した。彼は思い出す間すらなく、携帯電話のボタンを素早く押して耳に押し当てる。
「――スカル。ツナが拉致られた」
『なんだと!?』
周囲が静かなせいか、スカルの声が携帯電話から漏れてクロームの耳にも届く。
『くそ、……すまない、リボーン先輩』
「いいさ。どうせ、おまえがいたところで、ベル同様にツナに殴られて昏倒してただろうしな」
『いま、どこにいるんだ? 合流する』
「執務室の前だが、すぐに病棟へ戻る。――スカル、沈黙の棺の場所は分かるか?」
『沈黙の棺? 監禁部屋のことか? 詳しい場所までは――』
「分かった。今からシアンという男の携帯の番号を教えるから、誘導してもらえ」
『いったい、何をさせるつもりだ?』
「アホ牛の監禁を解く」
『……それは、あんたの独断でか?』
「ああ。そうだ」
『いいのか? これ以上、立場が悪くなると厄介じゃないのか?』
「オレの立場? そんなもの、この際知ったこっちゃねーぞ」
スカルの言葉を鼻先で笑い、リボーンは挑戦的な瞳で誰もいない無人の廊下を睨み付けた。
「大事なのはツナの命。それだけだ」
『――わかった。番号は?』
リボーンは口早にシアンの携帯電話の番号を言った。スカルは番号を違えることなく、繰り返す。
『沈黙の棺からランボを出して、奴と一緒に病棟へ行けばいいんだな?』
「ああ。オレがいた病室で落ち合うことにするぞ」
『了解。――あんまり、無理するんじゃないぞ、先輩』
「いま無理しておかないで、いつ無理しろってんだ?」
『……減らず口……』
スカルの言葉を鼻で笑い、リボーンは耳元から携帯電話を放して折り畳み、ベルへと差し出した。ベルは受け取った携帯電話を上着のポケットにしまう。
「ランボ、棺から出すんだ?」
「これはうちの内乱で、ボヴィーノが関係してる訳じゃねーだろ。だったら、あいつを監禁しても意味はない」
「あいつに何かやらせるの?」
「今回のことで、あいつは屈辱を味わったからな。名誉挽回のチャンスがあったっていいだろう」
「あ、そう。――ならさ、王子も行くよ。ツナヨシを助けに行くなんて、面白そうじゃんか」
「いや。おまえは駄目だ」
「なんでだよ。みんなで俺ばっかハブりやがってー、ちょうイライラするんですけど!」
「そう怒るんじゃねーよ。ベル。ヴァリアーには、ここを――、ボンゴレ自体を守っていてもらいたい。頼めないか?」
「あぁん? ここを守るってどーゆーことよ?」
「オレも、他の守護者達も、出来る限り動いているが限界ってもんがある。ベルやスクアーロ達には、ボンゴレの屋敷で指揮にあたってほしい」
「そうすりゃ、リボーン達が自由に動けるってことね」
「ああ。そうだ」
「あー、あ。……なるほどね。分かったよ。じゃあさ――」
綱吉に殴られた頭が相当痛かったのか、しきりと頭の後ろを片手で撫でながら、ベルは不機嫌そうな顔のままでぶっきらぼうに言った。
「ついでにさ、建物に仕掛けられてるっていう爆弾処理の任務もさ、俺達に任せてくんない? 悪いようにしないから」
「ヴァリアーにか?」
「たぶん、監視してる奴がいて、連絡がきたら爆破する手筈だろうからね。うちらが監視者を殺すから、あとはボンゴレの爆弾処理の人に爆弾処理してもらうってので、どう?」
「相手がどういった奴らで人数も知らねーのにいいのか?」
「なに言ってんの? 王子達のこと、なんだって思ってるわけ? ヴァリアーなんだぜ?」
馬鹿にするなとでも言いたげに、すねたように言ってベルはわざとらしく猫背になってリボーンの顔を見下ろすようにする。男性として長身なベルと成長過程であるリボーンとでは身長差がはっきりとある。ベルの行動が気に障ったのか、ほとんど包帯に隠れているリボーンの顔が苛立ちによって引きつったのがクロームには分かった。
「すぐにボスに連絡して人数を集めるよ。ちょう精鋭ばっかでね。だからあんた達は何の心配もしないでツナヨシのことを追いなよ。そんでさ――」
じっとりとベルを睨み付けていたリボーンの眼前に人差し指を突きつけ、ベルは挑戦的な笑みを浮かべて口角をつりあげた。
「しっかり取り戻してきてよ。ボンゴレの、俺達の――、そしてあんたの、大事な大事な『大空』をさ」
|
|
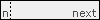 |