|
「おやおや、これは本当にひどい」
ノックもなしにドアを開け開口一番に言い放った六道骸は、あっけにとられている綱吉に構うことなくドアをしめて入室した。
ちょうどランボと入れ違いになったわりには、ランボがやってこないことが不可解に思えた。骸はいちいち用もないのに執務室に入り浸り、綱吉にやけにからんだり接触したりを繰り返すのと、骸と綱吉を二人きりにはさせられない!と常々、獄寺が言っているのを他の守護者たちも聞いているせいか、最近では骸と二人きりになることは少なくなっていた。おそらく骸はランボが部屋から出ていったのを見計らって、十分な距離がとれてから執務室のドアを開けたのだろう。
綱吉はにこやかな骸を椅子に座ったまま見上げ、首をかしげる。
「ひどいって、なにが? このデスクの上がってこと?」
「あなたの顔色ですよ、綱吉くん」
「そう?」
答えながら、綱吉は骸に命じていた仕事の種類を思い出す。彼に頼んでいたのは治安に関する情報収集だったはずだが、彼の手には小さな紙袋がひとつだけだった。
「ドクターから話を聞いたんですよ。昨日は大変な目におあいだったとか! 仕事帰りに美味しいと評判のお店に立ち寄って、苺をおみやげに買ってきましたよ」
骸は綱吉のデスクの前までくると、とてもいい笑顔で右腕を振りかぶり、机の上にきちんと処理済みと処理前とで仕分けしていた書類や資料などすべてをものの見事薙ぎ払った。ばさあと音をたてて百枚近い紙が舞い上がって宙を舞う。書類の山がなくなった机に腰をかけた骸は、紙袋のなかから小さなかごをとりだし、そこに盛られている赤く熟れた苺のひとつを右手でつまんで、綱吉の眼前にさしだして、にっこりと笑う。
「はい、あーん!」
綱吉は頭痛のする頭を右手で支えた。
「えっと、とりあえずデスクから降りてください。で、なぎはらった書類を一緒に拾ってください」
「あーん!」
「――あーん……」
引き下がらない骸の態度に降参し、綱吉は目の前に差し出された苺を口を開けて受け入れた。甘い苺をかみ砕いた綱吉は、脱力して椅子の背にもたれた。
「もう、よけいな仕事ふやさないでよ……」
「あーこれはもうだめですねー、綱吉くん、あれですよ、休憩しましょう!」
「――むーくーろー……」
「ちょっと談話室にいきませんか? 紅茶でも飲みながら、一休みしましょう。あとで一緒に書類の整理しますから、ね?」
可愛らしく首をかしげる青年を椅子に座ったまま見上げ、綱吉は彼を観察する。見ようによってはパイナップルのシルエットとよく似た髪型をしているのに、顔立ちが恐ろしいほど整っているため、おかしな髪型すらデザインされた洗練さが漂っていて不思議だった。右目が血のように赤く、左目は青い。オッドアイの人間を綱吉は彼以外知らない。そもそも瞳のなかに数字が浮かんでいる人間も骸しか知らない。ついでに骸を人間という種類にくくっていいのかさえ、綱吉には分からなかった。
綱吉に見上げられているあいだ、骸は少しも動じる様子なく、ニコニコと笑い続けている。その笑顔がくせ者で、綱吉はいつだってその笑顔に押し切られてしまいがちになる。
はあ、あ、と切れ切れに息をついて、綱吉は椅子から立ち上がる。
「骸はさ、オレのことを疲れさせる天才だよね」
「お褒めいただき光栄ですよ、ボス」
「褒めてないんだけどね」
「分かってますよ、ボス」
綱吉がじろりと睨んでも、骸は気にする様子もなく執務室のドアに向かう。綱吉も彼の後を追うように歩き、二人は執務室をあとにした。
廊下を歩いて談話室を目指す。談話室とは、綱吉や守護者たちが集まって、他愛のない話をしたり、ビリヤードをしたりする娯楽室のような場所だ。途中で出会ったメイドの一人に、骸は紅茶の用意を二人分頼み、持っていた苺いりの籠も手渡して皿に盛るように言った。メイドはうやうやしく一礼して、優雅に歩いていく。
「寝ていないでしょう?」
談話室について綱吉がソファに座ると、彼がすぐに言った。
「リボーンも同じでしたね」
ローテーブルをはさんで向かい側に座った骸に、綱吉は思わず驚いた視線を投げる。
「リボーンと会ったの?」
「おや、リボーンも寝不足のはずなんですか。ただ、かまをかけただけです。そうですか、愛人との情事で寝不足とはずいぶんと爛れてますねぇ。はれんちなボス!」
骸は両手で頬をはさんでおおげさなリアクションをする。
綱吉は舌打ちしたあと、片手で額をおさえる。
「骸はさ、ほんとさ――」
「お褒めいただき光栄ですよ」
「何も言ってないよっ」
骸は上機嫌そうに笑っている。綱吉はいつも骸の笑顔がよく分からなかった。なにか大切な想いがあったとしても、それすら仮面のような笑顔で隠されてしまっているような、奇妙な違和感がいつも骸の笑顔にはついてまわる。
「ねえ、綱吉くん」
「なに?」
「僕がリボーンを殺してあげますか?」
「は?」
「君を食い潰す存在を僕は許せないんですよ」
「なに、笑ってすごいこと言ってんの、骸ってば」
「本気ですよ。ボス。僕はね、君という存在を脅かす者はすべて気に入らないんです」
「駄目だ。リボーンに手をだしたら許さない」
骸は右手をあげてかなしげに眉尻を下げる。
「そう。君にそう言われてしまえば、僕はお座りをして待つしかないんですよ。わん」
「ふざけるなって。もう」
綱吉が呆れるようにつぶやくと、彼はきゅうにしおらしい表情になって優しく囁く。
「でも、お願いですから、今夜は私邸に戻らずに、どこかホテルで休んでください。どうせリボーンも一緒の寝室なのでしょう? そんなところでやすらいで眠れるはずはないでしょう? 眠らないでいればいるほど、判断能力も体力もなくなっていきますから」
「いや、それは無理。――帰らないと」
骸の表情は変わらなかったが、目の色だけが異様なほど鋭いものに変わる。そんなときこそ、骸がより人間らしく見えることに、綱吉はなんだか奇妙な気分になった。
「そんなにあのガキが好きですか?」
綱吉は微笑んでみせる。昨夜は散々めちゃくちゃにされたが、結局は嬉しさが残った。彼は何度も綱吉の身体で果てたし、綱吉も彼の手で何度も果てた。キスも数え切れないほどし、どんなふうに彼の指が綱吉の身体のうえを這い回ったのかも覚えている。無理矢理に始まった情事だったかもしれなかったが、綱吉にとってはそれは十分に愛のある行為だった。
骸は面白くなさそうに唇を噛んだあと、首をかしげた。
「君のその愛情は、ひな鳥のインプリティングと同じなんじゃないんですか? 幼いころから共にいつづけた結果、精神的に強く残っているという印象だけで思いこんでいるだけでは?」
「いや、それはないよ。オレ、中学時代に好きな女の子いたんだけど、それと同じだから」
「そのときは女の子だったんですよね? でも今じゃあ、男に欲情するっていう意味ですか? じゃあ、僕にも欲情します?」
「骸にまで欲情してたら、オレって変態じゃないか」
「なんだか、今更ですけど。リボーンにむらむらしちゃってるんですから、綱吉くんはその時点で、けっこう変態だと思いますけどね」
「ぐ、……なんか、こう、言いづらいことを言うよね、骸って」
「十三歳も年下のガキを抱きたいって?」
「あー……」
「おや、もしかして逆ですか? それは驚きです。十四歳でも挿入――」
ソファから立ち上がってローテーブルに手をつき、もう一方の手で骸の口をふさぐ。事実だとしても、実際に声に出して言われるとなけなしのプライドが崩れていきそうになる。刹那、べろりと手のひらを舌で舐められ、綱吉は驚いて手を放した。悪戯っぽく口を開いて舌を動かす骸を睨みながら、綱吉はソファにどっかりと勢いよく座り直す。
「そうだよ、悪いかよ、むらむらして! 十四歳のガキに主導権にぎられてんの、おかしいかよ!」
「ううっ、僕の綱吉くんがどんどん愛人とのつきあいで、ただれていきます」
「ちょっと待って。いつからおまえのになったの、オレ」
思わず綱吉は声を立てて笑った。両手で顔を覆って泣き真似をしていた骸は、顔から手をはずして「くふふ」と笑い声をたてる。
「もっと笑ってください。綱吉くんが笑ってくれないと、僕はつまらないんですから」
執務室を訪れたときから今までのことすべてが、綱吉を笑わせるためだけの行動だったのだろう。ようやく彼の行動の意図がよめ、綱吉は感謝の気持ちで目頭が熱くなる。彼はいつだってふざけた人間だったが、綱吉の心のさざ波をいつだってめざとく見つけるのは骸だった。彼は六つの輪廻を巡ったおかげなのか、人間の感情のゆらぎに関しては、ひどくめざとい。長年のつきあいになる獄寺や山本すらだませることができても、いつも彼だけはだませない。
「ありがとう。骸」
骸は綱吉の礼の言葉が染み渡るのを待つかのように目を閉じて微笑む。
扉をノックする音がした。
綱吉が答えると、ドアがひらいて、先ほど骸が声をかけたメイドと年若い執事が姿を見せる。執事はドアを開けた脇に立った。メイドは銀のトレイを手に室内に入ってきて一礼し、綱吉たちが座るソファへと近づいてくる。紅茶が入ったポットと二揃いのカップ、ガラスの器にもられたヘタのとれた苺をローテーブルにきれいに配置する。ポットをかたむけ、綱吉と骸のかっぷに紅茶を注ぎ入れたあと、メイドは深々と二人に一礼する。
「他にご用がありましたら、電話でなんなりとお申し付けくださいませ」
メイドは銀のトレイを抱え、部屋を出る前にもう一度一礼をして廊下に出る。執事はメイドが廊下に出たあとで、自分も一礼をし、ドアを静かに閉めた。
温かい紅茶のカップに唇をつける。よい香りと味が舌先にひろがる。温かい飲み物は心をと落ち着かせるにはじゅうぶんの効力があった。
「あのう、綱吉くん」
「はい?」
「リボーンの本当の気持ち、知りたくありませんか?」
思わず綱吉は顔をしかめてしまった。
「リボーンは、さ。オレのこと疎ましくなってきたんだと思うよ。同情ひいて愛人になってもらったけど、あの日から一度だって、前にみたいに笑ってくれなくなったし……。いい加減、離れたいんじゃないのかな……」
「はたして、そうでしょうか?」
色の違う骸の目が、じっと綱吉の首元にそそがれる。包帯は今朝、鏡をみながら綱吉が自分で巻いた。かさぶたがはがれかけていた傷跡の痛々しさを隠すためだったが、周囲にいやらしいほど散らばっているキスマークを隠すためといったほうがいいくらいだった。
「綱吉くん、その首の傷、自分でつけたでしょう?」
「え、いや、これは――」
「僕を侮らないでください。六つの生を巡ったんですから、相手の性格などが分かれば、やりそうなことなど想像がつくものです。――リボーンはね、おそらく、君が自傷をするのを恐れている。それを利用すればいいんです」
「またやれってこと?」
「いいえ。逆です」
「逆?」
「リボーンを殺そうとしてください」
「は、あ?! おまえ、それ、適当に言ってない?」
「おやまあ、失礼ですね。本気ですよ。このままあと数週間もすれば、君は思い詰め、リボーンを殺して自分も死ぬ!なんて言い出しそうじゃないですか。体の関係をもっても、愛情に対して疑念があれば、いくら体をつなげたって意味のないことですよ。それはもう、分かってるとは思いますけど」
「骸はずけずけ言うね」
「いまさら包み隠して話す年ですか、僕ら」
骸の視線を受けて、綱吉は肩をすくめる。
「オレがリボーンを殺そうとして、それがどうしてリボーンの気持ちを知ることができるってなるわけ?」
「リボーンがあなたに殺されることを了承したら、それは愛の告白と同じことですよ。あのリボーンが心中してくれと言って心中してくれますか? 利己主義のかたまりのようなあのガキが、自分の未来を捨てて、あなたの手で死のうとするなんて、理由なんてひとつに決まっています」
「却下」
「なんでです? いい作戦じゃあありませんか?」
「殺気のない戦いをふっかけても、あいつは見破るよ」
「じゃあ、僕がどうにかしますから任せてください」
骸は片手を胸にそえてにっこりと笑う。
綱吉は骸に負けじとにっこりと笑ってばっさりと言った。
「すごい、ものすっごい、信用できない」
「まあまあ、部下を信じてくださいよ、ボス! このままじゃいけないことくらい、あなたは分かっているのでしょう。あなたは手の内をすべて見せすぎです。僕があのガキのカードのひったくって来ますよ。だいたい、あのガキのせいで綱吉くんがこんなに困ってるのが許せません」
骸は苺を口の中にひとつ頬張る。綱吉は紅茶をひとくち飲んでから、苺を口に入れる。よく熟した苺は甘く、ひさしく感じていなかった食欲がすこしわいてくる。二個目の苺を綱吉が頬張るのを見つめていた骸は、出会った頃の彼から想像もつかない優しい顔をみせる。できることなら、綱吉だけにではなく、他の人間にも同じように優しく接してくれるようになれば、きっと彼を取り巻く人々の評価も格段に変わるのではないだろうか、と思うことがある。けれど、彼は綱吉以外には決して、いま彼が浮かべている表情を見せることはない。
骸は微笑んで、愛らしさというものを計算しつくされたように首をかしげる。
「僕に任せてください。あなたの忠実な下僕に」
「……お互いに怪我をしないって誓える?」
「あっちが手を出さない限りは」
「無理そうな気がするんだけど」
「双方、怪我のないようにしますよ。だいたい、僕には幻影という能力があるんですからね」
悩みながらも、綱吉は苺を口にいれる。いちど、食べ始めると手がとまらない。五個目の苺を食べ終えたとき、寝不足のせいもあってか食欲がわかずにいたので、忙しいからと言って昼食をとっていないことを思い出す。どうりでおなかが減っていた訳である。九個目の苺を食べ終えたあと、あまりにもいやしい食べっぷりだったのを反省して紅茶を飲む。
骸は組んだ足の膝のうえに両手をおいて、苺をむさぼり食べている綱吉を眺めて微笑んでる。
「だいたいね、あなたを愛するつもりがないのなら、僕はリボーンには消えてもらいたいんですよ。ほんとは殺したいですけど、それは君が許しそうもないですから。文字通り、目の前から消えて欲しいって事なんですけどね」
「……骸……」
「けじめをつけましょう。ねえ、ドン・ボンゴレ。これ以上、バランスをとり続けるには足場が悪すぎますよ」
正直な話、昨夜のリボーンの仕打ちすら、綱吉は許してしまっている。きっとリボーンは綱吉に嫌われ、遠ざからせようとして、あんな仕打ちをしたのだ。言葉の端々、仕草の端々に、そんな彼の意志が伺えた。綱吉を駄目にしたくないと思って離れていこうとするリボーンを手放せない自分は我が儘なのだろうか、と、綱吉はぼんやり考える。このままでは、きっと次第に綱吉とリボーンの関係性のゆがみが、ボンゴレ自体へのゆがみに発展するのも遅くはない。それは避けねばならない。
どんなに異常な恋に狂っていようと。
どんなに愛を貪欲に求めていようと。
沢田綱吉は血の一滴まで、ボンゴレファミリィのためにあるのだから。
紅茶のカップから視線を持ち上げ、骸を見る。彼は目を離したときと同じ姿勢のまま、いつの間にか頬張っていた苺を飲み込んだところだった。
「リボーンは、今日は獄寺くん達のお見舞いに行ってるはずだよ。そのあとはここに来る予定だったと思う」
「分かりました。綱吉くんは、執務室でなくて、客室のほうでゆっくり眠っていてください。いま、クロームを呼びましたからね、寝ないとすぐに僕に分かりますから」
「え、ちょっと。クロームは今日は休養日だろう? 呼び出すなよ」
「彼女、休養日だったんですか? さっき、邸内でみかけましたよ。良い花をみつけたそうで、玄関の花瓶の花を取り替えているところでしたから。いま呼びましたから、すぐにここに来ますよ。さ! そうと決まれば客間に行ってください。僕は執務室に行きます」
立ち上がった骸につられるように綱吉も立ち上がる。
「……執務室、壊れたりしないよね? 大事なものとかあるんだからね?」
「リボーン次第ですかね」
「心配だ」
ソファから離れてたった綱吉の近くに骸は近づいてきて立った。
「綱吉くんは、リボーンに恋愛対象として見て欲しいですよね?」
「恥ずかしいことを面と向かってきくね、おまえ。――そうだよ」
「リボーンが恋愛対象として綱吉くんをみることができない、って分かったらどうします?」
一瞬、綱吉は骸を睨んでしまったが、細長く息を吐いて目を伏せる。
「もうこんなの、終わりにするよ。ガキの我が儘が押し通せる訳ないって分かってるのに、し続けてみんなに迷惑かけたしね……。きちんと選択する」
「綱吉くんの意向はわかりました。――クローム。早かったですね」
骸がドアへと声をかけるのと、ドアが遠慮がちにノックされるのは同時だった。綱吉が入室を許可する声をかけると、ドアはそっと開かれ、黒いワンピースドレスをきたクローム・髑髏がゆっくりと入室してきた。
綱吉たちが立っている場所まで近づいてくると彼女は優雅な仕草で会釈をした。長い黒髪がさらりとゆれて、再びまたもとの美しい直線のながれにもどる。
「こんにちわ。ボス。骸様」
ほんのり分かる程度にクロームは微笑む。あまり感情を豊かに表現できないのが彼女の特性でもある。彼女のそっと溶けるような微笑は、どこか儚げで守ってやりたい衝動を呼び起こさせる。綱吉はクロームにむかって、にっこりと笑いかける。
「やあ、クローム。玄関の花を取り替えてくれたんだってね、ありがとう」
「いいの。散歩していて、花屋のまえを通りかかったら、良い花があったから」
「休養日なんだから、きちんと休めばいいのに」
「どうせ部屋にいてもすることがないから、ここにきてボスの側にいた方がいいの」
「さあ、クローム。綱吉くんは寝不足なんです。客間のベッドにどんと突き飛ばして、彼が寝るのを監視していてください。あ、駄目ですよ、同じベッドで寝ちゃあ!」
「骸!」
「分かったわ、骸様」
「え、その場合、どこが分かったってこと?」
「ボス、行きましょう」
クロームの手が綱吉のスーツの袖に触れる。彼女の優しい表情に導かれるように、綱吉は一歩を踏み出そうとした。
「あ、ちょっと待ってください」
「え?」
骸は戸惑っている綱吉に構わず、両腕を広げて綱吉の体を抱きしめた。背の高い彼に抱きすくめられると視界が遮られる。見上げてみれば、骸のキスが額に落ちるところだった。
「ちょ、骸!」
「下僕にささやかな祝福をください」
右目の下に唇が触れる。思わず目を閉じると、至近距離で骸のひそやかな笑い声が響いた。案外簡単に抱擁をといた骸は、穏やかに微笑んで片手を顔の横まで持ち上げて、上品に指を動かした。
「おやすみなさい。綱吉くん。起きるころには結果がでているころでしょう」
綱吉は微笑する骸の顔を眺めた。綱吉は彼の好意を知っている。利用している自覚はある。残酷なことをしていると分かっていても、利己的な感情は抑えきれない。なんとも情けない思いに気分を沈ませ、綱吉は彼に頭を下げる。
「――変なこと、頼んでごめん。骸。でもオレ、もう自分じゃ終わらせられないや」
「頼ってくださって結構ですよ。もっと頼って欲しいくらいです」
胸に右手をそえて骸が微笑む。
綱吉は彼に向かって、心の底から感謝をの意味を込めて、微笑む。
「ありがとう。骸」
|
|
××××× |
|
綱吉とクロームが連れ立って部屋を出ていくのを見送った骸は、顔に張り付いていた微笑を取り去って、執務室の椅子に腰を掛けた。
普段、仕事中に綱吉が腰掛けている
椅子に身を預け、目を閉じる。肘置きを指先で愛おしくたどる。綱吉がいつも見ている景色を同じ場所に座って眺めていることに、骸は喜びを感じて唇に笑みをのせる。
「さて」
スーツの内側から細長い筒を取り出し、その中から、一本のスティック型のお香とお香立てを取り出す。スーツのポケットから小さな箱入りの棒マッチを手に取り、お香に火を灯す。甘ったるい香りが白い煙と共に室内に立ち上り始める。
ゆらゆらとゆれる白い煙を見つめながら、骸は右手で右目に触れる。
「綱吉くん。――あなたを苦しめる者はすべて僕が消してあげますからねぇ。やすらかに眠っていてください。僕の愛するファムファタール」
深紅の目を細め、骸は愉悦に酔うように微笑した。
|
|
××××× |
|
客室に備え付けのバスルームで、スーツからバスローブに着替えた
綱吉は、バスルームの外で待っていたクロームに脱いだスーツを手渡した。彼女は丁寧にそれらを畳んで、部屋に備えられたシルバーのワイヤーバスケット――クリーニング店へひとまとめに回収される――へと入れた。
綱吉は客間――と、いってもホテルのスイートルームくらいは整えられた――のベッドに膝で乗りあげ、布団の中に体をもぐらせる。クロームは窓際のテーブルセットから椅子を一脚両手で抱え、ベッドサイドに椅子を置き、そこへ座った。人形のように無表情のままの彼女は美しく、綱吉は彼女といても、女性と接しているような気分にはならなかった。性別という概念がひどく曖昧な印象がクロームにはあった。美しい。綺麗。そんな言葉だけに意味があるかのように、彼女は綱吉の目の前に存在していた。
「クローム、ごめんね」
「いいのよ。ボス。気にしないで」
「だってせっかくの休みだったのに。オレの子守役なんてしなきゃならないなんてさ。骸のやつ、あとで言ってやらないと――」
クロームはうすく微笑んで、首を左右に振る。
「ほんとうにいいの。私、ボスや骸様の役にたてるのうれしいから。ボスにも頼って欲しかった。こんなになるまで一人で耐えるのはよして。私でいいのならいつだって呼び出して」
「ありがとう。クローム。その気持ちだけでもオレはとても嬉しいよ。……クロームも今回のことで、いろいろ迷惑かけちゃって、ごめんね。でも、もうすぐ、決断するから、それまで待っててね」
「ボスはあのヒットマンを愛してるのね」
透き通ったクロームの声に、綱吉は枕に頭を預けたままで、呼吸を止める。緊張が行き渡った体から息を吐き出しながら力を抜き、綱吉は微苦笑をうかべる。
「あいつを想う感情がそう呼べれば幸せなんだけどね」
「ヒットマンもきっとボスを愛してるわ」
「そう、かな?」
「私には分かる」
「どうして?」
「女の感」
とぼけた様子もなく、クロームが真剣な顔で言うので、綱吉は吹き出してしまった。クロームはわずかに目を伏せ、愛らしく口元をゆるませる。
「笑ってもらえてよかった」
「え、クロームって冗談なんて言うキャラだった?」
「ボスには笑っていて欲しいから」
「うん。ありがとう。すこし元気がでてきたよ」
綱吉が明るく言うと、クロームはまるで母親が子供にするように、綱吉がもぐった布団のうえに右手をのせ、首をかしげる。美しい長い黒髪が彼女の仕草にあわせて、音もなくゆれた。
「さあ、眠って。ボス」
「んー、うん。――なんか、側に人がいると、こう、寝づらいね」
「ボスが眠れないのなら、私が寄り添って子守歌でも――」
「いや。それは別の意味で眠れないからよしてほしい、ほんとに。寝るよ、寝るからっ」
「――ねえ、ボス」
ぎゅっと目をつむっていた綱吉は、クロームの問いかけに目を開けた。彼女はじぃっと綱吉の顔を見下ろしている。
「うん?」
「ボスの手を握ってもいい?」
「なんだか、オレが言うべき台詞のような気もするけど。オレ、寝ちゃうけど、いいの?」
クロームがうなずく。綱吉は左手を布団から出して、彼女の前に差し出した。彼女は両手で綱吉の手をとった。やわらかく小さな彼女の手は温かい。綱吉は心地の良い他人の体温を優しく握り返して、目を閉じる。
「おやすみ。クローム」
「おやすみなさい。ボス。良い夢を」
クロームの声を聞きながら、綱吉はまぶたのうらにボルサリーノをかぶった少年を思い描いていた。骸がどんな答えを持ってくるかは分からない。離別の確率の方が高いだろう。綱吉はそれを覚悟しなくてはならない。眠れるような状況ではなかったが、左の手のひらを包む優しい体温と寝不足のおかげか、綱吉の意識は次第にうすれていった。
せめて夢のなかでは幸せであるように。
綱吉は祈りながら眠りにおちていった。
|
|
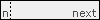 |